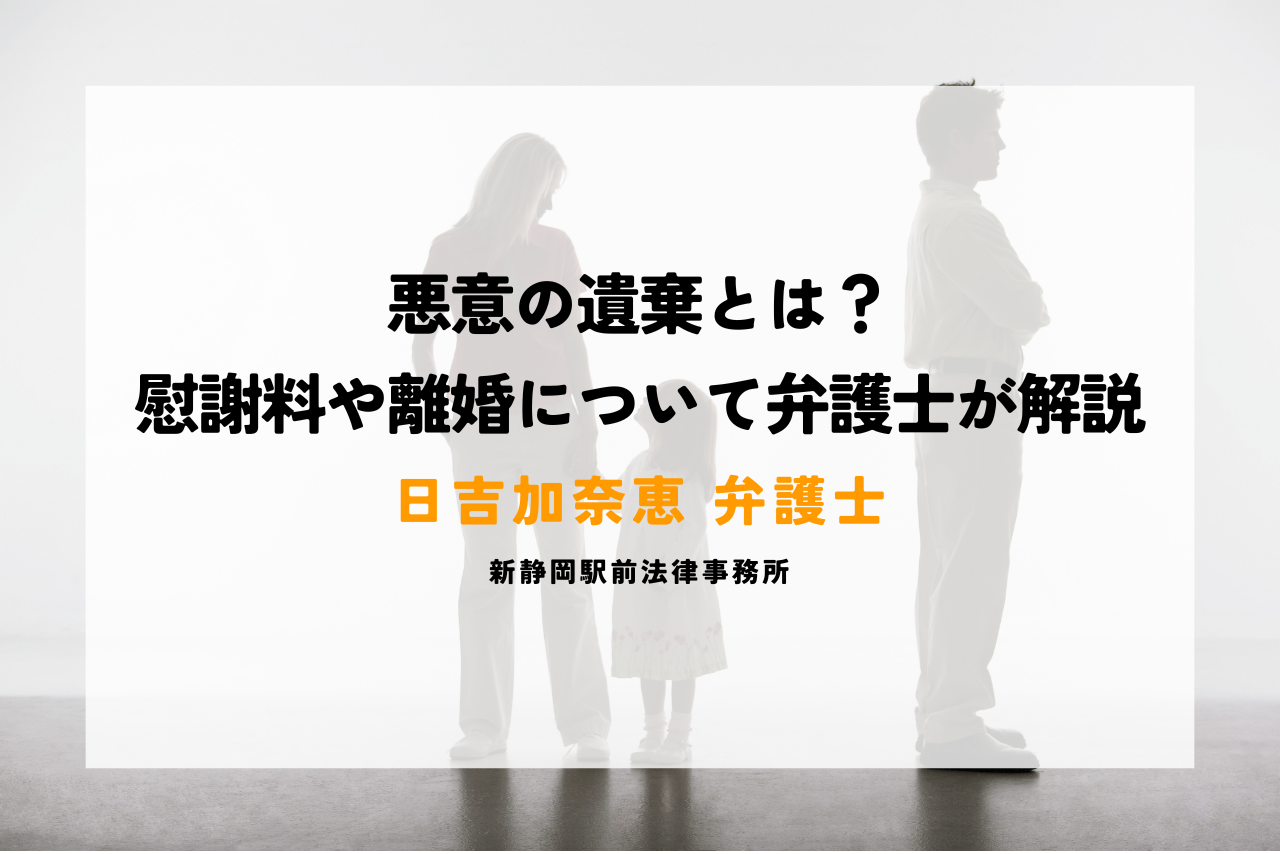突然配偶者が家を出ていき別居されてしまった場合や、配偶者が生活費を全く支払わない場合などには、悪意の遺棄を理由に配偶者に対し慰謝料や離婚を請求できる可能性があります。
そこで本記事では、悪意の遺棄に該当する条件や慰謝料について解説します。
目次
悪意の遺棄とは?
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務に反することをいいます。
民法第752条には、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと定められています。
同居義務とは、その名のとおり夫婦が同居するべき義務です。
ただし、単身赴任の場合など正当な理由がある場合は同居していなくても同居義務違反とはなりません。
協力義務とは、夫婦が生計の維持や家事、育児などについて互いに協力する義務です。
また、扶助義務とは、夫婦が同程度の生活首位準を保持できるようにする義務のことです。
これらの義務に正当な理由なく違反した場合には、「悪意の遺棄」に該当し、裁判上の離婚事由に該当して離婚が認められる可能性があります(民法第770条第1項第2号)。
悪意の遺棄に該当するケース
具体的には、以下のような場合に悪意の遺棄に該当する可能性があるでしょう。
- 無断で家を出ていき同居に応じない
- 理由もなく働かず、家事や育児も一切行わない
- 収入があるのに生活費を一切支払わない
- 不貞相手と同居するために別居し、生活費も支払わない
なお、悪意の遺棄にいう「悪意」とは、社会的倫理的に値するような、婚姻共同生活の継続を廃絶するという結果の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思をいうとされています。
単に育児や家事に非協力的であるといった程度では認められないこともあるので、注意が必要です。
悪意の遺棄に該当しないケース
逆に、以下のような場合には、正当な理由があるとして悪意の遺棄には該当しないと考えられます。
- 相手がDVをするので身を守るために別居をした場合
- 出産や介護のために別居をしている場合
- 病気等のために働けない場合
- 失業しており生活費が払えない場合
悪意の遺棄をされたらどうする?
①婚姻費用を請求する
相手が別居して生活費を支払わない場合には、婚姻費用(生活費)を請求するとよいでしょう。
婚姻費用とは、家族が通常の生活を営むために必要な費用のことをいいます。
基本的には収入が高い方が低い方に支払うこととなり、その額は双方の年収を基準に、裁判所が作成した算定表を用いて決定します。
婚姻費用は、相手方に正式に請求をした時(調停を申し立てた時など)から請求ができるため、早めに形に残る方法(内容証明郵便や調停の申立て等)で請求するとよいでしょう。
婚姻費用の請求方法については、以下のコラムで解説しています。
②離婚を請求する
前述のとおり、悪意の遺棄は、裁判上の離婚事由に該当します。
裁判上の離婚事由とは、訴訟(裁判)をして判決で離婚を認めてもらうための、法律で定められた離婚事由です。
裁判上の離婚事由がある場合には、相手が離婚を拒否したとしても、裁判を起こして離婚を認めてもらうことができます。
ただし、離婚裁判を起こす場合には、まず離婚調停を申し立てる必要があります。
これは、離婚などの当事者の身分関係に該当するような行為については、まず当事者同士で協議を行うのが適当であるという理由によるものです(調停前置主義といいます)。
また、離婚は相手と合意さえすれば離婚届を提出してすることができるので、まずは相手との間で離婚協議を行い、相手と協議が整わなかった場合に調停や裁判に進むとよいでしょう。
悪意の遺棄をするような相手の場合、相手も離婚をしたいと考えている場合もあるでしょうから、協議をスムーズに進めることのできる可能性もあります。
③慰謝料を請求する
悪意の遺棄は、民法上の不法行為(民法第709条)に該当するため、悪意の遺棄をされた場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の相場は、悪意の遺棄をするに至った理由や態様、子どもの有無や婚姻期間等の事情を総合的に考慮して決められますが、おおよそ50万円~300万円程度の慰謝料が認められることが多いです。
相手に対して離婚を請求する場合には、調停や裁判の中で併せて慰謝料を請求することができます。
また、離婚成立後に別途慰謝料の請求をすることも可能です。
ただし、慰謝料請求には以下のとおり時効・除斥期間がありますので、期間の経過後は権利が行使できなくなる(=慰謝料を請求できなくなる)点には注意が必要です(民法第724条、第724条の2)。
除斥期間については、悪意の遺棄があったことを被害者が知っているか否かに関わらず、不法行為(=悪意の遺棄)の時から進行し、期間が経過すると権利が消滅します。
通常、悪意の遺棄をされたことを知らないということは考えづらいため、5年又は3年で権利が消滅すると考えておいた方がよいでしょう。
悪意の遺棄の時効・除斥期間
(ⅰ)悪意の遺棄が生命・身体を害するといえる場合
損害及び加害者(相手による悪意の遺棄があったこと)を知った時から5年間
又は
悪意の遺棄があってから20年間
(ⅱ)(ⅰ)以外の場合
悪意の遺棄があったことを知った時から3年間
又は
悪意の遺棄があってから20年間
悪意の遺棄を主張する場合の証拠は?
相手が悪意の遺棄をしたことを調停や裁判で主張する、慰謝料を請求する場合には、証拠が重要となります。
例えば、以下のような証拠を用意することで、相手方が悪意の遺棄をしたことを裁判所にも認めてもらいやすくなるでしょう。
- 相手方の住民票(相手が住民票を移している場合)
- 相手方とのLINE、メール等のやりとり(帰ってくるよう求めている内容など)
- 相手方との会話の録音(家事や育児についての会話など)
- 預貯金の取引履歴(相手方が生活費を入れていないことが分かるもの)
- 生活費の領収書やクレジットカードの明細書(こちらが生活費を負担していることが分かるもの)
まとめ
相手方の行為が悪意の遺棄に該当するかどうかは、ご自身のみでは判断が難しい場合もあるでしょう。
また、相手が不貞行為をし、その結果悪意の遺棄をしている場合には、慰謝料の請求の際に効果的に主張をすることで、慰謝料の額を増額することができる可能性もあります。
当事務所では、これまでに数多くの離婚に関するご相談をお受けしており、その経験を活かした最適なアドバイスをさせていただくことが可能です。
配偶者が勝手に家を出て戻らないなど、配偶者の行為でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。