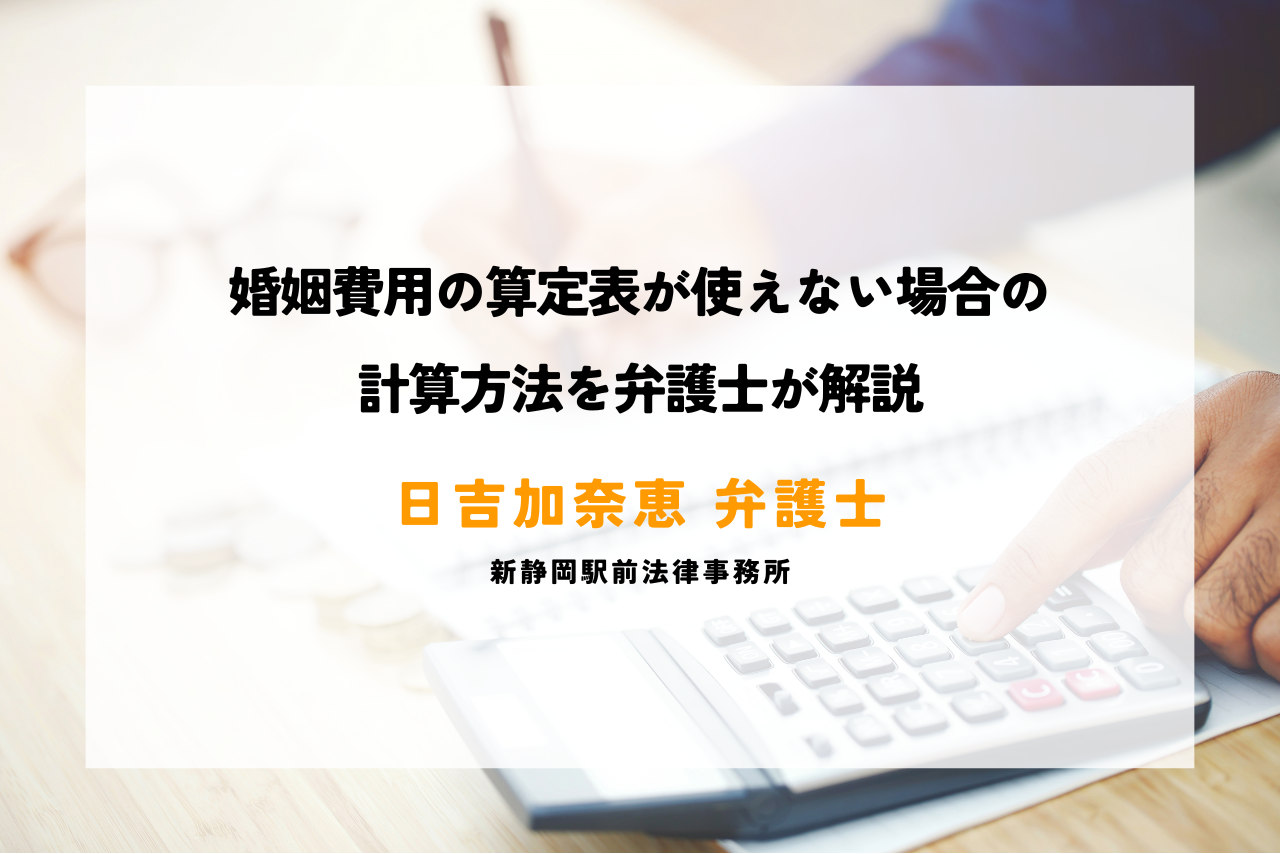別居をしている夫婦の一方は、相手に対して婚姻費用(生活費)を請求できる場合があります。
この婚姻費用は、裁判所が作成した「算定表」にて額を決めることが一般的です。
しかし、裁判所の算定表は、全てのケースに対応しているわけではないので、算定表では婚姻費用の額が分からないケースがあります。
そこで、本記事では、算定表が使えない場合の婚姻費用の計算方法について解説します。
目次
1. 婚姻費用の算定表とは
算定表は、家庭裁判所の裁判官などが、簡単に婚姻費用の額を算定するために作成したものです。
婚姻費用を請求する人(=「権利者」といいます)と婚姻費用を支払う人(=「義務者」といいます)の双方の年収を元に、婚姻費用の額が表で簡単に確認できるようになっているものです。
婚姻費用の算定表の見方は、以下のコラムで詳しく解説しています。
2. 算定表が使えないケース①子が多い場合
婚姻費用この算定表は、子どもが3人までのものしか用意されていません。
そこで、子どもが4人以上いる場合には、算定表を使って婚姻費用の額を確認することはできず、「標準算定方式」という計算式により婚姻費用の額を計算します。
実は、婚姻費用の算定表も、この計算式を元に作成されているものです。
算定表は、都度計算が不要なように表形式で婚姻費用の額が確認できるようになっているので、計算式を使うことにより、算定表の考え方を用いて婚姻費用の額が計算できます。
婚姻費用の計算は、以下のような順序で行います。
以下のような家族を例にとって説明します。
例:
夫の年収が800万円(会社員)、妻の年収が400万円(会社員)、妻が子ども4人(15歳の子ども1人、14歳の子ども1人、8歳の子ども1人、3歳の子ども1人)を養育している場合
ステップ1:夫婦の基礎収入を算定する
基礎収入とは、年収から公租公課や住居関係費などの必要経費を引いた額をいいます。
可処分所得とほぼ同じと考えていただくとイメージがつきやすいでしょう。
基礎収入は、以下の表に基づき決められた割合(基礎収入割合)を、1年間の収入(額面)に乗じることで算出できます。
表:給与所得者の基礎収入割合
| 収入(万円) | 割合 |
|---|---|
| 0~75 | 54 |
| ~100 | 50 |
| ~125 | 46 |
| ~175 | 44 |
| ~275 | 43 |
| ~525 | 42 |
| ~725 | 41 |
| ~1325 | 40 |
| ~1475 | 39 |
| ~2000 | 38 |
表:自営業者の基礎収入割合
| 収入(万円) | 割合 |
|---|---|
| 0~66 | 61 |
| ~82 | 60 |
| ~98 | 59 |
| ~256 | 58 |
| ~349 | 57 |
| ~392 | 56 |
| ~496 | 55 |
| ~563 | 54 |
| ~784 | 53 |
| ~942 | 52 |
| ~1046 | 51 |
| ~1179 | 50 |
| ~1482 | 49 |
| ~1567 | 48 |
夫と妻の基礎収入は、それぞれ以下のとおりです。
夫の基礎収入=800万円×0.4=320万円
妻の基礎収入=400万円×0.42=168万円
ステップ2:権利者世帯に配分される婚姻費用を計算
次に、権利者(婚姻費用をもらう側)に割り振られるべき生活費を算定します。
この計算は、「生活費指数」といって、大人1人を100とした場合に、家族のそれぞれに割り振られるべき生活費の割合用いて行います。
生活費指数は、以下のとおりです。
| 親(権利者・義務者とも) | 100 |
| 15歳以上の子 | 82 |
| 14歳以下の子 | 65 |
権利者世帯に割り振られる婚姻費用の計算は、以下の式を用いて算出します。
(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×
(権利者の生活費指数 + 権利者と同居する子供の生活費指数計)/(権利者の生活費指数 + 義務者の生活費指数 + 子供の生活費指数計)
上の例でいうと、以下のとおりです。
(320万円+168万円)×(100+85+62+62+62)/(100+100+85+62+62+62)
≒3843906
ステップ3:義務者が支払う婚姻費用の額を計算
最後に、義務者が払うべき婚姻費用の額を算出します。
以下の式を用いて算出します。
権利者世帯に分配される婚姻費用 – 権利者の基礎収入
上の例でいうと、以下のとおりです。
384万3906円-168万円=216万3906円
算出された額は年額となりますので、1か月分になおす(12で割る)と、18万325円となります。
実務上は、100円未満を切り捨てする、四捨五入するなどして、きりのいい数字とすることも多いです。
3. 算定表が使えないケース②権利者・義務者がそれぞれ子を監護している場合
夫婦の中には、夫と妻がそれぞれ子を監護しているという方もいらっしゃいます。
その場合も、算定表では計算できないため、「2」で述べた計算式で算出します。
以下のような家族を例にとって説明します。
例:
夫の年収が600万円(会社員)、妻の年収が200万円(会社員)、夫が子ども1人(15際の子)を、妻が子ども2人(8歳の子1人、3歳の子1人)を養育している場合
ステップ1:夫婦の基礎収入を算定する
基礎収入の算定方法は変わらないため、夫と妻の基礎収入は、それぞれ以下のとおりです。
夫の基礎収入=600万円×0.41=246万円
妻の基礎収入=200万円×0.43=86万円
ステップ2:権利者世帯に配分される婚姻費用を計算
権利者世帯に割り振られる婚姻費用の計算は、以下の式を用いて算出します。
夫が監護している子の生活費指数は、分子に含めず、分母のみに含めます。
(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×
(権利者の生活費指数 + 権利者と同居する子供の生活費指数計)/(権利者の生活費指数 + 義務者の生活費指数 + 子供の生活費指数計)
上の例でいうと、以下のとおりです。
(246万円+86万円)×(100+62+62)/(100+100+85+62+62)
≒1818288
ステップ3:義務者が支払う婚姻費用の額を計算
最後に、義務者が払うべき婚姻費用の額を算出します。
こちらも計算式は変わりません。
権利者世帯に分配される婚姻費用 – 権利者の基礎収入
上の例でいうと、以下のとおりです。
181万8288円-86万円=95万8288円
月額に直すと、7万9857円となります。
4. 算定表が使えないケース③収入が高い場合
子どもの数が多い場合以外にも、婚姻費用の算定表が使えないことがあります。
それが、義務者(又は権利者)の収入が多い場合です。
算定表は、給与所得者であれば年収2000万円を、自営業者であれば所得1567万円が上限となっており、これを超える場合には算定表を用いることができません。
このような場合の婚姻費用をどう算定するかについては、以下のとおりいろいろな考え方があります。
①算定表の上限額を頭打ちの額とする
算定表の収入を超える収入があっても、算定表の上限である2000万円(自営業者であれば1567万円)で計算するという考え方です。
年収が3000万円であっても、4000万円であっても、2000万円の箇所で婚姻費用を算定します。
実際に裁判例でも採用されている方法です(大阪高裁決定平成17年12月19日)。
②基礎収入の割合を修正する
上で述べた基礎収入割合を、上限(38%)よりも若干低く設定して、計算式により婚姻費用の額を算定する方法です。
算定表が改定される以前の裁判例ですが、当時の上限34%を修正し、32%として計算した裁判例があります(大阪高裁決定平成18年1月18日)。
③貯蓄率を控除する方法
高額所得者の場合、収入を貯蓄や資形成に回すことも多いことから、基礎収入を算定する際に、貯蓄率も控除して算定するという考え方もあります。
総務省統計の平均的な貯蓄率を、可処分所得に乗じて得た額を、その他の必要経費と併せて控除した裁判例がありました(大阪高裁決定平成20年6月9日)。
④裁量にて決定する方法
夫婦の同居中の生活レベルや、生活費の支出状況、現在の生活状況を鑑みて、裁判官が婚姻費用の額を決定する方法です。
総収入が5000万円ほどの医師について、夫婦が別居後に妻に支払っていた額(50万円)を基準に、その後子どもが出生したことや生活実態を踏まえて、婚姻費用の額を40万円とした裁判例がありました(大阪高裁決定平成20年5月13日)。
5. まとめ
本記事では、算定表を用いることができない場合の婚姻費用の額について解説しました。
婚姻費用の額は、算定表や計算式により比較的簡単に算出することができますが、本記事で述べたように一概には額を決められない場合もございます。
また、婚姻費用は相手に正式に請求した時から支払いがされるため、早めに請求をした方が良いケースも多いです。
当事務所では、離婚に関する数多くのご相談を受けており、婚姻費用やその後の離婚についてのご相談にもトータルでサポートすることが可能です。
問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。