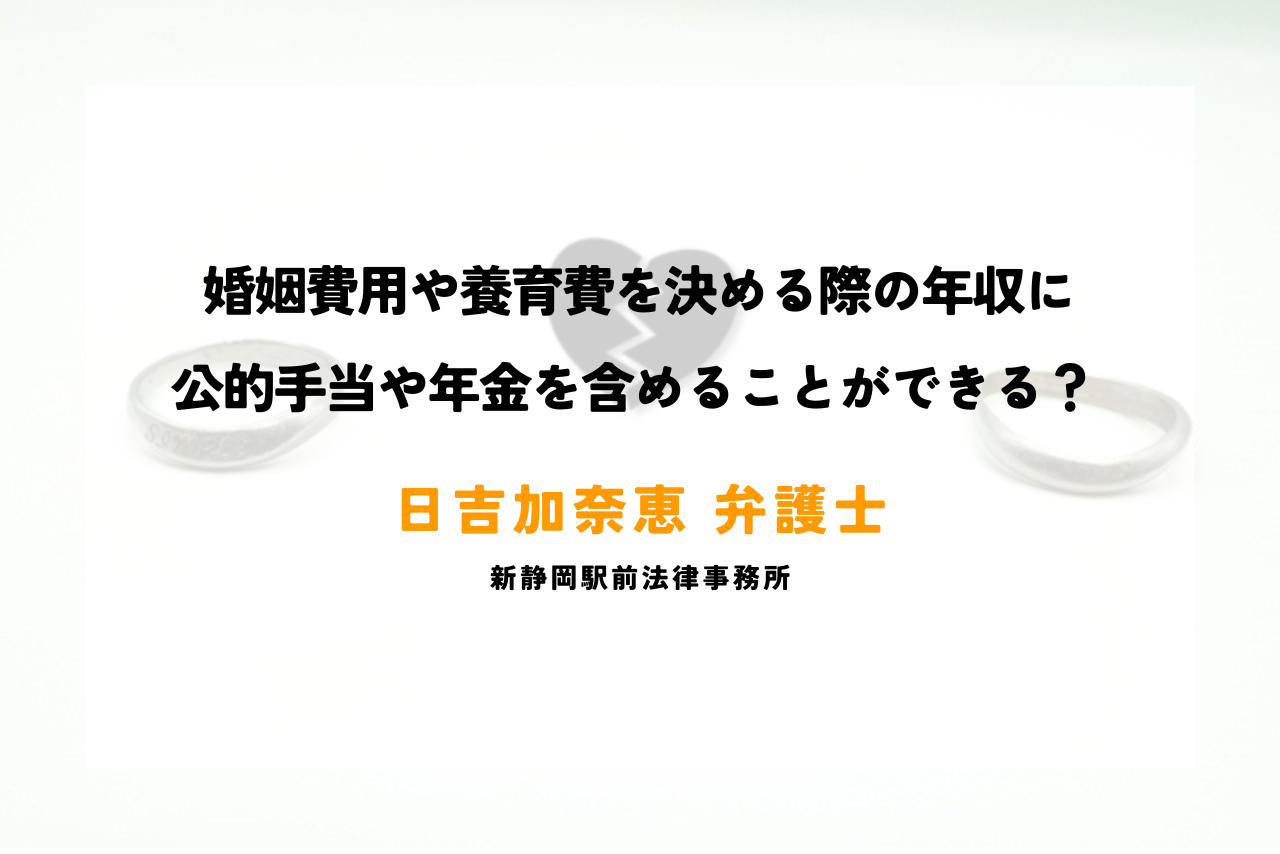婚姻費用や養育費の額を決める際には、お互いの年収を元に裁判所が作成した算定表を用いて行います。
この際、相手が年金や公的手当を受給していれば、その額を年収に含めて計算すべき場合があります。
そこで、本記事では、相手が年金や公的手当を受給している場合に、婚姻費用や養育費を決める元となる年収をどう考えればよいかについて解説します。
目次
1. 婚姻費用や養育費の算定表
婚姻費用や養育費の額を決める場合には、裁判所が作成した算定表を用いて決めることが一般的です。
算定表とは、両親の収入や子どもの数を元に、婚姻費用や養育費の額が一覧できる表のことをいいます。
お互いの年収を基準に、簡単に婚姻費用や養育費の額を決めることができますので、婚姻費用や養育費の請求をお考えの方は、一度算定表を確認してみるとよいでしょう。
詳しい算定表の見方は、以下の記事で解説しています。
婚姻費用の場合:
養育費の場合:
2. 年収の計算に考慮される収入、考慮されない収入
前述のとおり、婚姻費用や養育費の額はお互いの年収を基準に決めるため、まずはお互いの年収を確認することが必要です。
会社員で給与収入しか得ていない場合には、年収は源泉徴収票などで確認ができ、比較的簡易に額が決定できるでしょう。
他方、給与収入以外にも収入がある場合、婚姻費用や養育費の算定にあたってその額を考慮しないと、本来もらえる額よりも少ない額となってしまうことがあります。
相手に他に収入があるかについては、額を決める際にきちんと確認するようにしましょう。
以下、代表的な公的手当などについて、婚姻費用や養育費の算定にあたって考慮できるかを解説します。
児童手当などの公的手当
子どもがいる場合、婚姻費用や養育費を受領する側が、児童手当や児童扶養手当(ひとり親家庭へ支給される手当)を受給していることがあります。
この場合でも、手当の額を養育費から控除したり・受給している側の年収に含めて計算することはありません。
これは、こういった手当は、子育ての支援等を目的として支給されているものであり、手当があるからといって婚姻費用や養育費の額を減額すべきではないという理由によるものです。
失業保険
失業保険については、受給額を年収に含めて計算することになります。
失業保険は、受給者本人だけではなく、その家族の生活を維持することも目的として支給される手当であるからです。
年金収入
年金収入についても、失業保険と同様に、本人のみではなく家族の生活の意地も目的として支給されるものですから、年金収入も、婚姻費用や養育費の算定にあたり考慮すべき収入となります。
実家からの援助
例えば、婚姻費用や養育費を受領する側が、実家から生活費の援助を受けている場合であっても、それを年収に含めて計算することはしないのが原則です。
これは、婚姻費用や養育費の分担義務は、親族が負う扶養義務に優先するためです。
親は子に対し、第一次的な扶養義務を負うことから、それよりも下の順位の扶養義務しかない者からの援助を理由に、婚姻費用や養育費の支払義務を免れるとするのは妥当ではないと考えられています。
事実上も、このような援助はいつ打ち切られるか分からないものであり、婚姻費用や養育費の額の決定にあたり考慮するのは妥当ではないといえるでしょう。
特有財産の不動産収入
例えば、婚姻費用や養育費の支払い義務を負っている側ら、両親から相続した不動産を所有しており、そこから毎月賃料収入を得ていた場合、その収入を考慮することはできるでしょうか。
これについては、特有財産からの収入であっても、婚姻中の生活費の原資となっている場合には、婚姻費用分担額の算定にあたって基礎とすべき収入とみるべきであるとした裁判例があります(大阪高等裁判所平成30年7月12日決定)。
この裁判例を前提にすれば、賃料収入についても夫婦の生活費として使っていた場合には、収入として考慮できると考えられます。
なお、両親から相続した不動産は、夫婦の協力により得た不動産ではないことから、特有財産に該当し、財産分与(夫婦が共同生活により築いた財産を離婚時に分配すること)の際には考慮されませんので注意が必要です。
3. 失業保険や年金を収入に加算する場合の計算方法
前述のとおり、失業保険や年金は、婚姻費用や養育費の額にあたり考慮すべき収入です。
しかし、単純に受給している額をそのまま算定表に当てはめて計算するわけではありません。
給与収入は、仕事をして得る収入のため、収入を得るために必要な経費(交通費や、被服費、通信費、書籍費等をいい、これを「職業費」といいます)が発生することを考慮して、算定表が作成されています。
これと異なり、失業保険や年金は、実際に仕事をして得た収入ではないため、職業費も発生しません。
収入を得るために必要な経費が発生しないことから、生活費に割り当てられる額も増えることになりますので、これを考慮して婚姻費用や養育費の額を決める必要があります。
裁判実務上は、簡易的に算定するため、受給している額を0.8で割った金額を収入とすることが一般的です。
なお、実際には、職業費をして考慮されている数値は、年収に応じて、0.83~0.86の間とされています。
より正確に計算する場合には、収入に応じた職業費の割合を用いることもあります。
具体例:義務者の年金収入が100万円の場合
100万円÷0.8=125万円となるので、収入は125万円であるとして、算定表に当てはめることになります。
4. まとめ
婚姻費用や養育費の額を決める場合には、算定表を見ることによりご自身でもおおよその額を確認することは可能です。
しかし、本記事で述べてきたように、相手に他の収入があるなど、算定表のみでは判断できない場合もあります。
婚姻費用や養育費は、離婚協議中や離婚後のご自身、お子さんの生活を維持するためのひとつの基盤となるものですから、額の決定にあたっては慎重な判断が必要です。
当事務所では、離婚問題に注力しており、婚姻費用や養育費に関する数多くのご相談をお受けしてきました。
婚姻費用や養育費の請求を考えている方は、相手と合意してしまう前に、適正な額であるか確認してみるとよいでしょう。
一度、お気軽に問い合わせフォームお問い合わせください。