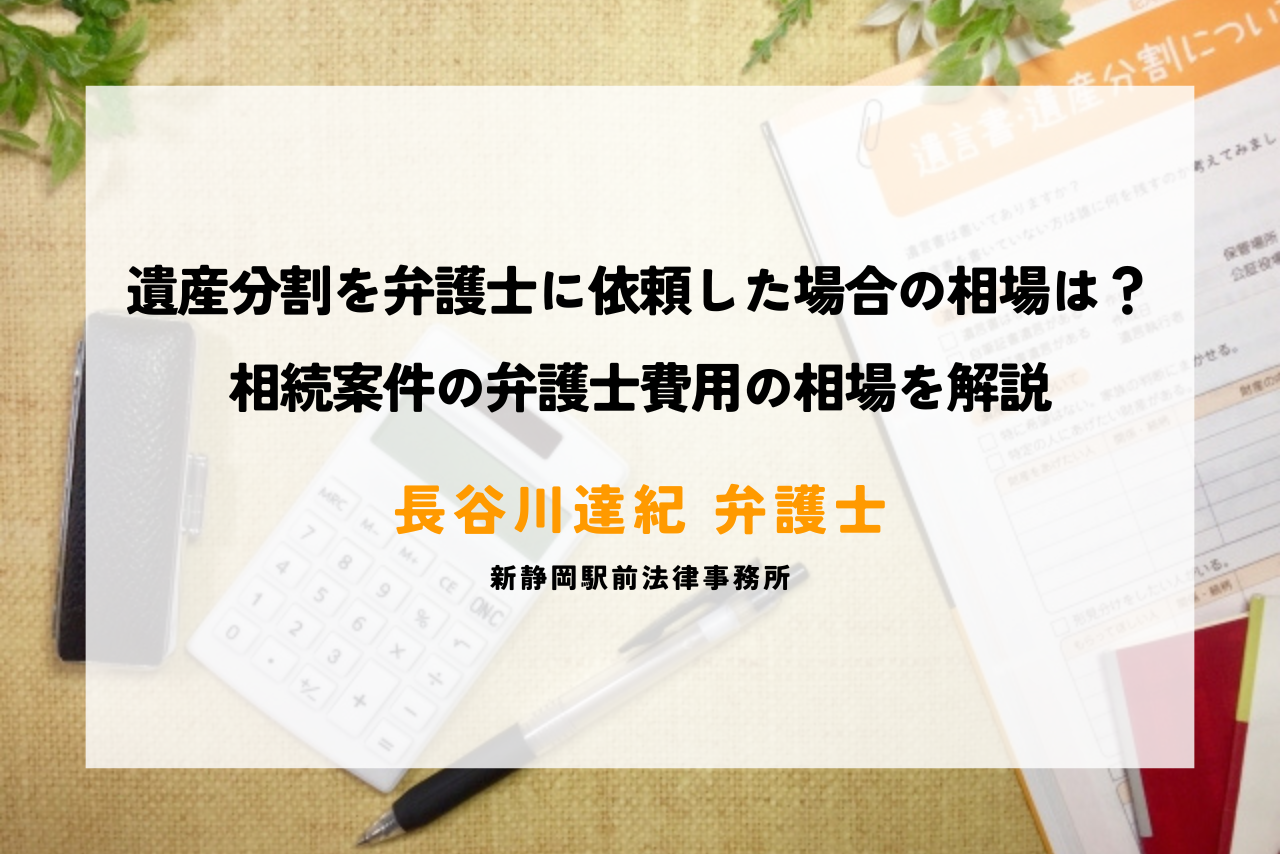遺産分割を弁護士に依頼した場合の相場は?相続案件の弁護士費用の相場を解説
遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺言書の作成、相続放棄などの相続案件を弁護士に依頼したいと考えている場合、弁護士費用はどれくらいかかるのだろうと心配な方もいらっしゃると思います。
以前は弁護士報酬基準により弁護士費用が定められていましたが、現在は同基準が廃止され、弁護士費用は自由に設定できることになっているため、弁護士費用は法律事務所や弁護士によって様々です。
本稿では、相続案件の弁護士費用の相場を種類ごとに解説いたします。
目次
1. 遺産分割
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を分けることです。
法定相続人が1人の場合は分割について協議する必要はありませんが、複数の法定相続人がいる場合には、遺産をどのように分けるか協議する必要があります。
遺産分割協議については、以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討しましょう。
調停とは、裁判所を通した話合いの手続です。
調停でも話合いがまとまらない場合には、審判という裁判所が遺産分割の方法を決定する手続に移行します。
遺産分割調停については、以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
遺産分割協議の弁護士費用は、着手金と報酬に分かれている法律事務所が多いです。
着手金
「着手金」とは、弁護士が法律事務や裁判手続の代行業務に着手する際に生じる費用のことをいいます。
遺産分割協議の着手金は、20万〜30万円程度であることが多いです。
遺産分割協議がまとまらず、調停に移行する場合に追加の着手金が必要となる場合もあります(追加着手金の相場は10万円程度)。
また、法定相続人が多数に渡る場合には(例えば5人以上の場合など)、業務量が増えることから、着手金が通常よりも高額になる可能性があります。
報酬金
「報酬金」とは、ある一定の条件を満たしたり、成果を達成した場合に生じる費用のことです。
遺産分割の場合、依頼者が得た経済的利益の◯%と定めることが多いです。
何パーセントとするかは、遺産の金額や種類(現金or株式or不動産)によって異なりますが、概ね3〜16%とする事務所が多いです。
事務所や案件によっては、遺産分割が完了した時に◯万円と定めることもあります。
相場としては、30〜40万円程度となります。
日当
「日当」とは、弁護士が調停又は審判期日に出頭するなど事件処理のために事務所外で活動をした際に生じる費用です。
近年では、裁判期日がウェブ会議や電話会議で実施されることが増えているところ、ウェブ会議や電話会議の場合には日当が生じないとしている事務所も一定数あります。
会議費・書面代
日当の相場は3万〜5万円ですが、遠方の裁判所に出頭する場合には、移動時間によりこれ以上の金額が生じることもあります。
少ないですが、事務所によっては、打合せ1回につき◯万円、書面1枚につき◯円というように会議費や書面代を設定している場合があります。
これらの費用が設定されている場合、想定していた金額よりも弁護士費用が高額となることがありますので、きちんと確認するようにしましょう。
実費
弁護士費用と異なりますが、裁判所に納める収入印紙・郵券代、内容証明郵便などの郵送代、戸籍謄本・住民票を取得するために地方自治体へ支払う手数料、交通費など、事件処理のために生じた費用は、「実費」として請求されることがあります。
多くの事務所が実費は依頼者負担となっていますが、事務所によっては、実費は着手金に含むとしていたり、みなし実費として一定額を支払うことで実費を免除していることもあるので、依頼する際には実費の処理についてきちんと確認するようにしましょう。
2. 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属が有する権利で(民法第1042条1項)、民法で定められている遺留分を侵害されている場合に、遺留分を侵害した者に対して行うことができる請求です。
詳細は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
遺留分侵害額の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることを検討しましょう。
調停でも協議がまとまらない場合には、地方裁判所への訴訟提起を検討することになります。
着手金
遺留分侵害額請求の着手金は、20万〜30万円であることが多いです。
調停に移行する場合や訴訟に移行する場合には、追加の着手金が生じることもあるでしょう。
報酬金
多くの事務所では、依頼者が得た経済的利益の◯%と定めています。
遺留分侵害額を請求する側の場合は実際に回収できた金額を基準に、遺留分侵害額を請求されている側の場合は相手方の請求額から減額できた金額を基準にすることが多いです。
ただし、遺留分侵害額を請求されている側の場合は、受任時点で相手方の請求額が不明な場合も多く、そのような場合は、遺留分侵害額請求事件が解決した時に◯万円と定めることが多いです。
相場としては、30〜50万円程度となります。
日当等
日当、会議費、書面代及び実費については、前述した遺産分割と同様です。
3. 遺言書の作成
遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の費用は、10万〜50万円程度が相場になります。
遺言書の内容や遺産の数と種類、法定相続人の数などにより、金額が異なります。
また、公正証書遺言を作成する場合で、かつ、依頼した弁護士に証人になってもらう場合には、追加の費用が生じることがあります。
遺言書については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
4. 相続放棄
相続放棄の手続を弁護士に依頼した場合の費用は、5万〜15万円程度です。
民法上、相続放棄ができる期間は、相続開始を知った時から3か月以内と定められていますが(民法第915条1項本文)、遺産の調査に時間を要する場合など、正当な理由がある場合には上記期間の伸長を求めることができます(同項ただし書き)。
期間の伸長が必要な場合や遺産の調査が必要な場合には、弁護士費用が高額になる傾向にあります。
なお、相続放棄手続の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
5. 遺産調査
遺産の調査を弁護士に依頼した場合、10万〜30万円程度の費用が生じます。
弁護士費用は、遺産の数や種類によって異なります。
なお、遺産の調査を弁護士に依頼する場合、委任状や関係機関との調整が必要となるなど、法定相続人が直接手続を行うよりも、負担が大きく、時間もかかることが多いため、まずはご自身で調査を行ってみる方が良いでしょう。
また、遺産の調査については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
6. 不動産登記と相続税申告
不動産登記
遺産に不動産が含まれており、かつ、相続を理由とする所有権移転登記手続が必要な場合は、弁護士ではなく、司法書士に依頼すると良いでしょう。
相続登記を司法書士に依頼する場合の費用は、5万〜20万円程度です。
なお、当事務所は、相続登記を多く取り扱っている司法書士と提携しておりますので、相続案件をご依頼いただいた場合、ワンストップで対応が可能です。
相続税
相続が生じた場合、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告は、基本的には弁護士ではなく税理士に依頼すると良いでしょう。
税理士に相続税の申告を依頼した場合の費用は、遺産の0.5〜1.5%が相場となります。
遺産分割や遺留分侵害額の協議がまとまっていない段階であっても、暫定的な相続税の申告は必須になりますので、相続が生じた場合には、速やかに税理士に相談しましょう。
なお、当事務所は、相続税の申告を多く取り扱っている税理士と提携しておりますので、相続案件をご依頼いただいた場合、ワンストップで対応が可能です。
7. 弁護士に依頼する場合の注意点
相場より高額でないかを確認する
相続案件の弁護士費用の相場は上記のとおりですが、事務所によって弁護士費用が大きく異なることが多いので、相見積もりを取ってみると良いでしょう。
委任契約書の内容を確認する
弁護士に依頼する場合、通常は委任契約書を締結します。
「委任契約書」とは、弁護士への依頼内容や弁護士費用などを定める書面です。
委任契約書の中に、説明がなかった費用が記載されていることもあるので、委任契約書の内容をきちんと確認し、疑問点や不明点がある場合には必ず弁護士に確認の上、委任契約書を締結するようにしましょう。
私の経験上、特に日当・会議費・書面代などをきちんと確認しておらず、想定外の費用が生じてしまったという話をよく耳にします。
そのような事態が生じないように、委任契約書の内容はきちんと確認するようにすべきです。
8. まとめ
これまで相続案件の弁護士費用の相場について解説してきましたが、事務所によって弁護士費用は様々です。
相続案件に関しては、司法書士や税理士などのワンストップの対応ができるかという点も重要となります。
また、上記で述べたとおり、事務所によっては、日当・実費・会議費・書面代などを設定していることがあり、想定外の弁護士費用を支払うことになるケースもあります。
当事務所は、ホームページにおいて弁護士費用を明示しており、ご相談の際には弁護士費用を分かりやすくかつ丁寧に説明するよう心がけております。
当事務所への相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。