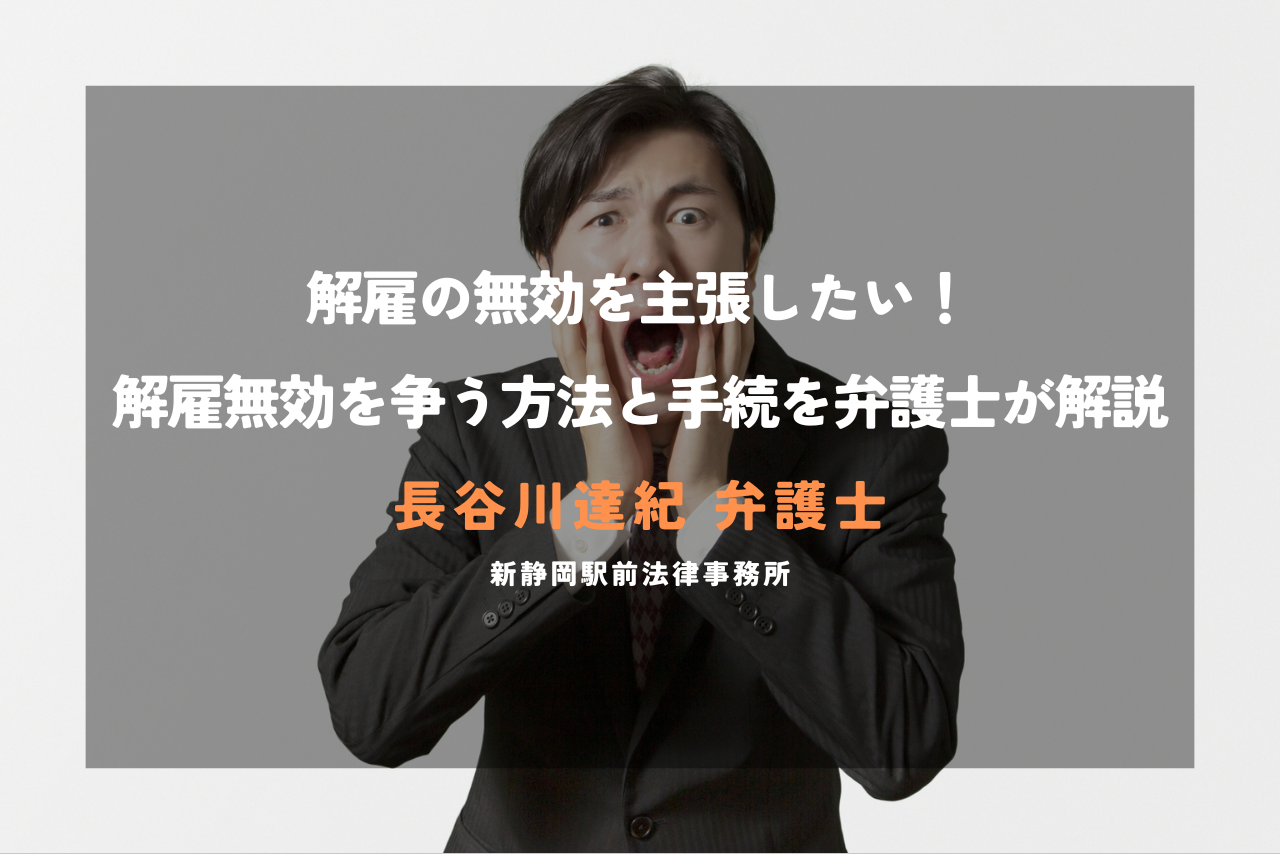会社から解雇を通知されたが、解雇に納得がいかない場合、解雇の無効を主張することが考えられます。
解雇が無効であると認められると、解雇後の賃金が支払われたり、解雇の経歴が残らないなどのメリットがあります。
本稿では、解雇の無効を争う方法と手続を弁護士が解説いたします。
目次
1. 解雇とは
解雇とは、使用者(会社)が労働者との雇用契約を一方的に終了させる通知のことを指します。
解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。
上記3種類の解雇には、労働契約法又は判例法により、それぞれ解雇が有効となるための要件が定められており、要件を満たさない解雇は無効となります。
解雇の詳細や解雇が無効となる条件は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 解雇無効を争う方法
①解雇の理由を確認する
会社から解雇を通知された場合、まずは解雇の理由を確認しましょう。
解雇の理由を確認しないと、解雇の無効を争うか否かの判断ができず、また、反論や証拠収集の準備もできないためです。
労働基準法第22条2項は、労働者からの請求があった場合、会社は遅滞なく解雇理由証明書を交付する必要があると定めていますので、会社に対し、解雇理由証明書の交付を求めましょう。
②会社と協議する
解雇理由を確認し、解雇の無効を争うこととした場合、会社と協議をすると良いでしょう。
解雇処分に対する反論や反証(解雇が無効であることを示す証拠を提示)するなどをして、会社が解雇処分を撤回することに同意すれば、解雇はなかったことになります。
もっとも、経験上、解雇を通知した会社が裁判外で解雇の撤回や無効確認に応じるケースは少なく、会社が応じない場合には、後述する労働審判の申立てを検討しましょう。
③労働審判を申し立てる
裁判外での協議がまとまらなかった場合には、労働審判の申立てを検討しましょう。
「労働審判」とは、解雇無効確認請求等の会社と労働者との個別労働紛争に関し、裁判所が紛争の解決を仲介してくれる手続です。
労働審判手続では、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名(使用者側の専門家と労働者側の専門家それぞれ1名ずつが選任)により構成される労働審判委員会が期日の進行、調停案の提示、審判を下すなどの手続を行います(労働審判法第9条)。
原則として3回の期日で審理を終結することとされていること(労働審判法第15条2項)、「調停」という裁判所を通じた話合いの手続が組み込まれていることなどが労働審判の特徴で、通常の訴訟手続よりも迅速かつ柔軟な解決を図ることができる手続といえます。
裁判外での協議がまとまらない場合、労働審判手続を経ずに訴訟手続を選択することもできますが、上記のとおり、労働審判の方が迅速かつ柔軟な解決が図れる手続ですので、まずは労働審判を申し立てることをお勧めします。
労働審判手続の詳細は、裁判所のホームページをご参照ください。
解雇の無効確認を求める場合、「解雇無効確認請求」という請求内容とすることもありますが、実務上は解雇が無効であるため労働契約上の地位が存在することを求める「地位確認請求」という形にすることが多いです。
また、解雇後は賃金(給料)が支払われないことになるので(解雇予告手当を除く)、解雇が無効であることを前提に未払賃金請求も併せて行うと良いでしょう。
④訴訟を提起する
労働審判でも協議がまとまらず、労働審判委員会が審判を下すこととなり、当事者のいずれかが審判に対し異議を申し立てた場合は、訴訟に移行します。
なお、この場合、労働審判を申し立てた時点で訴訟提起があったものとみなされます(労働審判法第22条1項)。
また、労働審判法第24条1項は、「労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる」と定めています(一般的に「24条終了」と呼ばれています)。24条終了の場合も、労働審判を申し立てた時点で訴訟提起があったものとみなされます(労働審判法第23条2項、同第24条2項)
訴訟に移行した場合、互いに主張と反論、立証と反証を行い、最終的に裁判所が判決を下すことになります(ただし、訴訟手続の中で和解協議の機会が設けられ、裁判上の和解が成立することもあります)。
3. 裁判手続の流れ
労働審判
申立て
労働審判は、相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地(会社が法人ではなく自営の場合等)、若しくは、労働者が現に就業又は最後に就業した事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます(ただし、当事者が管轄合意した地方裁判所がある場合はその裁判所に申し立てます)。
通常の民事訴訟と異なり、労働審判手続の申立先の裁判所は、本庁と一部の支部(東京地裁立川支部、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部、広島地裁福山支部、福岡地裁小倉支部)に限られていますので、注意が必要です。
必要書類
労働審判の申立てには、以下の書類を提出することが必要です。
申立書や必要書類に不備があった場合には、裁判所から補正・追完の指示がありますので、指示に従いましょう。
- 労働審判申立書正本1通、副本(写し)3通+相手方の数
- (当事者の一方又は双方が法人の場合)資格証明書(代表者事項証明書、全部事項証明書等、証明日から3か月以内のもの)
- 証拠の写し各1通+相手方の数
- 証拠説明書正本1通、副本(写し)1通+相手方の数
- 申立手数料(収入印紙)※金額は管轄の裁判所にお問い合わせください
- 郵券(郵便切手)※金額と内訳は管轄の裁判所にお問い合わせください
期日指定
申立てが完了すると、裁判所から第1回期日の日程調整の連絡があり、調整が完了すると、第1回期日が指定されます。
相手方には、裁判所から期日呼出状と申立書や証拠等の写しが送付されます。
第1回期日は、原則として、申立てがなされた日から40日以内に指定されます。
答弁書等の提出
相手方は、労働審判間が定めた期限までに、答弁書等(申立ての内容に対する反論書面)を提出することになります。
審判期日
第1回審判期日には、当事者双方が出頭し、争点整理を行った上で、労働審判官と労働審判員が当事者双方から直接事情を聴取することが多いです。
また、第1回審判期日で労働審判委員会が一定の心証(結論・見通し)を持ち、これを当事者双方に示すことが多いです。
その上で、労働審判委員会から当事者双方に調停案が示されることもあります。
第1回期日で調停が成立(合意が成立)することもありますが、多くのケースでは、第1回期日は心証の開示又は調停案の提示までで終了となり、第2回期日までに労働審判委員の心証や調停案に同意するか否かを検討するという進行になります。
また、裁判所から追加の主張や証拠の提出を求められることもあり、その場合には、第2回期日までに行います。
第2回期日以降は、労働審判委員会の心証や調停案をもとに、話合いによる解決の見込みがあるか、協議を行う進行になることが多いです。
追加の主張・立証を行いたい場合には、第2回期日以降も行うことができます。
調停成立又は審判
当事者が合意できた場合には、調停が成立し、手続は終了となります。
合意ができなかった場合には、労働審判委員会が審判を下します(結論を出します)。
審判から2週間以内に異議申立てがなければ、労働審判が確定し、解決ということになります。
訴訟
異議申立て
労働審判委員会の審判に不服がある場合には、審判がなされてから2週間以内に異議申立てを行うことが必要です。
当事者のいずれかが異議の申立てをすると、審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。
訴状に代わる準備書面
通常、訴訟提起をする際は裁判所に訴状を提出する必要がありますが、労働審判に対し異議が申し立てられると、労働審判申立時に訴訟提起がなされたと擬制され、労働審判申立書が訴状とみなされることから、労働審判が訴訟に移行する際は「訴状に代わる準備書面」という形で、労働審判申立て後の事実について、追加の主張・立証を行います。
その後は、通常の訴訟手続と同様に、互いに主張・立証を繰り返し、裁判上の和解が成立しない場合には、裁判所が判決を下すことになります。
4. 解雇無効を弁護士に依頼するメリット
複雑な裁判手続と裁判所とのやりとりを一任できる
前述のとおり、会社が裁判外で解雇無効を認めるケースは少なく、労働審判等の裁判手続が必要となる可能性が高いです。
裁判手続は複雑で、特に労働審判の申立書を作成するに当たっては、法的知識や経験が必要となります。
知識や経験が不足していると、有効な主張や証拠の提出ができずに不利な判断がなされてしまうリスクもあります。
弁護士は法的な知識と経験を有していますので、弁護士に依頼することで裁判手続を一任でき、有効な主張や証拠提出を行ってもらえます。
また、裁判手続では、裁判所や相手方又は相手方代理人弁護士とのやりとりが必要になりますが、弁護士に依頼することで裁判所等とのやりとりも一任することができます。
裁判手続に同席してもらえる
労働審判や訴訟手続では、裁判所に出頭することが必要となりますが、一人で裁判所に出頭するのが不安という方は多いです。
弁護士に依頼すると、弁護士が裁判手続(期日)に同席してくれて、アドバイスをもらえたり、代わりに発言をしてもらえるというメリットがあります。
また、訴訟の場合、当事者が出頭する必要性が低いため、弁護士に依頼している場合には、弁護士が代理することがほとんどです。
一方で、弁護士に依頼していないと、ご自身で出頭していただく必要があるので、弁護士に依頼することで裁判所への出頭の負担も軽減することができます。
5. まとめ
解雇無効を求める案件では、裁判手続になることが多いため、ご自身での対応が難しい場合があります。
当事務所には、解雇無効を含む労働事件を主に扱う事務所での勤務経験のある弁護士が在籍しておりますので、解雇に関する紛争でお困りの方は、ぜひ問い合わせフォームよりご連絡ください。