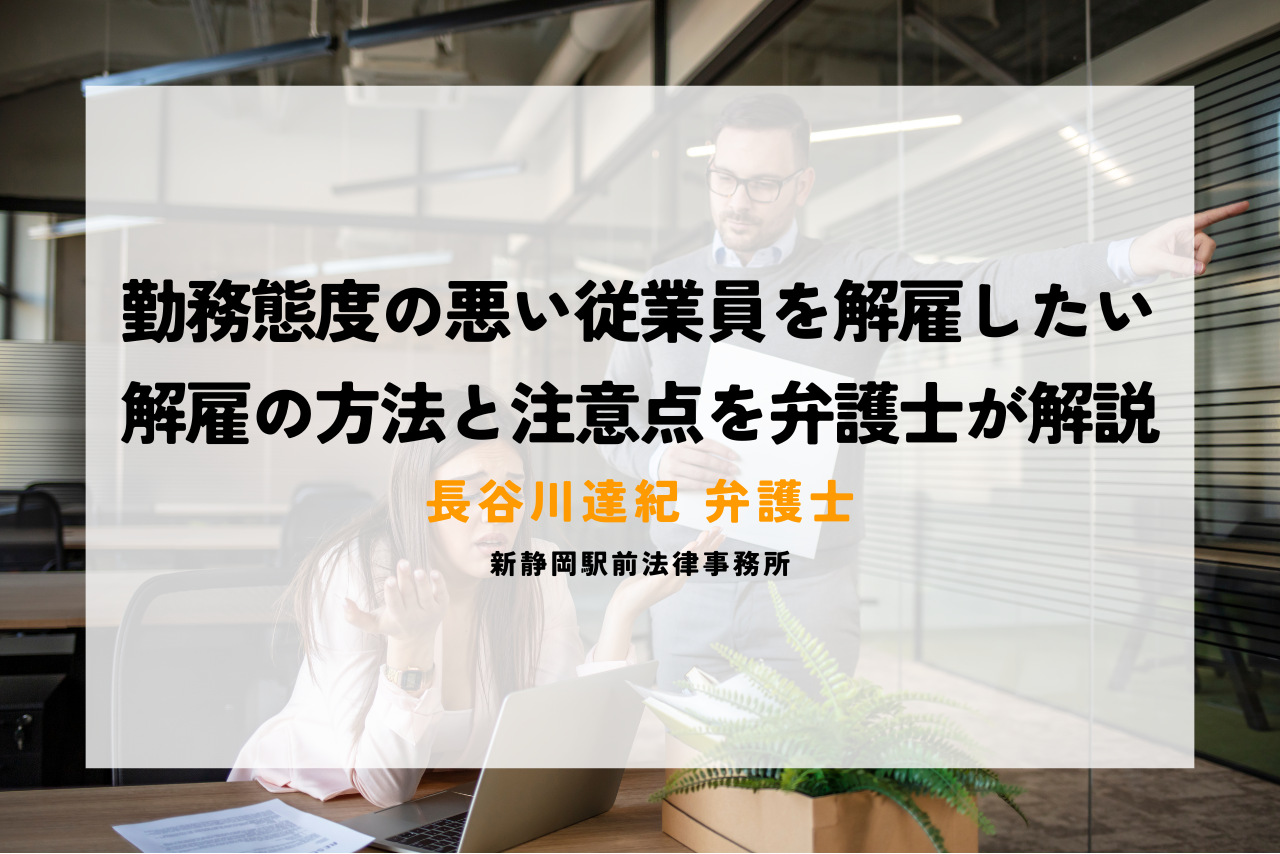勤務態度の悪い従業員がいると、職場環境を害したり、業務に支障を来すため、そのような従業員を解雇したいと考える企業や事業主の方は多いと思います。
本稿では、勤務態度の悪い従業員を解雇する方法と解雇する際の注意点を解説いたします。
目次
1. 解雇とは
「解雇」とは、使用者(会社や事業主)の一方的な通知により労働者との雇用契約を終了させることをいいます。
解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。
「普通解雇」とは、一般的に、労働者の能力不足や傷病による就労不能などの労働者側の債務不履行(業務に従事できない事由)が原因で解雇することをいいます。
「懲戒解雇」とは、労働者が会社の秩序を乱したり重大な非行を行った場合に、秩序違反や非行に対する制裁(懲戒処分)として労働者を解雇することをいいます。
「整理解雇」とは、会社の業績悪化など会社の経営上の理由により、労働者を解雇することをいいます。
勤務態度の悪い従業員を解雇する場合、能力不足を理由とする普通解雇か、懲戒解雇をすることが多いので、本稿では、能力不足を理由とする普通解雇と懲戒解雇を取り上げることとします。
2. 能力不足を理由とする普通解雇の要件
就業規則に能力不足を理由に解雇する旨が定められていること
能力不足を理由とする普通解雇をする場合、使用者が能力不足を理由に労働者を普通解雇できることを、就業規則、雇用契約書、労働条件通知書等に明記していることが必要です(労働基準法第15条1項は解雇事由の書面での明示を義務づけています。
以下「労働基準法」を「労基法」といいます)。
就業規則、雇用契約書、労働条件通知書等の書面において、普通解雇の事由が明記されていない場合、普通解雇は無効となります。
解雇権の濫用に該当しないこと
労働契約法第16条(以下「労働契約法」を「労契法」といいます)は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
「客観的に合理的な理由」とは、解雇をする理由に客観性かつ合理性が備わっていることをいいます。
例えば、「あの従業員の顔が嫌いだから」という理由は、客観性も合理性も欠いているため、「客観的に合理的な理由」が認められないことになります。
また、「社会通念上相当である」と認められるためには、当該従業員を解雇することが相当であると判断されることが必要です。
例えば、従業員に書類の作成を依頼したが、誤記が複数回あったことを理由に解雇した場合、解雇までする相当性はないとして、社会通念上相当であるとは認められない可能性が高いです。
一方で、書類の誤記が多数あり、何度も指摘したにもかかわらず、多数の誤記が繰り返されたような場合には、能力不足を理由とする解雇が社会通念上相当であると認められる可能性があります。
3. 懲戒解雇の要件
就業規則に懲戒の種別・事由を定めていること
使用者が労働者に懲戒処分を行うためには、就業規則に懲戒の種別及び事由を定める必要があると解されています(フジ興産事件・最二小判平成15年10月10日労判861号5頁)。
懲戒の種別として懲戒解雇や諭旨解雇が定められていない場合や就業規則に定めのない懲戒事由で懲戒解雇をした場合、懲戒解雇は無効になります。
懲戒権の濫用に該当しないこと
労契法第15条は、「使用者が労働者を懲戒できる場合において、その懲戒が労働者の行為及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、その解雇は無効とする」と定めています。
「客観的に合理的な理由」については、上記普通解雇で紹介した内容と同様です。
「社会通念上相当である」という要件について、懲戒処分の場合は、懲戒の理由となる行為の性質及び態様、結果の程度、情状及び前歴等、過去の処分例等と比較してその処分が重きに失しているかなどの要素が考慮されます。
また、懲戒処分は、労働者に対する制裁的な側面を有するので、懲戒処分を行う前に、労働者に弁解の機会を与える必要があります。
十分な弁解の機会を与えないまま、懲戒処分を下した場合、適正な手続を経ていないとして、社会通念上相当でないと判断される可能性があります。
4. 解雇の方法
①解雇事由を確認する
前述のとおり、解雇が有効となるためには、「客観的に合理的な理由」があることが必要です。
まずは、労働者を解雇する理由を明確にし、その理由に客観性と合理性があるかを確認しましょう。
また、労働者から解雇の有効性を争われた場合、解雇に客観的に合理的な理由があることを示すために、証拠が必要になります。
証拠がないと、客観的に合理的な理由がないと判断される可能性が高まりますので、証拠が整っているかも併せて確認することが必要です。
解雇の有効性の判断は、法的評価を伴い、過去の裁判例等も参考にしながら判断する必要がありますし、また、証拠の有効性(証拠価値)の判断も法的な判断が必要となりますので、解雇事由を確認するに当たっては、解雇の有効性について、弁護士に相談した方が良いでしょう。
②解雇の通知をする
解雇事由を確認したら、労働者に解雇する旨の通知を行いましょう。
原則として、解雇は、少なくとも30日前に労働者に予告しなければならないとされています(労基法第20条1項)。
仮に、解雇を予告した日と解雇日までの期間が30日に満たない場合には、労働者に対し、不足している日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
また、労働者から解雇通知書及び解雇理由書の交付を求められた場合には、これらを交付しなければなりません(労基法第22条1項、同条2項)。
労働者からの請求がなければ、解雇通知書及び解雇理由書の交付を行う義務がありませんが、後の紛争を予防するために、解雇を通知する際に解雇通知書及び解雇理由書の交付を行っておいた方が良いでしょう。
③協議・労働審判・訴訟
解雇を通知した後、労働者が解雇の有効性を争ってくることがあります。
このような場合には、まずは裁判外で協議を行い、協議がまとまらない場合には、労働審判や訴訟等の裁判手続に移行し、裁判所を通じた解決を図ることになります。
解雇の有効性を争われた場合、法的主張や立証(証拠による証明)に関し、専門的な知識や経験が必要となることから、弁護士に相談ないし依頼した方が良いでしょう。
5. 注意点
前述のとおり、解雇には労基法や労契法において、厳格な要件が定められています。
裁判実務上も、解雇の有効性に関しては、使用者にとって非常に厳しい判断がなされることが多いです。
労働者を解雇する場合には、弁護士に相談するなどして、慎重に行うようにしましょう。
弁護士に相談し、解雇が無効となる可能性があるという意見であった場合には、まずは当該労働者に厳重注意を行い、厳重注意をしたにもかかわらず改善が見られない場合には、改めて弁護士に相談の上、解雇の手続を行うという方法もあります。
また、退職勧奨や早期退職制度など、解雇よりも厳格でない手続により、円満に退職をしてもらう方法も考えられます。
退職勧奨等の場合、一定の和解金を支払ったり、退職金の増額を行う必要があることが多く、金銭的な負担は生じますが、労働審判や訴訟等の法的リスク、解雇が無効と判断された場合の未払賃金の支払義務のリスクなどを考慮すると、円満に退職してもらうことにより、これらのリスクを回避することができます。
解雇以外の方法についても、弁護士に相談することで、様々な選択肢を示してもらえますので、勤務態度の悪い従業員に辞めてもらいたいという場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
6. まとめ
解雇は、労働案件の中でも法的リスクの高い項目の1つです。
勤務態度の悪い従業員を早く辞めさせたいからといって、安易に当該従業員を解雇してしまうと、大きな法的リスクが生じかねません。
労働者の解雇を考えている場合、まずは弁護士に相談し、解雇の有効性に関する意見と今後の方針を聞いてみることをお勧めします。
当事務所には、使用者側の労働案件を主に取り扱う事務所に所属していた弁護士が在籍しており、労働案件の知識や経験は豊富です。
解雇を含む労働案件に関する相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。