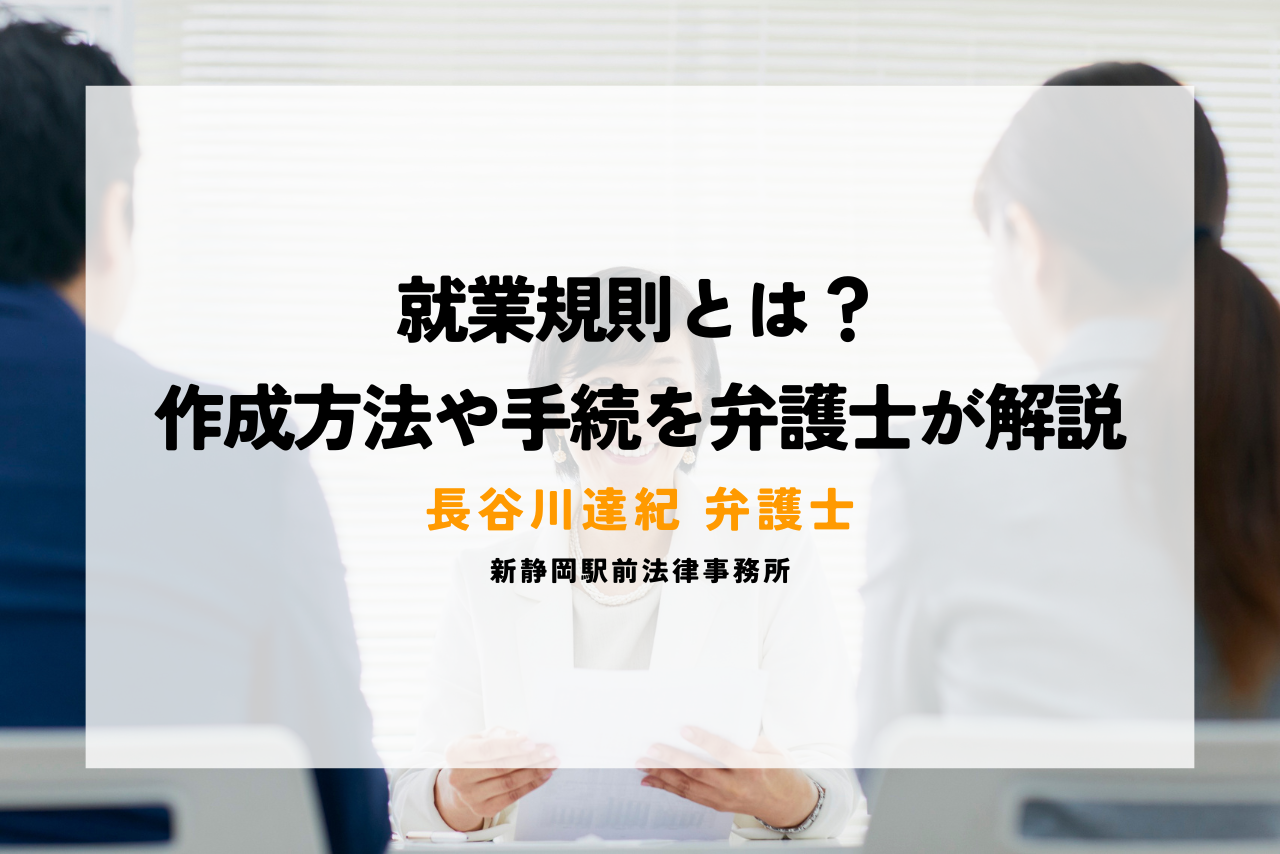常時10人以上の従業員を雇用する企業は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務を負います。
もっとも、従業員が10人未満の企業であっても、就業規則を作成することによるメリットは大きいので、企業を経営している場合は、就業規則を作成することをお勧めします。
本稿では、就業規則の作成方法と手続を解説いたします。
目次
1. 就業規則とは
「就業規則」とは、労働者の賃金や労働時間等の労働条件や職場内の規律を定めた規則集です。
常時10人以上の従業員を雇用する企業は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません(労働基準法第89条、同法第90条)。
就業規則を作成し、職場内で周知することにより、企業と労働者の労働条件を定める効果があります(労働基準法第106条参照)。
従業員が10人未満の企業であっても、就業規則を作成し、周知することで、労働条件を定めることができ、労務紛争の防止や労働条件の明確化に繋がるため、就業規則を作成することをお勧めします。
2. 就業規則の作成方法
絶対的必要記載事項
就業規則には、必ず記載しなければならない事項が定められています(絶対的必要記載事項、労働基準法第89条)。
就業規則の作成に当たっては、下記の事項を必ず記載するようにしましょう。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
企業(事業場)において、特定の労働条件を定めている場合に、必ず就業規則に記載しなければならない事項を相対的必要記載事項といいます。
以下の労働条件について、労働契約に定めがある場合、必ず就業規則に記載するようにしましょう。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
ひな形
就業規則の作成に当たっては、厚生労働省がモデル就業規則を公開しておりますので、同モデル就業規則を参考にすると良いでしょう。
ただし、労務リスクを避けるためには、企業の実情に合った就業規則を作成する必要がありますので、就業規則を作成する場合、弁護士や社会保険労務士に相談又は作成を依頼する方が良いでしょう。
3. 就業規則の効果
法令・労働協約違反の禁止
法令や労働協約に反する就業規則は無効となるので、注意が必要です(労働基準法第92条)。
就業規則で定める基準に達しない労働条件の無効
就業規則で定めた労働条件の基準に達しない労働契約を締結した場合、同労働契約の労働条件は無効となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)。
4. 手続
労働組合又は過半数代表者の同意
就業規則の作成又は変更に際しては、労働者の過半数が所属する労働組合又は労働者の過半数代表者の意見を聴くことが必要です(労働基準法第90条)。
なお、過半数労働組合又は過半数代表者の同意までは必要ありません。
意見を聴取したら、意見書を書面に残すようにしましょう。
労働基準監督署への届出
過半数労働組合又は過半数代表者からの意見聴取が完了したら、就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出ましょう。
労働基準監督署への届出に当たっては、過半数労働組合又は過半数代表者の意見書を添付する必要があります。
所轄の労働基準監督署は、厚生労働省のホームページで確認することができますので、ご参照ください。
労働基準監督署に届出を行った場合、労働基準監督署から補正等の助言があることがありますので、助言があった場合には従う方が良いでしょう。
労働者への周知
労働基準監督署への届出が完了したら、労働者に周知しましょう。
周知の方法は、以下のとおりです。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示する又は備え付ける
- 書面で労働者に交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
5. まとめ
就業規則を作成又は変更するに当たっては、企業の実情に合った内容にしたり、法令違反がないようにするなど、専門的な知識が必要となることがあります。
就業規則の作成又は変更を検討されている方は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談ないし作成を依頼することをお勧めします。
当事務所には、労働案件の使用者側の案件を主に取り扱う事務所に所属していた弁護士が在籍しており、労働案件の知識や経験は豊富です。
労務に関する法律相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。