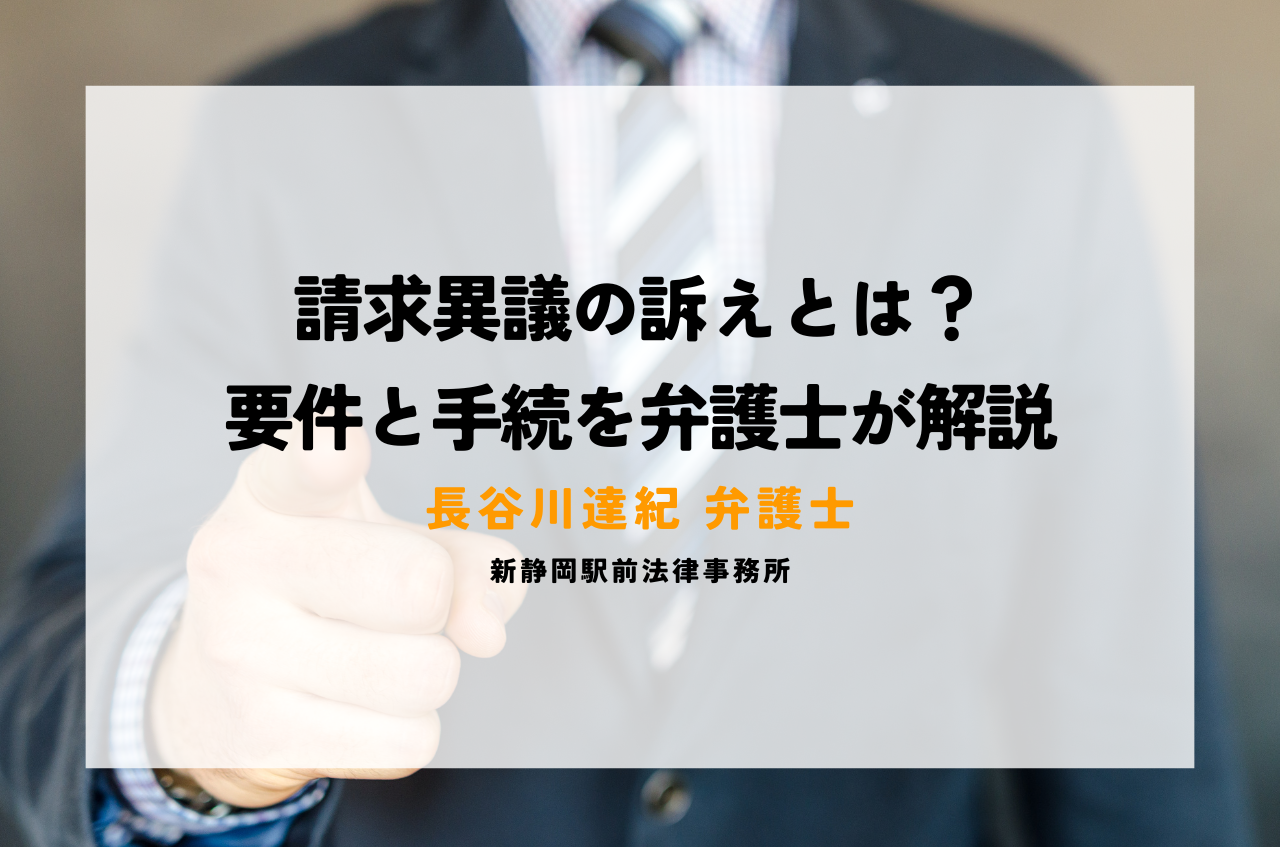不当な強制執行(差押え等)に対しては、裁判所に請求異議の訴えを提起することができます。
請求異議の訴えが認められると、裁判所が不当な強制執行を許さないことを命じます。
本稿では、請求異議の訴えが認められるための要件と手続の内容を解説いたします。
目次
1. 請求異議の訴えとは
民事執行法は、「債務名義に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる」と定めています(民事執行法第35条1項)。
「債務名義」とは、判決、和解調書、調停調書、公正証書などの強制執行を行うために必要な公的機関が作成した文書のことをいいます。
例えば、「被告は、原告に対し、100万円を支払え」という判決がなされたにもかかわらず、被告(債務者)が100万円の支払をしなかった場合、原告(債権者)は、裁判所に対し、被告名義の財産の強制執行を申し立てることができます。
なお、強制執行に関しては、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
一方で、「被告は、原告に対し、100万円を支払え」という判決に基づき、被告が原告に100万円を弁済した(支払った)にもかかわらず、原告が被告名義の財産に対する強制執行を申し立てた場合、強制執行を行う理由がなく、不当な強制執行となります(「不当執行」といいます)。
このような不当執行がなされた場合の債務者側の救済手段が「請求異議の訴え」です。
請求異議の訴えが認められれば、裁判所が債権者に対し、「強制執行を許さない」という判決を下し、債権者は強制執行を行うことができなくなります。
2. 請求異議の要件
請求異議の訴えが認められるためには、強制執行に対する異議事由があることです。
異議事由の具体例は以下のとおりです。
請求権の消滅
以下のように、債務名義に表示されている請求権が消滅した場合、異議事由が認められます。
- 債務を弁済した場合
- 請求権の根拠となる契約が解除されて請求権が消滅した場合
- 請求権が相殺により消滅した場合
- 債権者が債務を免除した場合
- 債権者が請求権を放棄した場合
- 消滅時効が完成した場合
請求権の不存在
以下のように、元々請求権が存在していなかったような場合にも、異議事由が認められます。
- 意思無能力、公序良俗違反、心裡留保、通謀虚偽表示などにより契約が無効であった場合
- 錯誤、詐欺、強迫などの契約の取消事由があった場合
債務者の変更
債権譲渡や免責的債務引受(債務者以外の者が債務を引き受け、元の債務者は債務を負わないこと)などにより、債務者が変更となった場合にも、異議事由が認められます。
3. 請求異議の手続
請求異議の訴えの提起
請求異議を行うためには、裁判所に対し、請求異議の訴えを提起する必要があります。
管轄の裁判所は、債務名義に執行力を付与した裁判所(執行裁判所)です。
請求異議の訴えは、債務名義が成立した後であれば、強制執行手続の開始前であっても提起することができます。
請求異議の訴えの提起に必要な書類は以下のとおりです。
- 訴状
- 証拠(異議事由があることを証明する資料、債務名義、差押命令など)
- 資格証明書(当事者の一方又は双方が法人の場合)
- 収入印紙(請求権の金額により決まります。詳細は裁判所のホームページをご参照ください)
- 郵券(裁判所により金額と内訳が異なりますので、事前に裁判所に確認するようにしましょう)
強制執行停止の申立て
請求異議の訴えを提起しても、原則として強制執行の手続は停止しません。
そこで、通常は、請求異議の訴えを提起すると共に、強制執行停止の申立てを行うことが多いです。
異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疏明(裁判所が事実の存在を一応確からしいという程度の推認を抱かせること)があったと認められた場合、請求異議の訴えの判決がなされるまでの間、強制執行を停止する又は取り消すという決定がなされます(民事執行法第36条1項)。
強制執行停止手続の流れについては、裁判所のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
審理・判決
請求異議の訴えの訴状が裁判所に受理されると、当事者が互いに主張・反論、立証・反証するなどの審理がなされ、裁判所が判決を下します。
4. 第三者異議の訴えとの違い
請求異議の訴えと類似する裁判として、第三者異議の訴えという手続があります。
例えば、AさんがBさんに対する債権(債務名義)を有していて、Bさんが支払を怠ったために、AさんがBさんに対する強制執行を行おうとして財産を差し押さえましたが、実はその財産がCさんのものであったとしましょう。
このような場合に、CさんがAさんに対して自らの財産への強制執行が不当であるとして、裁判所に強制執行を許さないよう求める訴えが「第三者異議の訴え」です(民事執行法第38条)。
請求異議の訴えとの違いは、請求異議の訴えが請求権の存否が争点となるのに対し、第三者異議の訴えは強制執行の対象となっている財産が債務者の所有物であるか否かが争点となる点です。
なお、第三者異議の訴えを提起しても、原則として強制執行手続は停止しませんので、請求異議の訴えと同様に、第三者異議の訴えの提起と併せて強制執行停止の申立てを行うのが一般的です。
5. まとめ
請求異議の訴えは、訴訟手続であるため、手続が非常に複雑であり、また、強制執行停止の申立てが必須であるケースがほとんどですので、迅速さも求められます。
そのため、請求異議の訴えを検討されている方は、まずは弁護士に相談の上、請求異議の訴えを提起する場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
当事務所は、請求異議の訴え及び請求異議の訴えに伴う強制執行停止の申立てにも対応しておりますので、相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。