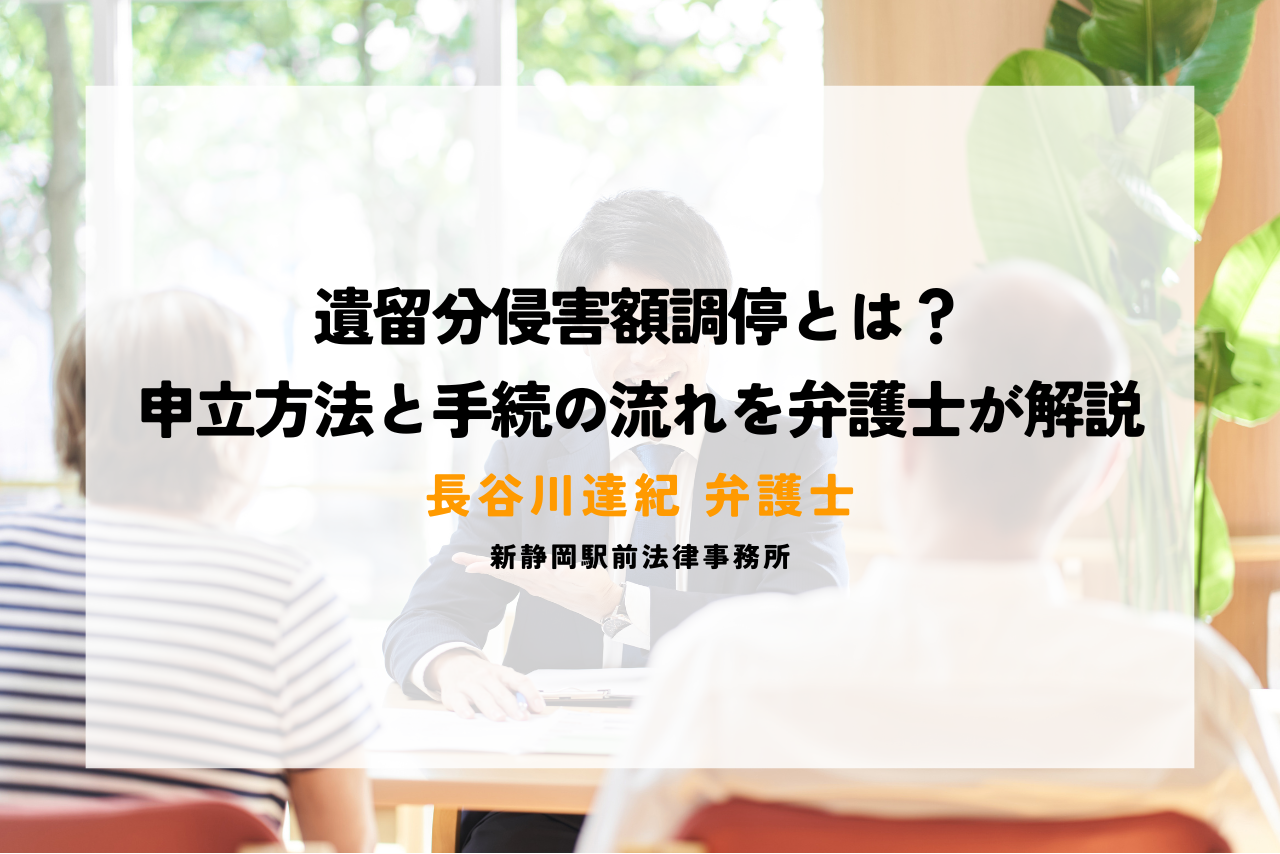遺留分侵害額請求について、当事者間の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
本稿では、遺留分侵害額調停の申立方法と手続の流れを解説いたします。
目次
1. 遺留分侵害額請求とは
「遺留分」とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産について、一定の相続人に法律上保証されている最低限の取得分のことをいいます。
遺留分が侵害されている場合に、遺留分を侵害している者に対し、自身の遺留分の不足分を請求するのが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分権利者(法律で遺留分が認められている相続人)の範囲、遺留分の割合、遺留分の算定方法については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 遺留分侵害額請求調停とは
「調停」とは、裁判所を通じた話合いの手続のことをいいます。
調停を申し立てると、裁判官又は調停官1名、調停委員2名による調停委員会が構成され、調停委員会が話合いの仲介をしてくれます。
調停委員は、現役の弁護士が務めることもありますし、法曹資格を持たない一般の方が務めることもあります。
遺留分侵害額請求調停を含む相続に関する調停の場合、法的知識が必要となることが多いため、弁護士が調停委員を務めることも多いです。
調停は、話合いの場ですので、調停委員会が一方的に結論を出して決定を下すということは基本的にはありません(「調停に代わる審判」という裁判所が相当であると考える結論を出すことがありますが、調停に代わる審判に対しては、当事者双方から異議の申立てが可能であるため、結局、調停委員会が結論を強制するということはありません)。
調停委員会が間に入ることで、当事者間では感情的になって話合いができなかったり、建設的な話合いができないケースであっても、話合いがまとまることがあるので、調停は紛争解決力の高い制度といえます。
一方で、調停には時間がかかるというデメリットがあります。
調停の時間は1回の期日につき約1時間30分〜2時間ですので、特に当事者の数が多い場合はなかなか話合いが進まないことがあります。
また、調停期日は1か月〜2か月に1回の頻度で行われるのが通常で、裁判所の休廷期間(年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休廷期間、年度末〜年度初めの人事異動期間)は、調停期日が実施されず、次回期日が2か月以上先に設定されることもあります。
調停を申し立てる場合、最低でも半年、長ければ1年以上かかることを念頭に置いておきましょう。
3. 遺留分侵害額請求調停の申立方法
申立先
遺留分侵害額請求調停の申立先(管轄裁判所)は、相手方(遺留分を侵害している者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相手方が複数いる場合、それぞれの住所地を管轄する家庭裁判所にそれぞれ申立てを行うことが原則です。
しかし、同じ相続に関する遺留分額侵害額請求であれば、同じ裁判所で同じ日時に調停を行った方が良いケースがほとんどです。
そのような場合、申立ての際に、1人の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に事情を説明する(上申する)ことで、当該家庭裁判所が併せて手続を行ってくれることがあります(「自庁処理」といいます)。
必要書類
遺留分侵害額請求調停の申立てに必要な書類は以下のとおりです。
以下の書類を管轄裁判所に提出することで、遺留分侵害額請求調停を申し立てることができます。
提出方法は、直接裁判所に持参しても良いですし、郵送でも受け付けてもらえます。
不備や不足があった場合、裁判所から補正や追完の指示がありますので、裁判所の指示に従いましょう。
- 申立書、遺産目録、当事者目録、相続人関係図、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書(ひな形は裁判所のホームページに掲載されています。)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票又は住民票
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票
- 遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- (遺産に不動産が含まれている場合)全部事項証明書、固定資産評価証明書
- (遺産に預貯金や有価証券が含まれている場合)残高証明書、取引履歴、通帳の写し等)
- 収入印紙1200円分
- 郵券(各裁判所により内訳が異なるので、事前に申立先の裁判所に確認する必要があります)
4. 遺留分侵害額請求調停の流れ
①申立て
前述した方法で、管轄裁判所に申立てを行います。
②第1回調停期日の指定
申立てが完了すると、裁判所から連絡があり、第1回目の調停期日を調整します。
期日の調整が完了すると、裁判所から相手方に対し、調停の申立てがあったこと及び第1回期日の日時が郵便で通知されます。
③第1調停期日への出頭
第1回期日に管轄裁判所に出頭します。
遠方の場合や高齢等の理由で出頭が難しい場合、ウェブ会議や電話会議による方法での出頭を認めてもらえる場合があるので、申立て時又は第1回期日の日程調整時に、裁判所にウェブ会議又は電話会議での実施を希望すること並びにその理由を具体的に上申するようにしましょう。
なお、第1回期日は、申立人と裁判所のみで日程調整を行うため、相手方の都合がつかず、第1回期日は相手方が欠席する又は第1回期日を取り消して、相手方の含めた日程調整を行うことも多いです。
第1回期日の最後に、第2回調停期日の日程調整を行います。
第2回期日以降は、期日の最後に次の期日の日程調整を行うことになりますので、スケジュール帳や手帳など、予定の分かる物を持参すると良いでしょう。
④第2回調停期日以降
第2回期日以降は、期日を重ねて話合いを継続していくことになります。
期日の終わりに、裁判所から書面や資料の追加提出の指示と提出期限の設定がなされることがあるので、メモができる物を持参すると良いでしょう。
なお、2回連続で、相手方が期日に出頭せず、書面も提出せず、かつ、裁判所からの連絡にも応じない又は出頭する意向がないという回答があった場合には、調停は不成立となり、終了することになります。
⑤調停の終了
話合いがまとまった場合、調停成立の手続が行われます。
調停委員会及び書記官立会いのもと、裁判官又は調停官が調停条項(合意した内容をまとめたもの)を読み上げて、当事者の最終確認が取れると調停成立となり、調停は終了します。
読み上げられた調停条項の内容は、後日、裁判所が調停調書という書類にまとめてくれます。
調停調書は強制執行が可能な効力(執行力)を有する重要な書類ですので、大切に保管するようにしましょう。
一方で、調停委員会が合意成立の見込みがないと判断した場合、調停を不成立とする手続を行います。
調停が不成立になると、調停は終了となります。
遺留分侵害額請求の場合、自動的に審判という手続に移行しないため、別途遺留分侵害額請求訴訟(裁判)を提起するかを検討することになります。
なお、遺留分侵害額請求訴訟の提起先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ではなく地方裁判所になるので、注意が必要です。
5. まとめ
遺留分侵害額請求調停を申し立てる場合、必要書類が多く、書面の作成や資料の収集に多くの時間を要することがほとんどです。
また、調停の進行に当たっては、裁判所や相手方から追加の書面や資料の提出を求められることが多く、ご自身で対応することが難しい場合があります。
遺留分侵害額請求調停の申立てを検討している方は、弁護士に依頼することを検討すると良いでしょう。
当事務所は、相続案件に注力しており、遺留分侵害額請求調停の経験と実績も豊富です。
遺留分侵害額請求調停を含む相続案件に関する相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。