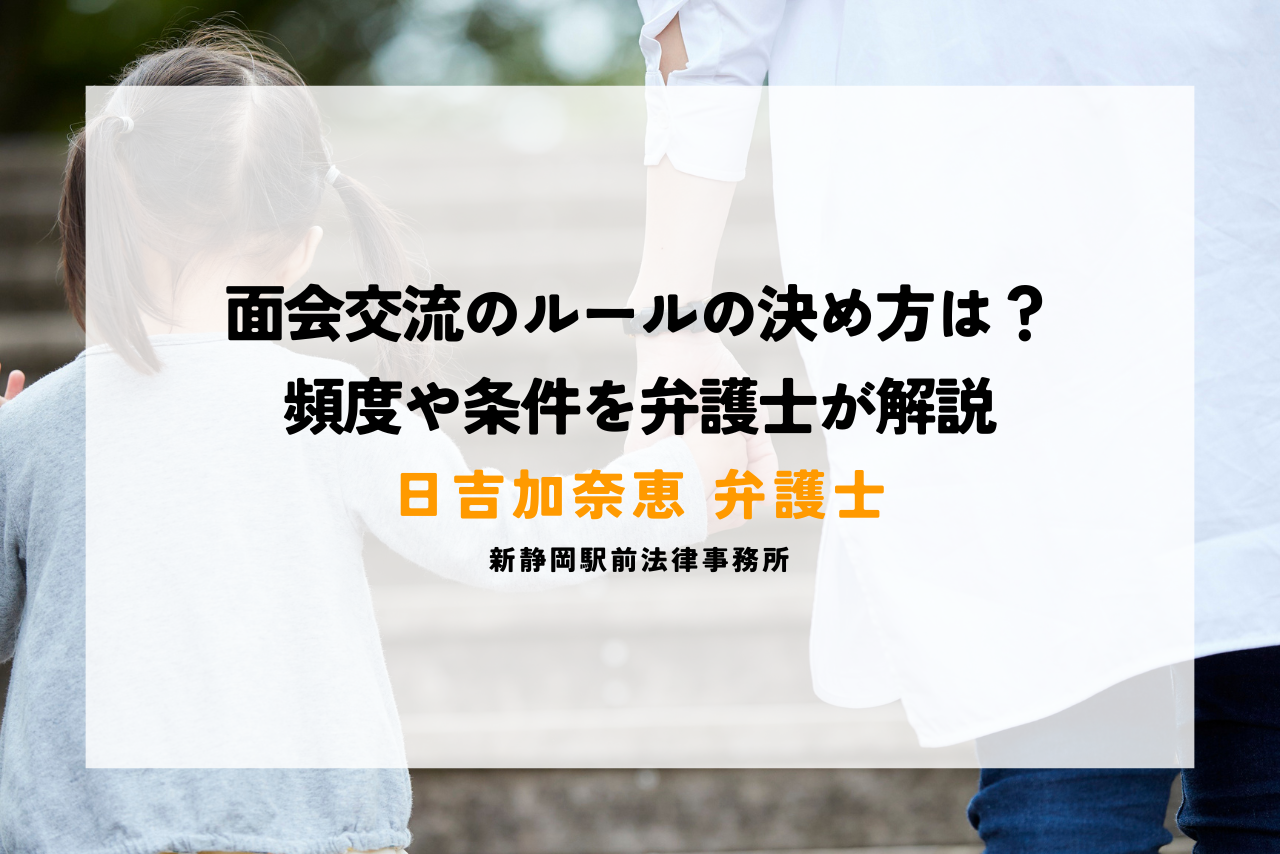「面会交流を実施するよう求められているが、どういったルールで実施してよいか分からない」
面会交流の実施にあたり、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、面会交流のルールの決め方やポイントについて解説します。
目次
1. 面会交流とは
面会交流とは、夫婦が離婚や別居をしたときに、子どもの親権者ではない親や監護をしていない親(「非監護親」といいます)が子どもと直接会ったり、電話やメールをしたりして交流することをいいます。
両親が離婚や別居をしたとしても、子どもにとっては双方が親であることに変わりなく、子どもの健全な成長のためには両親の継続的な関与が必要であると考えられており、裁判所も面会交流の実施には積極的です。
裁判実務では、「面会交流(直接交流)が相当でない場合に限り、面会交流を認めるべきである」という見解が主流です。
2. 基本的な面会交流のルール
上記のとおり、面会交流は子どものためにも重要な機会であると考えられています。
しかし、面会交流の実施には、別居や離婚した夫婦の双方の協力が必要であることから、ルールを決めずに実施してしまうと、無用なトラブルを招いてしまったり、スムーズに面会交流が実施できないなどといった事態になりかねません。
そこで、面会交流の実施にあたっては、以下のようなルールを決めておくとよいでしょう。
頻度
面会交流の頻度については、「月に1回」「週に1回」などと決めることが一般的です。
裁判実務上は、月1回と定めることが多いことから、当事者の協議で決める場合でも、その回数が目安になるでしょう。
なお、子どもの負担にならず、監護親も面会交流に積極的な場合には、より多い回数を決めることもあります。
日程
面会交流の日程を事前に決めることもあります。
例えば「第1土曜日」や、「毎週金曜日」などです。
面会交流の日程を固定化することで、都度日程調整をする手間が省ける反面、子どもの急な予定や体調の変化に対応しづらいといったデメリットもあるため、どこまで具体的に決めるかは、慎重に検討するとよいでしょう。
時間
面会交流の時間は、始まりと終わりの時間を決める(9時~18時等)、又は、何時間実施するかのみ決める(5時間以上)ことが一般的です。
特に子どもが乳幼児の場合、長時間母親と離れるのが難しいといった場合には、短時間(1~2時間程度)のみ実施するということもあります。
子どもの引渡し方法
どこで子どもを引渡すかも事前に決めておくと安心です。
方法としては、面会場所まで監護親が連れて行く、集合場所(自宅近くの公園)を決めておくということが考えられます。
面会場所
面会場所については、特に制限しない場合と、事前に決めておく場合があります。
事前に決めておく場合には、公園、ファミリーレストラン、遊園地等の施設を指定する場合が多いです。
また、遠すぎるのが心配な場合には、「市内のみ」といった形で決めることもあります。
宿泊の有無
宿泊の有無についても決めておくことが考えられます。
子どもが小さい場合には、子どもの負担を考慮し、日帰りで実施することが多いです。
行事への参加の有無
毎月実施する面会交流とは別に、行事(入学式や卒業式、運動会等)への参加を認めるかについても取り決めておくとよいでしょう。
また、行事へ参加した場合には面会交流を1回とカウントするのか、別途毎月決まった回数の面会交流を実施するかについても明確にルール化しておくとよいでしょう。
連絡手段
面会交流の日程調整や、面会交流中の連絡手段についても取り決めておくとスムーズです。
例えば、連絡はメール・LINEで行う、日程の変更は○日前までに連絡するといったことを定めておくとよいでしょう。
3. その他の面会交流のルール
上記のほか、面会交流中に避けて欲しいことを定める場合もあります。
例えば、第三者を立ち会わせない、高価なプレゼントは送らないなどといった形です。
また、非監護親のみで面会交流を実施するのが心配な場合には、監護親が立ち会う旨を定める場合もあります。
4. 面会交流のルールの決め方
面会交流のルールを取り決める場合には、まずは当事者間で協議をすることが考えられます。
この場合には、取り決めた内容を必ず書面に残すようにしましょう。
特に、相手に守って欲しいルールがある場合には、明確に記載することが必要です。
また、当事者が譲らず合意ができない場合には、面会交流の調停で協議をすることになります。
調停とは、1名の裁判官(又は調停官)と2名の調停委員で組織される調停委員会が、当事者の話し合いを仲介し、当事者間で合意を目指す手続きです。
第三者を通じて話し合いを行うことにより、当事者同士のみで話し合う場合と比べて、スムーズな話し合いができることが期待できます。
調停でも話し合いが整わない場合には、審判という手続きに移行します。
審判では、裁判官が当事者の主張を踏まえて一定の判断を下します。
面会交流の場合には、面会交流の頻度や時間を裁判所が決定します。
面会交流調停については、以下のコラムで解説しています。
5. 調査官調査について
面会交流の方法や頻度について調停においても当事者間の合意ができない場には、裁判官の決定により調査官調査が実施されることが多いです。
調査官とは、家庭裁判所で取り扱っている家事事件、少年事件などについて調査を行う人のことです。
心理学や社会福祉学などの専門的知見を活かして一定の事項を調査するのが調査官の仕事であり、面会交流の場面では、両親双方との面接、子の意向・心情調査(調査官が子どもと面会し、面会交流についての思い等を聞くこと)を行います。
また、交流場面観察といって、子どもと非監護親と面会する場面を調査官が観察することもあります。
これらの調査の内容を調査官が調査報告書にまとめるのですが、裁判官はこの調査報告書を重視した決定を出すことが多いため、調査報告書野内容は非常に重要です。
6. 面会交流のルールが守られない場合は?
面会交流のルールを取り決めたにも関わらず、相手がそのルールを守ってくれない場合でも、一方的に面会交流を拒否してしまうことは避けましょう。
拒否してしまうと、相手から慰謝料を請求されたり、間接強制(面会交流を実施しない場合、不履行1回あたり○円支払え)を申し立てられてしまうなどのリスクがあります。
まずはルールを守ってもらえるよう申し入れをしつつ、相手が応じない場合には、再び面会交流の調停を申し立て、その中で話し合いをするとよいでしょう。
7. まとめ
面会交流の実施は、子どもの成長のために重要な機会であると考えられており、事前にルールを取り決めることでスムーズな実施が期待できます。
しかし、別居や離婚をした親同士ではルールの協議がうまくいかない場合も多いでしょう。
このような場合には、弁護士に相談することで協議がうまくいったり、調停のサポートをしてもらえることが期待できますので、お気軽にお問い合わせください。