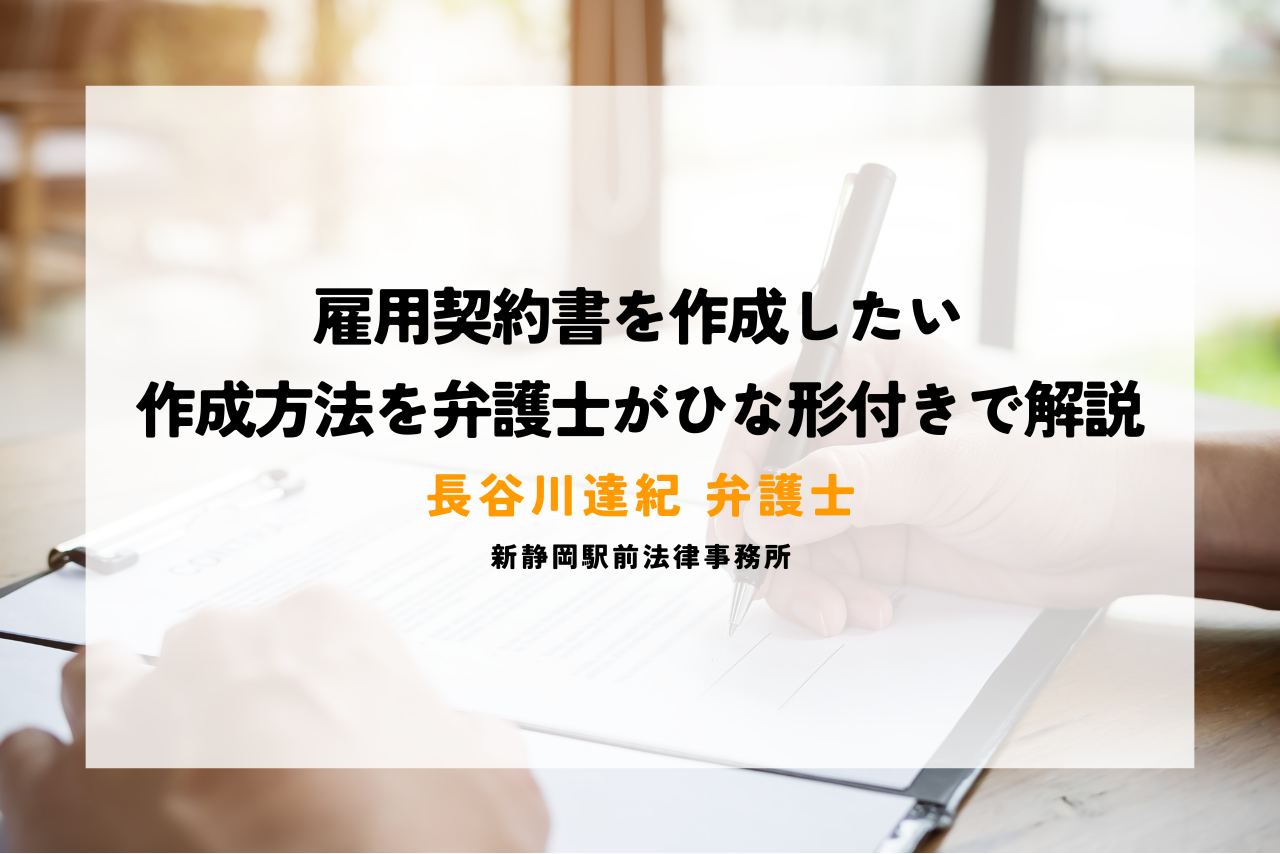企業や自営業の方が従業員を雇用する場合、雇用契約書や労働条件通知書等の労働条件を明示した書類を作成することが必要です。
本稿では、雇用契約書の作成方法を弁護士が解説いたします。
目次
1. 雇用契約書とは
「雇用契約書」とは、使用者(雇用主)と労働者(従業員)との間で合意された労働契約の内容を書面化したものをいいます。
雇用契約書と併せて作成されることが多い書類として、労働条件通知書があります。
これは、労働者の労働条件を書面により明示するための書類として使用されることが多いです。
一般的には、雇用契約書には使用者と労働者の双方が署名・押印をし、労働条件通知書には労働者の署名・押印をしないことが多いですが、法律上、このような運用をすることが義務付けられているわけではありません。
そのため、「雇用契約書兼労働条件通知書」というタイトルで1通の書類を作成したり、労働条件通知書を作成せずに雇用契約書に労働条件を記載する企業もあります。
また、労働基準法第15条1項は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められており、使用者は労働者に対し、雇用契約書や労働条件通知書等において、労働条件を明示することが義務付けられています。
2. 絶対的記載事項
労働準法施行規則第5条1項は、労働者に明示することが義務付けられている具体的な労働条件(絶対的記載事項)を定めています。
- 労働契約の期間(同項1号)
- 就業場所及び従事すべき業務(同項1号の3)
- 始業時間、終業時間、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇(同項2号)
- 賃金の決定、計算、支払方法、締切り、支払時期(同項3号)
- 退職及び解雇に関する事項(同項4号)
また、有期雇用の労働者に対しては、以下の労働条件も明示する必要があります。
- 更新の基準、更新回数の上限の有無と回数(同項1号の2)
- 無期転換の申込機会、無期転換後の労働条件((同条5項)
さらに、パートタイム・有期雇用労働法第6条に基づき、パートタイムやアルバイトなどの短時間労働者に対しては、以下の労働条件も明示する必要があります。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
3. 相対的記載事項
労働準法施行規則第5条1項は、該当する制度が存在する場合には、明示することを義務とする労働条件を定めています(相対的記載事項)。
- 退職金の定めが適用される労働者の範囲、決定、計算、支払方法、支払時期(同項4号の2)
- 臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当、最低賃金金額(同項5号)
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品等(同項6号)
- 安全及び衛生(同項7号)
- 職業訓練(同項8号)
- 災害補償及び業務外の傷病扶助(同項9号)
- 表彰及び制裁(懲戒処分等)(同項10号)
- 休職(同項11号)
4. 雇用契約書の作成方法
絶対的記載事項を必ず記載する
雇用契約書の作成に当たっては、前述した絶対的記載事項を必ず記載するようにしましょう。
雇用契約書ではなく、別途労働条件通知書を作成し、労働条件通知書に記載しても問題ありません。
また、相対的記載事項については、書面での明示は義務付けられていませんが、相対的記載事項を明示したことを客観的な記録として残すために、相対的記載事項も雇用契約書又は労働条件通知書に記載しておいた方が良いでしょう。
なお、労働基準法施行規則の改正により、労働者の希望があれば、FAX、Eメール、LINE、SMSなどによる労働条件の明示も可能となりました(労働準法施行規則第5条4項)。
ただし、あくまで原則は書面で行うこととされていますし、「労働者の希望」があったことを証拠として残す必要があることから、大きな支障がないようであれば、書面で行うことをお勧めします。
労働基準法を遵守する
労働基準法に違反する労働契約の内容は無効となります(労働基準法第13条)。
各労働条件を定めるに当たっては、労働基準法に違反するものが含まれていないか、弁護士や社会保険労務士等の専門家に確認してもらうのが良いでしょう。
また、就業規則に定められた労働条件に達しない労働条件を定めた場合も、無効となります(労働契約法第12条)。
弁護士や社会保険労務士等の専門家に相談するに当たっては、就業規則も併せて確認してもらうと良いでしょう。
実態に即した労働条件を定める
労働基準法第15条2項は、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と定めています。
労働条件が実際の就労環境や労働の内容と異なる場合、労働者からの即時解除が可能となってしまうので、実態に即した労働条件を定めるようにしましょう。
労働条件通知書のひな形
雇用契約書及び労働条件通知書の作成に当たっては、厚生労働省が公開している労働条件通知書のひな形をベースにすると良いでしょう。
厚生労働省が公開している労働条件通知書のひな形のタイトルを「雇用契約書兼労働条件通知書」と変更し、労働者に署名・押印をしてもらう方法でも良いですし、別途雇用契約書を作成し、「労働条件は別紙労働条件通知書のとおりとする」と記載して署名・押印をしてもらう方法でも構いません。
ひな形は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
労働者の署名・押印
雇用契約書を作成する場合、必ず労働者の署名・押印をもらうようにしましょう。
労働者の署名・押印がない場合、労働者が労働条件に同意していたことを証明することが困難になり、法的紛争となった場合に不利益を被るおそれがあります。
基本的に、雇用契約書に署名・押印があれば、労働条件通知書には署名・押印がなくても問題はありませんが、雇用契約書と労働条件通知書を別途作成する場合には、念のため、労働条件通知書にも署名・押印をもらっておいた方が無難です。
このような労働条件通知書は見たことがない、交付されていないなどという反論に対応できるようにするためです。
また、雇用契約書と労働条件通知書は2通作成し、労働者に1通を交付し、もう1通は使用者側で保管するようにしましょう。
使用者側が原本を保有していないと、紛争になった際に、労働者が雇用契約書や労働条件通知書を偽造したり、雇用契約書を作成していないなどと主張してきた場合に、対応ができないためです。
5. まとめ
雇用契約書の作成方法を誤ってしまうと、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、30万円以下の罰金が課される(労働基準法第120条1号)などのリスクがあります。
また、労働者との紛争を招来するおそれがあり、労働審判や訴訟で不利な判断がなされ、大きな損失を被る可能性もあります。
雇用契約書の作成に当たっては、弁護士や社会保険労務士に相談をし、場合によっては、作成を依頼することを検討すると良いでしょう。
また、既に会社が使用している雇用契約書のひな形がある場合でも、内容に不安があるようであれば、一度専門家にチェックしてもらうことで、法的紛争を予防できる可能性が高まります。
当事務所には、企業側の労働案件を多く取り扱っている事務所に所属していた弁護士が在籍しており、その知識と経験は豊富です。
労働問題に関する相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。