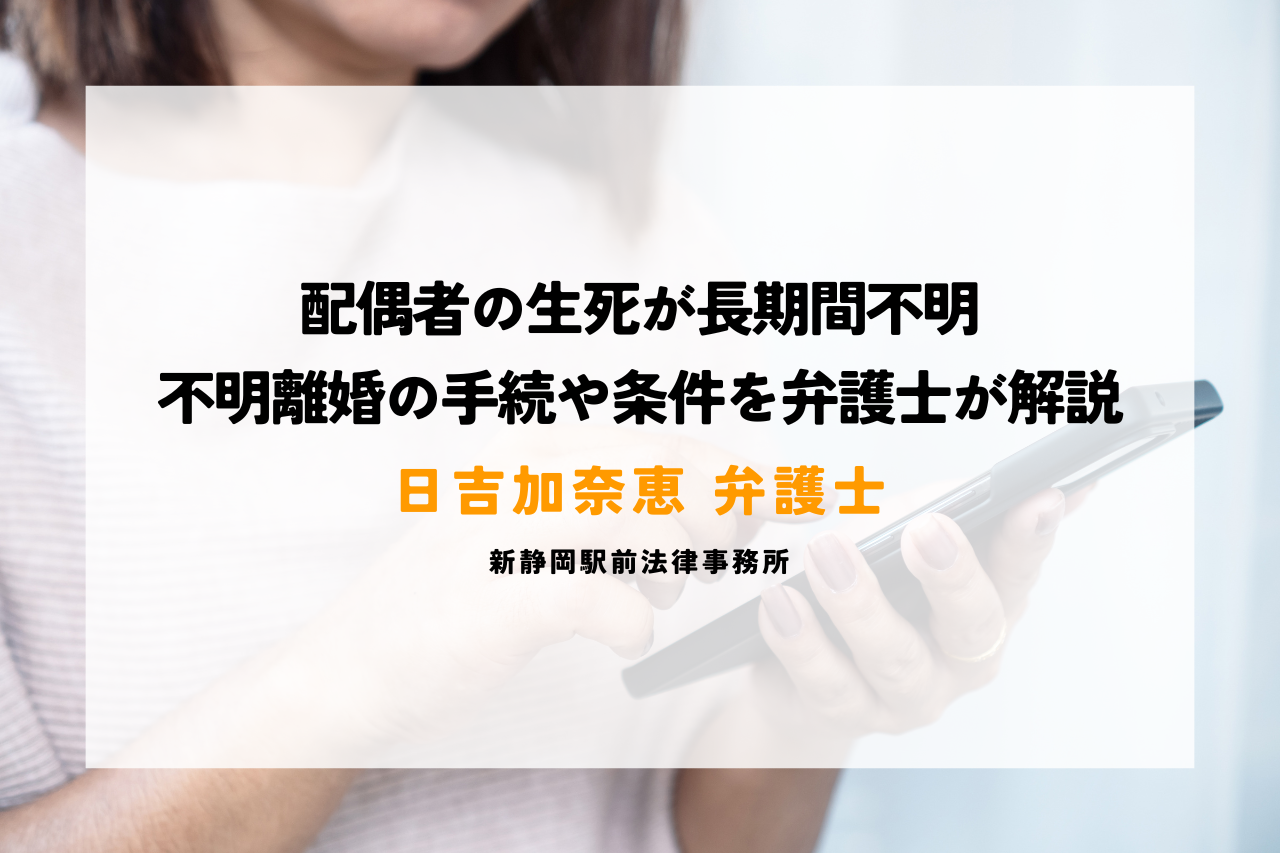配偶者が家を出ていき長期間音信不通となっている場合、離婚をしようとしても配偶者と連絡がとれず手続きが難しい場合もあるでしょう。
このような場合には、裁判で離婚をすることができることがあります。
そこで本記事では、配偶者の生死が不明な場合の離婚の手続きについて解説します。
目次
1. 配偶者の生死が不明な場合は離婚できる?
民法には離婚事由が定められており、この事由を満たせば、相手が離婚に同意しなくても裁判をすることで離婚することができます。
この離婚事由のうちのひとつに定められているのが「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」です(民法第770条第1項3号)。
つまり、配偶者が生死不明な状態が3年以上続いていれば、裁判をすることで離婚をすることができます。
ただし、「生死不明」である必要がありますので、配偶者と連絡が取れなくても、配偶者が生存していることが判明している場合には、生死不明を理由に離婚することはできません。
なお、配偶者の生存が確認できていたとしても、配偶者が勝手に家を出て戻らない場合には、別の離婚事由である「悪意の遺棄」(民法第770条第1項2号)や、「婚姻を継続し難い重大な理由」(民法第770条第1項5号)があるとして離婚をできる場合があります。
配偶者の生死が3年以上不明といえる場合とは
配偶者の生死が3年以上不明といえる場合とは、単に所在が不明な場合ではなく、配偶者の年齢や性格、健康状態、所在不明に至る経緯や配偶者や親族の対応等を総合的に考慮して判断されるとされています。
例えば、警察への捜索願の提出や勤務先、親族・知人への連絡を試みても見つけられなかったといった客観的な事実が認められる必要があります。
また、いつから数えて3年が経過する必要があるかについては、最後の音信のとき(最後に連絡や接触をしたとき)とされています。
2. 生死不明の配偶者と離婚する場合の流れ
①離婚訴訟の提起
3年以上生死不明の配偶者と離婚をしたい場合には、離婚訴訟を提起する必要があります。
生死不明の配偶者の場合、相手と協議して離婚届を提出する協議離婚や、調停で離婚について話し合う調停ができないことから、裁判にて裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。
なお、離婚訴訟は、まずは調停をしてから提起する必要があります(調停前置主義、家事事件手続法第257条2項本文)が、配偶者が生死不明で調停に応じる可能性が極めて低い場合には、例外的に調停を経ずに裁判をできるとされています(家事事件手続法第257条2項ただし書)。
離婚訴訟は、訴状(原告の請求内容や主張を記載した書面)を裁判所に提出することで行います。
離婚訴訟の詳しい方法は、以下のコラムをご参照ください。
また、配偶者が生死不明の場合、当然住所も不明でしょうから、訴状を配偶者の自宅にに送付することができません。
この場合には、公示送達(意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、又は、相手方の住居所が不明であるために、意思表示を到達させることができない場合に、意思表示が到達したものとみなす手続をいいます(民事訴訟法第110条))という方法を取る必要があります。
公示送達は、裁判所に申し立てることにより行うことができます。
公示送達の詳細は、以下のコラムをご参照ください。
②第1回口頭弁論期日の開催
公示送達によって相手方に訴状が送達された場合には、口頭弁論期日(当事者の主張や証拠を公開の法廷で審理する期日のこと)が開催されます。
裁判所に対し、相手方が3年以上生死不明であることを認めてもらう必要があるので、後述する証拠と共に、こちらの主張を整理した書面をこの期日までに提出しておくようにしましょう。
③判決・離婚届の提出
裁判所が離婚事由があると認めた場合には、離婚を認めるという判決が出されます。
被告への判決の送達(こちらも公示送達で行われます)から2週間以内に被告が控訴をしなければ、判決が確定し、離婚届の提出が可能となります。
判決の確定により離婚は成立しますが、この場合でも離婚届の提出は必要です。
配偶者の署名なく単独で離婚届の提出ができますが、判決確定から10日以内に離婚届の提出をする必要があるので注意が必要です。
また、離婚届の提出の際には、判決謄本(判決書の写しのこと)も提出する必要があります。
判決謄本は、離婚訴訟を行った家庭裁判所に請求すると取得することができます。
3. 離婚訴訟に提出する証拠は?
前述のとおり、離婚訴訟において裁判所に離婚を認めてもらうためには、証拠が必要です。
警察に捜索願を出している場合はその写しを証拠として提出するとよいでしょう。
また、勤務先や配偶者の親族、知人に協力が得られる場合には、「陳述書」という形で、配偶者が勤務先に長期間出勤していないことや、連絡を試みても連絡が取れないことを証言してもらうとよいでしょう。
陳述書とは、当事者や関係者の証言をまとめた書面をいい、知っていることや経験したことを口語形式で記載してもらうことが一般的です。
4. 証拠が少ない場合は?
今まで述べてきたように、配偶者の生死が3年以上不明な場合には、それを理由に離婚をすることができますが、そのためには、裁判所に証拠を元に3年以上生死不明であると認めてもらう必要があります。
配偶者の親族や知人に協力が得られないなど、証拠の収集が困難な場合には、離婚裁判を提起する際に、併せて「婚姻を継続し難い重大な事由がある」ということも主張するとよいでしょう。
こちらも民法上定められた離婚事由の一つです(民法第770条第1項5号)。
「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは、一般的には、「婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合」をいうとされています。
生死不明とまでは言えない場合であっても、配偶者と長期間連絡が取れない場合には、婚姻関係が破綻していると認められる可能性は高いといえるでしょう。
5. 配偶者の生死が7年以上不明な場合
配偶者の生死不明な期間が7年以上不明な場合には、失踪宣告という手続きをすることも考えられます。
失踪宣告とは、不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき等に、家庭裁判所が失踪宣告をすることで、不在者を法律上死亡したものとみなす手続きです(民法第30条1項)。
この手続きをすると、配偶者は法律上死亡したものとされるため、配偶者とは死別となり、離婚届の提出等は不要です。
配偶者からの相続権も発生することとなります。
ただし、失踪宣告はあくまで死亡したと「みなす」手続であることから、後に配偶者が生存していることが判明した場合には、失踪宣告は取り消されることとなる点には注意が必要です。
失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てることにより行います。
6. まとめ
当事務所では、これまでに数多くの離婚に関するご相談をお受けしております。
相手方の生死が不明な場合に離婚訴訟を提起した経験もございます。
配偶者の生死が不明で離婚をしたい場合には、裁判手続が必須となりますが、書面の作成や証拠の収集等が必要となることから、ご自身のみでは行うのが難しい場合もあるでしょう。
まずはお気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。