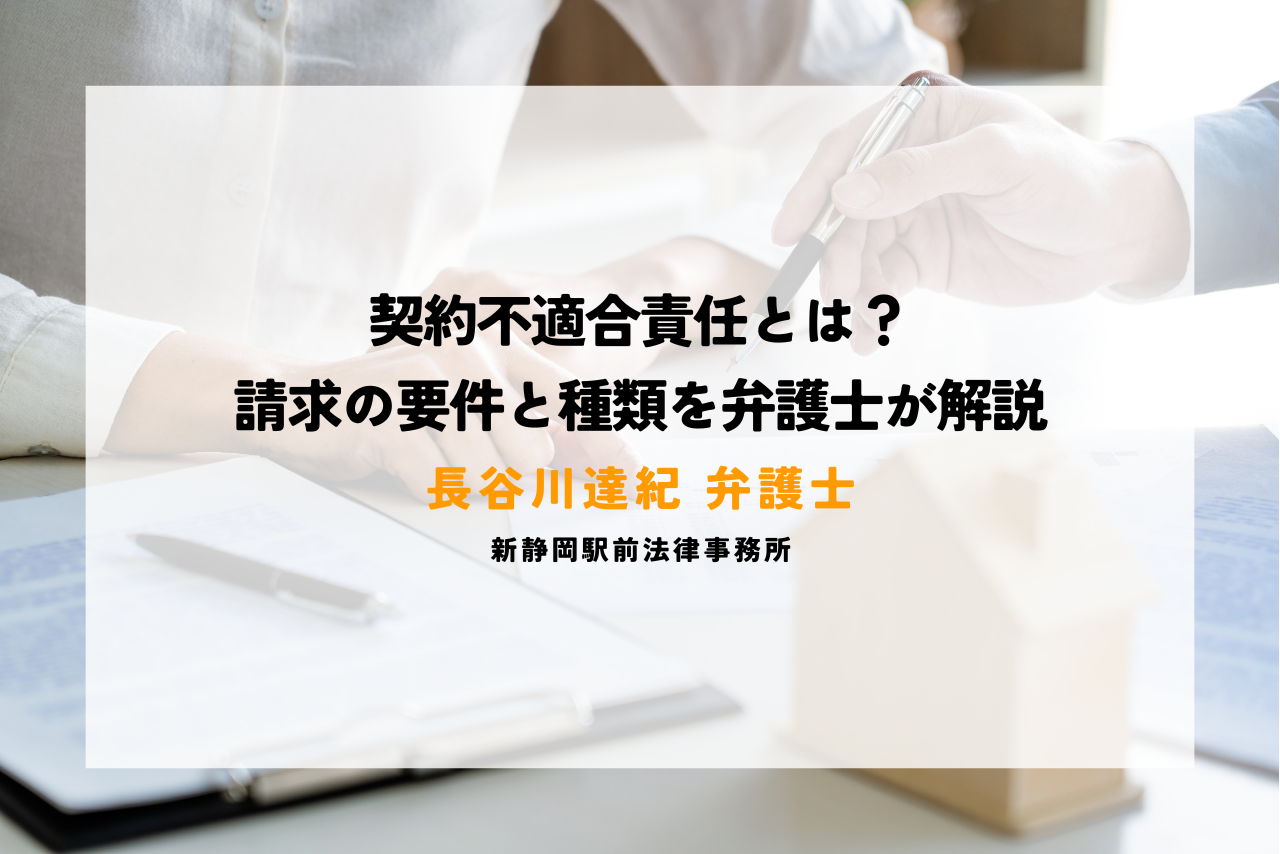2020年4月1日の改正民法の施行により、契約不適合責任が定められました。
契約不適合責任は、実務で問題となることが多く、特に不動産案件において問題となることが多い法的責任です。
そこで、本稿では、契約不適合責任の要件と種類を解説いたします。
目次
1. 契約不適合責任とは?
「契約不適合責任」とは、契約に基づき引き渡された物が契約内容と異なる場合に売主が買主に対して負う法的責任のことをいいます。
売買契約や請負契約の際にが問題となることが多く、特に不動産の売買や請負の際に問題になりやすいです。
2. 瑕疵担保責任との違い
改正民法の施行前は、瑕疵担保責任という規定が定められていました。
改正民法の施行により、瑕疵担保責任の条項が削除され、契約不適合責任が新設されました。
瑕疵担保責任は、その性質について学説上大きな争いがあり、法定責任説(民法が特別の法的責任を認めたという学説)及び契約責任説(契約内容の不履行責任を定めたものであるという学説)が対立していましたが、契約不適合責任では、契約責任(債務不履行責任)であることが明記されました。
また、瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」に限定されていましたが、契約不適合責任では「隠れた」という要件が廃止されました。
3. 契約不適合責任の要件
種類
契約で定められた物と引き渡された物の種類が異なる場合、契約不適合責任が生じます。
例えば、木目調の床にすることが契約内容となっているにもかかわらず、引き渡された物件の床がタイル素材の床であった場合には、種類の契約不適合ということで契約不適合責任が生じます。
数量
契約で定められた物の数量と引き渡された物の数量が異なる場合、契約不適合責任が生じます。
例えば、ガスコンロを3つ設置することが契約内容となっているにもかかわらず、引き渡された物件のガスコンロが2つであった場合には、数量の契約不適合ということで契約不適合責任が生じます。
品質
契約で定められた物の品質よりも引き渡された物の品質が劣る場合には、契約不適合責任が生じます。
例えば、中古物件の売買契約において、壁のひび割れはないと契約で定められていたにもかかわらず、引き渡された物件の壁にひび割れがあった場合には、品質の契約不適合ということで契約不適合責任が生じます。
4. 契約不適合責任に基づく請求の種類
追完請求
契約不適合責任が生じた場合、買主は売主に対し、契約に適合していない部分の履行の追完を求めることができます(民法第562条1項)。
改正民法施行前の瑕疵担保責任においては、損害賠償請求と契約の解除のみが定められていましたが、契約不適合責任では、追完請求が明記されました。
なお、契約の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである時は、追完請求は認められません(民法第562条2項)。
減額請求
買主が売主に対し、契約不適合部分の追完を催告したにもかかわらず、相当の期間内に追完を行わない場合、若しくは、追完が不能の場合又は売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した時には、代金の減額請求が認められます(民法第563条1項、同条2項)。
代金減額請求も、改正民法施行により明記された制度です。
減額される金額は、不適合の内容や程度によります。
裁判実務では、後述する損害賠償請求における損害額と同様に、減額されるべき金額が争点となることが多いです。
なお、契約の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである時は、追完請求は認められません(民法第563条3項)。
損害賠償請求
契約不適合責任により損害が生じた場合、損害賠償請求が可能です(民法第564条、同第415条1項本文)。
損害賠償請求においては、損害額が争点となることがほとんどです。
例えば、修理が必要な場合、修理に必要な金額がいくらかによって、損害額が決まりますが、妥当な修理費用に争いが生じることがあります。
また、損害の範囲として、例えば、お風呂の水栓が故障していた場合に、水栓の故障部分のみを修理すれば足りるのか、お風呂全体の修理が必要なのかによって、損害額が大きく異なってきます。
なお、契約不適合が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、売主の責めに帰することができない事由によるものである場合には、損害賠償請求は認められません(民法第415条1項但書)。
解除
買主が売主に対し、契約不適合部分の追完を催告したにもかかわらず、相当の期間内に追完を行わない場合、又は、追完が不能の場合には、契約を解除することができます(民法第564条、同第541条本文、同第542条)。
ただし、不適合の程度が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である時は、解除は認められません(民法第541条但書)。
また、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである時は、解除は認められません(民法第543条)。
5. 契約不適合責任の期間
前述した契約不適合責任に基づく請求を行う場合、その期間は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に不適合を通知しなければいけません(民法第566条、同第637条1項)。
上記規定は任意規定のため、特約により排除することが可能です。
ただし、不適合の存在を知りながら買主に告げなかった場合や自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利に関し不適合が生じた場合には、上記期間を排除する特約を定めた場合であっても、契約不適合責任を免れることはできません(民法第572条)。
また、新築住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の契約不適合責任は、引渡しから10年間の責任追及が可能であると定められており、同規定は強行法規であるため、特約で排除することはできません。
さらに、売主が宅地建物取引業者の場合、不適合責任の期間を引渡しから2年以上とする特約以外の特約は無効となります(宅地建物取引業法第40条1項)。
6. まとめ
上記のとおり、契約不適合責任は、主に不動産案件で問題となることが多いです。
不動産案件における減額請求や損害賠償請求では、減額の金額や損害額が争点となり、金額に関する主張に大きな開きが出て、主張・立証(証明)に失敗してしまうと、大きな不利益を被るおそれがあります。
また、契約不適合責任が認められるか否かは、事実認定や法的評価を伴うことがあるため、法的知識や経験が必要となることがあります。
そのため、契約不適合責任に基づく請求を検討されている方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所は不動産案件に注力しており、契約不適合責任の経験と実績も豊富です。
当事務所への相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。