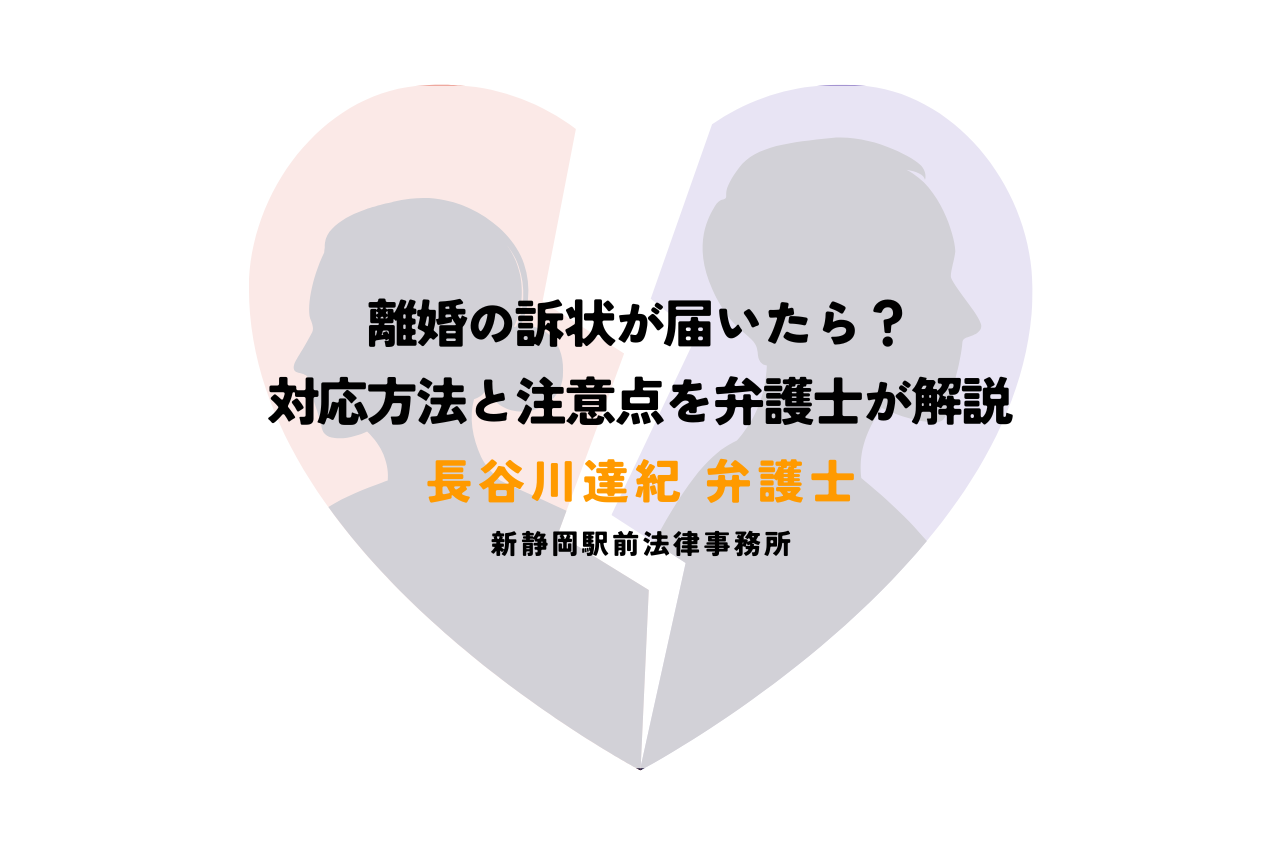裁判所から離婚の訴状が届き、どのように対応したら分からないという方も多いでしょう。
離婚訴訟の訴状が届いた場合、対応方法を誤ると大きな法的リスクを負うおそれがあります。
本稿では、離婚の訴状が届いた場合の対応方法と注意点を解説いたします。
目次
1. 訴状とは
「訴状」とは、訴訟を提起する(裁判を起こす)に当たり、裁判所に提出する書類の1つです。
訴状には、裁判所にどのような判決を出して欲しいか(どのような法的請求をしたいのか)を記載する「請求の趣旨」と、法的請求の根拠となる事実を記載した「請求の原因」が記載されています。
裁判所に提出する「正本」と被告に送達する「副本」を裁判所に提出し、訴状の審査が完了すると、訴状の副本が被告に送達されることになります。
送達の方法は複数ありますが、離婚訴訟の場合、配偶者の住所を知っている又は知らない場合でも調査が容易であるため、自宅に送達されることがほとんどです。
2. 離婚訴訟とは
「離婚訴訟」とは、一般的に、離婚の請求と離婚に伴い生じる附帯請求(養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など)を行う裁判のことをいいます。
離婚及び離婚に伴う附帯請求を行う場合、原則として、訴訟提起に先立ち、離婚調停を申し立てる必要があるため(「調停前置主義」といいます。家事事件手続法第257条1項)、離婚の訴状が届いたという方は、先んじて離婚調停を行っており、かつ、離婚調停が不成立や取下げにより終了していることがほとんどです。
3. 対応方法
①訴状と期日通知書の内容を確認する
訴状が届いたら、まずは訴状の内容と裁判所が作成した期日通知書の内容を確認しましょう。
訴状には前述した請求の趣旨と請求の原因が記載されていますので、その内容を確認し、請求に応じられるか否か、事実や認識と異なる点があるかなどを確認しましょう。
期日通知書には、第1回期日の日時と後述する答弁書の提出期限が記載されていますので、確認しましょう。
被告側は、第1回期日に出頭しなくても良い権利が法律上認められていますので(答弁書の「擬制陳述」という答弁書を提出すれば答弁書の内容を第1回期日で主張したとみなす制度です)、第1回期日に出頭できなくても問題ありません。
ただし、答弁書を提出しないと、上記擬制陳述の制度は利用できませんので、必ず答弁書の提出期限を確認した上で、答弁書の提出期限を守るようにしましょう。
②答弁書の作成及び提出
「答弁書」とは、訴状の請求の趣旨に対する答弁と請求の原因に対する認否・反論を記載し、裁判所に提出する書面です。
実務上、請求の趣旨に対しては、「1原告の請求を棄却する2訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める」と答弁することがほとんどです。
特に、離婚訴訟の場合には、先立つ離婚調停で話合いがまとまらず、不成立又は取下げとなっていることがほとんどのため、離婚訴訟における原告側の請求の趣旨の内容を認めることはまずありません。
また、不用意に請求の趣旨の内容を一部でも認めてしまうと、後ほど撤回することが困難であることから、答弁書の段階では上記のように「原告の請求を棄却する」としておくべきです。
離婚自体には応じるが、条件次第であるという場合であっても、離婚の反訴請求(相手方の訴訟提起に対し同じ訴訟手続においてこちらが相手方に訴えを起こすこと)を行うことによって、裁判所は離婚を認める判決を下すことができるので、上記のような場合であっても、「原告の請求を棄却する」と答弁をしておく方が無難です。
訴状に記載されている請求の原因に対しては、認否を行う必要があります。
認否は、基本的に、「認める」、「否認する」、「争う」、「不知」の4つで行います。
例えば、「原告と被告は令和7年1月1日に婚姻した」という内容が事実である場合は「認める」、「被告が原告に暴力を振るった」という内容が事実と異なる場合は「否認する」、「原告は被告に対し離婚に伴う慰謝料として300万円の請求権を有する」という法的評価が含まれる内容のうち納得がいかないものに対しては「争う」、「原告は被告の暴力について原告の母親に相談した」という内容を知らなかった場合には「不知」という認否をすることになります。
また、請求の原因に対しては、反論を行うのが一般的です。
例えば、「被告が原告に暴力を振るった」という主張に対して、「原告と被告が口論になった際に、原告が包丁を持ち出したので、原告の腕を掴んで包丁を取り上げたに過ぎない」というように反論を加えます。
答弁書の提出期限までに、請求の原因に対する認否・反論が間に合わない場合には、「請求の原因に対する認否・反論は追って行う」と記載して答弁書を提出することも可能です。
その場合、裁判所から連絡があり、請求の原因に対する認否・反論はいつまでに行うことができるかという確認の連絡があり、第2回目期日の日程調整がなされることが多いです。
③主張反論・立証反証
答弁書を提出した後は、期日を重ねながら、互いに主張・反論と証拠による立証・反証が行われることになります。
訴訟指揮は裁判官の裁量に委ねられているため、裁判官が当事者の意向を確認しながら、訴訟の進行を主導することになります。
④和解・判決
主張・反論と証拠による立証・反証が出尽くした時点で、裁判官は暫定的な心証(裁判官が認定すべき事実についての確信の度合い)を得ることができるので、和解協議に入ることが多いです。
和解協議の結果、合意が成立した場合には、裁判上の和解が成立し、裁判は終了となります。
和解協議が決裂した場合、当事者の尋問(事案によっては証人尋問)が行われます。
尋問が終了すると、裁判官は確定的な心証を得るため、尋問後に再度和解協議が行われることが多いです。
上記と同様に尋問後の和解協議で合意が成立した場合には、裁判上の和解が成立し、裁判は終了となります。
一方、和解協議が決裂した場合には、裁判所が判決を下すことになります。
⑤控訴審
原審である家庭裁判所の判決が下され、判決書を当事者双方が受領した後2週間が経過するまでは管轄の高等裁判所に対する控訴が可能です。
双方から上記期限内に控訴提起がなされなければ、判決が確定し裁判は終了となりますが、和解協議が決裂していることから、判決に進んでいる場合には、当事者の一方又は双方が控訴提起することが多いです。
控訴審において、和解が成立することも多いですが、控訴審でも和解協議が決裂した場合には、控訴審の判決に進むことになります。
なお、離婚訴訟の場合、事実関係や法的評価が争点となることが多く、控訴審でも事実関係や法的評価が争われることがほとんどです。
控訴審の判決に対して上告をするためには、憲法違反等の上告理由が必要となりますので、事実関係や法的評価が争点の場合、上告審で結論が変わる可能性は皆無に等しいです。
そのため、離婚訴訟の場合、事実上、控訴審が最後の和解協議及び裁判所による判断の場となることから、実務上、控訴審で和解が成立又は判決が確定するケースが多いです。
4. 訴状が届いたときにしてはいけないこと
訴状を無視する
離婚の訴状が届いた際に最も危険な行為は、訴状を無視することです。
訴状を無視してしまうと、裁判所は原告の請求及び原告の主張する事実に対する認否や反論がないものと判断し、原告の請求及び原告の主張する事実に沿った判決を出す可能性があります。
また、裁判所が訴状を送達するに当たっては、「特別送達」という方法を用いますが、不在の場合は郵便局の不在票がポストに投函されます。
不在票を無視して訴状を受領しなかった場合、「就業場所送達」という職場に訴状が届いてしまったり、「付郵便送達」という訴状を受領しなくても訴状が受領されたものとみなされる送達方法を取られてしまうおそれがあるので、不在票を確認した場合には必ず受領するようにしましょう。
弁護士に相談しない
裁判外での離婚協議や離婚調停と異なり、離婚訴訟は手続が厳格で、対応方法を誤ると大きな法的リスクを負う可能性があります。
特に、訴状が届いた段階の初期対応は非常に重要であり、この段階での対応を誤ってしまうと、取返しのつかない事態を招きかねません。
そのため、離婚の訴状が届いた場合には、弁護士に相談し、対応方法や見通し等を確認するべきです。
また、離婚訴訟を含む訴訟手続は、裁判所とのやりとり、期日への出頭、書面の作成、証拠の選定・提出準備、尋問の準備など、負担の大きい手続ですので、弁護士に依頼し、これらの対応を一任した方が良いでしょう。
なお、弁護士を選ぶポイントは以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
5. まとめ
前述のとおり、離婚訴訟を含む訴訟手続は、手続が厳格で負担の大きい手続ですので、弁護士に依頼することをお勧めします。
当事務所は、離婚案件に注力しており、離婚訴訟の経験と実績も豊富です。
当事務所への相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。