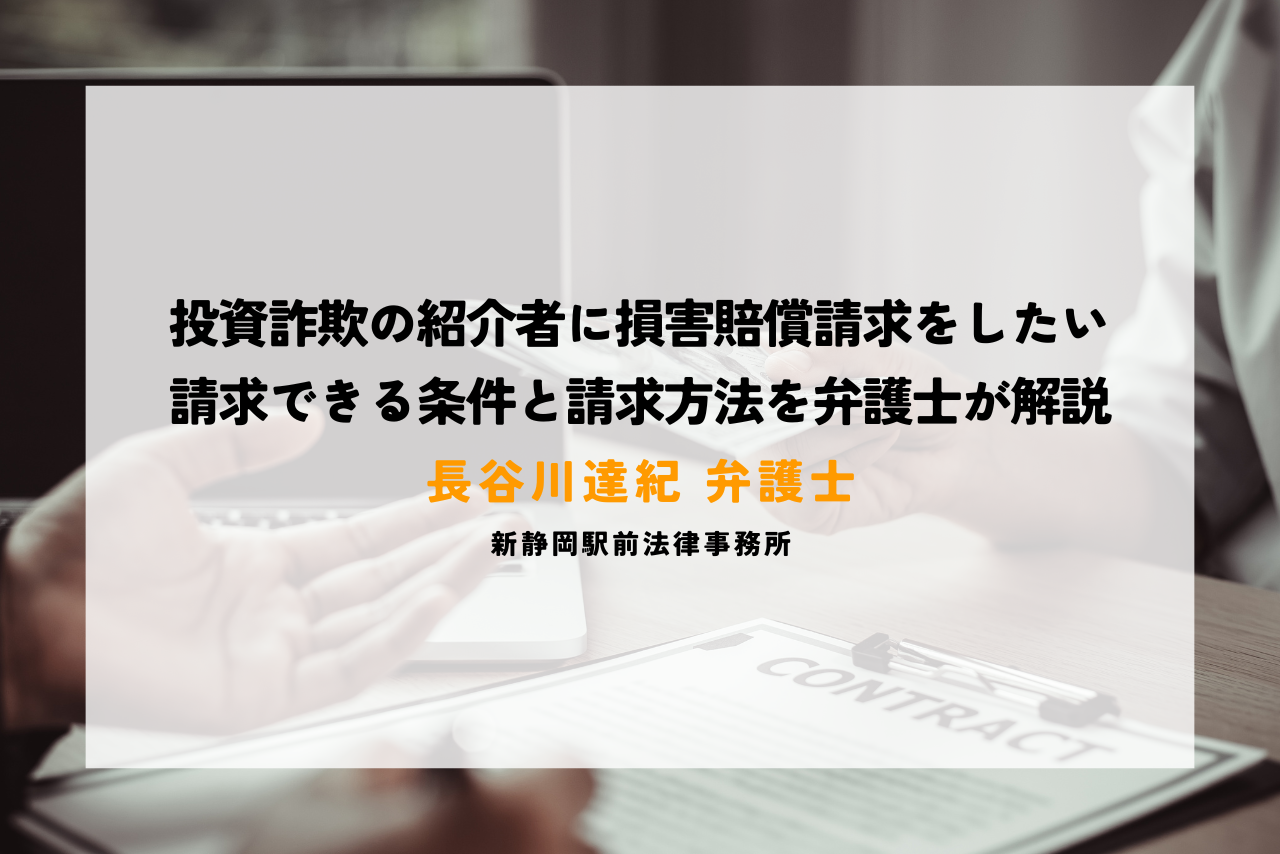投資詐欺の被害に遭ってしまった場合、投資詐欺の加害者から金銭を回収することは難しいことが多いです。
そのような場合、投資の紹介者・勧誘者に対して、損害賠償請求をすることができる場合があります。
本稿では、投資詐欺の紹介者・勧誘者に対し、損害賠償請求をすることができる条件と請求方法について、解説いたします。
目次
1. 投資詐欺とは
「投資詐欺」とは、元本保証、高利回り、確実に儲かるなどの虚偽の投資話を持ちかけて、金銭を支払わせる詐欺スキームの1つです。
近年、投資詐欺は増加しており、手口も巧妙になってきています。
そのため、詐欺の加害者の情報を得ることは非常に難しく、また、振込先の口座の凍結手続を行ったり、口座の名義人に対して返還請求をしても、他にも被害者が多数いたり、口座の残高が残っていないなどの理由で、回収ができないケースが多いです。
2. 紹介者に対する損害賠償請求の条件
知人から投資を勧められて投資をしたが、後ほど投資詐欺であることが判明したというケースは少なくありません。
このような場合、紹介者・勧誘者に対し、損害賠償請求が可能なことがあります。
紹介者・勧誘者に対し、損害賠償請求ができる条件は以下のとおりです。
①調査義務違反・説明義務違反
紹介者・勧誘者に対する損害賠償請求の法的根拠は、民法上の不法行為です(民法第709条)。
不法行為が認められるためには、紹介者・勧誘者の行為に違法性が認められることが必要です。
投資詐欺の場合、違法性を基礎づける行為としては、調査義務違反と説明義務違反が多いです。
調査義務違反とは、投資会社が適法に運営されているか、投資のスキームに不自然な点はないか、投資詐欺が疑われる勧誘文句がないか(「元本保証」、「絶対に儲かる」などの断定的表現)、実際に投資をした方にヒアリングをして問題なく運用できているかを確認するなどの十分な調査を尽くさないまま、投資を勧誘した場合に認められます。
説明義務違反とは、投資に伴うリスクなどの重要な事項を説明しなかったり、投資に関し虚偽の説明を行った場合に認められます。
なお、投資詐欺の場合、セミナーが開催されることがあります。
紹介者・勧誘者が積極的にセミナーに誘ったり、紹介者・勧誘者がセミナーの開催者であったという事情がある場合には、セミナーでの説明の内容が説明義務違反に該当していることもあります。
このような調査義務違反や説明義務違反が認められる場合には、違法性が認められることになります。
②紹介者の故意・過失
不法行為が認められるためには、紹介者・勧誘者に故意又は過失が認められることが必要です。
投資詐欺であることを知っていながら、虚偽の説明をして投資を勧めたような場合には、故意が認められることになります。
投資詐欺であるとは知らなかったが、投資詐欺であると知ることができたような場合には、過失が認められることになります。
一方で、投資詐欺の手口が巧妙で、紹介者・勧誘者が十分な調査を尽くしても投資詐欺であることに気付くことが困難であったような場合には、故意・過失が認められず、損害賠償請求も認められません。
投資詐欺は、手口が巧妙であることが多く、紹介者・勧誘者も投資詐欺と気付かず、かつ、自らも投資詐欺の被害者であるというケースが多いので、故意・過失が争点となることが多いです。
③過失相殺
紹介者・勧誘者の調査義務違反・説明義務違反や故意・過失が認められたとしても、損害賠償請求の全部又は一部が認められないことがあります。
例えば、紹介者・勧誘者に調査義務違反が認められるケースで、自らも十分な調査すれば容易に投資詐欺であると気付くことができたような場合、ご自身にも過失があったと判断されることがあります。
このような場合、「過失相殺」の規定(民法第722条2項)により、互いの過失の割合により損害賠償額が減額される可能性があります。
紹介者・勧誘者に損害賠償請求を行う場合には、自らにも過失がなかったか、過失があったとしてその割合はどの程度かを確認しておくべきです。
3. 損害賠償請求の方法
協議
紹介者・勧誘者に損害賠償請求をする場合、まずは裁判外で相手方と協議を行うと良いでしょう。
直接話し合う方法もありますが、やりとりの内容が正確な記録に残らないため、書面やメール等の記録に残る方法で協議をすることをお勧めします。
請求に際しては、内容証明郵便(いつ、誰がどんな内容の文書を送付したか証明してくれる日本郵便のサービス)の方法を利用することで、請求内容が記録に残りますし、相手方にプレッシャーを与えることができます。
訴訟提起(裁判上の請求)
裁判外での協議が整わなかった場合、損害賠償請求訴訟を提起することを検討しましょう。
投資詐欺の紹介者・勧誘者に対する損害賠償請求訴訟の場合、法律構成やその根拠となる事実の主張・立証(証明)が難しいことから、弁護士に依頼することをお勧めします。
調停
「調停」とは、裁判所での話合いの手続です。
調停委員会(裁判官・調停委員2名)が当事者の話合いを仲介してくれます。
訴訟と比較すると手続が簡便ですので、裁判外での協議が決裂し、ご自身で裁判手続を行いたいという場合には、調停を申し立てるのも1つの選択肢といえます。
また、紹介者・勧誘者は知人であることが多いので、訴訟で争うことはしたくないという方も、調停手続を利用することを検討しても良いでしょう。
もっとも、調停は、話合いの手続ですので、裁判所が何らかの結論を出すことはありません。
話合いがまとまらなかった場合、調停は不成立という形で終了します。
また、相手方が出頭しない場合も不成立で終了してしまいます。
そのため、訴訟と比較すると、紛争の解決力は弱いので、早期に紛争を解決したい、又は、裁判所に結論を出してもらいたいという場合には、調停ではなく訴訟を選択した方が良いでしょう。
4. まとめ
投資詐欺の紹介者・勧誘者に対する損害賠償請求では、調査義務違反・説明義務違反、故意・過失が認められるか、過失相殺が認められるか、過失相殺が認められるとしてその割合はどの程度かなど、法的評価が求められます。
これらの法的評価はご自身で判断することが難しい事項ですので、投資詐欺の紹介者・勧誘者に対する損害賠償請求を検討されている方は、まずは弁護士に相談し、見通しを聞いてみると良いでしょう。
当事務所は、詐欺被害案件に対応しており、投資詐欺の紹介者・勧誘者に対する損害賠償請求の経験・実績も豊富です。
詐欺被害に関する相談をご希望の場合には、問い合わせフォームよりご連絡ください。