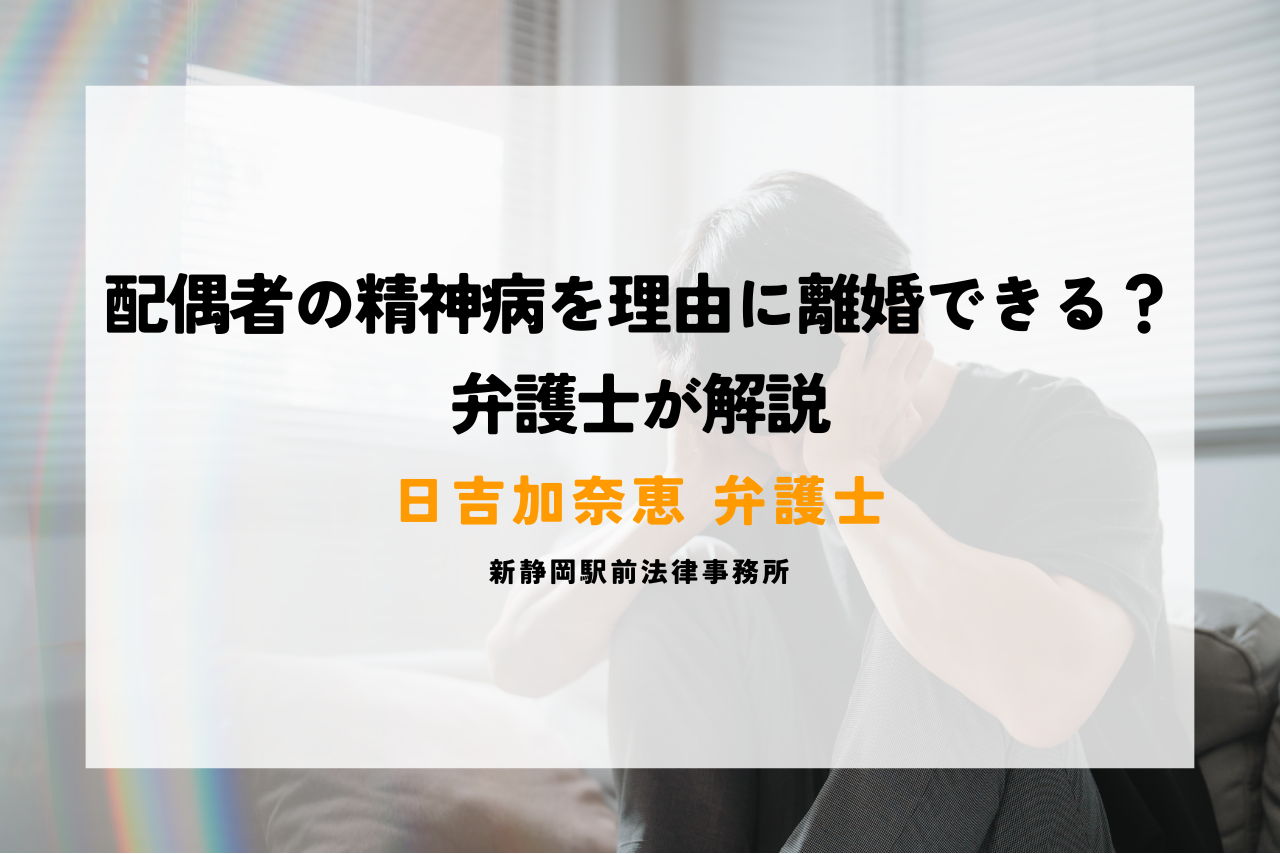配偶者がうつ病や統合失調症などの精神病にかかってしまった場合には、離婚をしたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
配偶者が精神病にかかってしまった場合、病状や生活状況によっては離婚が認められる可能性があります。
そこで本記事では、配偶者の精神病を理由に離婚が認められるか、離婚できる場合の手続きについて解説します。
目次
配偶者が精神病にかかってしまった場合に離婚できる?
配偶者が離婚に同意している場合
離婚は、相手と離婚することについて合意ができれば、離婚届を提出することで成立します(協議離婚といいます)。
配偶者が離婚をすることに合意している場合や、協議に応じてくれそうな場合には、まずは相手と離婚することや離婚の条件について協議するとよいでしょう。
また、当事者同士のみで協議することが難しい場合には、離婚調停を申し立てることも検討しましょう。
調停とは、裁判官(又は調停官)1名と2名の調停委員が、当事者の話し合いの仲介をする手続きです。
第三者である調停委員を介して話し合いをすることにより、話し合いがスムーズにできる場合があります。
配偶者が離婚に同意しない場合
当事者での協議や調停でも相手が離婚に同意してくれない場合には、離婚訴訟(裁判)をする必要があります。
訴訟において離婚をする場合には、民法定められた離婚事由があることが必要です。
離婚事由は、民法第770条1項に以下のとおり定められています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
ただし、2024年5月に改正された民法では、4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は削除されることとなりました(本記事の執筆時点では、まだ施行はされていません)。
民法が改正された理由としては、そもそも「回復の見込みのない」かどうかについては、医学的知識を必要とするため医師によっても判断が分かれるなど、訴訟において判断が難しいことや、精神病にかかってしまった人への差別を助長しかねないといった点が上げられます。
裁判実務上も、配偶者の精神病を理由とした離婚の請求については、4号ではなく5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かによって判断されることが多かったこともあり、民法改正がされたものと考えられます。
では、配偶者が精神病にかかっている場合、婚姻を継続し難い重大な事由があるとみとめられるのでしょうか。
そもそも「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、一般的に、「婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合」をいうとされています。
配偶者が精神病にかかっている=婚姻関係が破綻しているというものではなく、その他の事情(夫婦が別居しているかや、現状の生活状況など)と共に考慮要素の一つとして、離婚が認められるかを裁判所が判断することになります。
離婚事由があると認められやすい精神病
過去の裁判例の傾向からみると、以下のような精神病にかかっている場合、離婚が認められやすい傾向にあります。
- 統合失調症
- 躁うつ病
- アルツハイマー病
- 偏執病
離婚事由が認められづらい精神病
他方で、以下のような場合には離婚事由が認められづらいです。
- アルコール依存症
- ノイローゼ
- 精神衰弱
- 薬物中毒
ただし、これらの疾患に加え、ギャンブルばかりして生活費を入れない、アルコールを摂取すると暴力を振るうなどの事由があれば、離婚が認められる場合があります。
離婚の手続き
前述したとおり、相手が離婚に応じている場合には、離婚届を提出することで離婚ができます。
相手との協議が整わない場合は、まずは離婚裁判の前に、離婚調停を申し立てる必要があります。
これは、離婚など当事者の身分関係に関わる行為については、まずは調停において当事者間で話し合いをすることが適当であるという考えによるものです(調停前置主義、家事事件手続法第257条2項本文)。
ただし、配偶者の精神病の度合い等から、調停をすることが相当でないと認められる場合には、例外的に調停を経ずに裁判をできるとされています(家事事件手続法第257条2項ただし書)。
調停を経る必要があるか否かについては、裁判所の判断によりますが、一度訴訟を提起したあとに裁判所の判断により調停に付されることになると、その分時間がかかってしまう可能性があることには注意が必要です。
離婚調停でも相手と離婚の合意ができない場合には、離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟は、こちらの主張(離婚事由や離婚にあたって求める条件など)を記載した訴状等を管轄の裁判所に提出することによって提起できます。
管轄の裁判所は、当事者(夫又は妻)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
離婚訴訟の詳しい手続きは、以下のコラムで解説しています。
成年後見人について
配偶者の精神病が極めて重い場合など、配偶者が判断能力を欠いている場合には、配偶者に対して離婚訴訟を提起することができない場合があります。
このような場合には、「成年後見人」を選任する必要があります。
成年後見人とは、精神病などの障害により事理弁識能力(自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識する能力)を欠いている人について、家庭裁判所が本人の権利を守るために選任する人のことをいい、本人の財産の管理等を行います。
配偶者の精神病が重篤な場合等、判断能力を欠いていると考えられる場合には、まずは成年後見人の選任を家庭裁判所に申立てしましょう。
なお、成年後見人に選任されるのは、本人の親族や弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職であることが一般的です。
申立て方法や必要書類は、家庭裁判所のホームページで確認できます。
配偶者への慰謝料請求は可能?
配偶者の精神病を理由に離婚する場合、慰謝料をもらえるか気になる方もいると思います。
ただし、基本的には配偶者の精神病を理由に離婚する場合に、相手から慰謝料をもらえる可能性は低いでしょう。
慰謝料は、相手方の不法行為(故意又は過失によって他人の権利を侵害する行為)によって精神的苦痛を受けた場合に請求が認められますが、精神病にかかってしまったことをもって、故意又は過失による権利の侵害があったとはいえないと考えられます。
なお、他に暴力や不貞行為等があった場合には、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
まとめ
当事務所では、離婚に関するご相談に注力しており、これまでに多数のご相談を受けてきました。
離婚事件といっても、ご相談者様の状況は様々であるからこそ、ご状況に応じた最適なアドバイスをできるよう常に心がけております。
配偶者との離婚に関する問題でお悩みの方は、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。