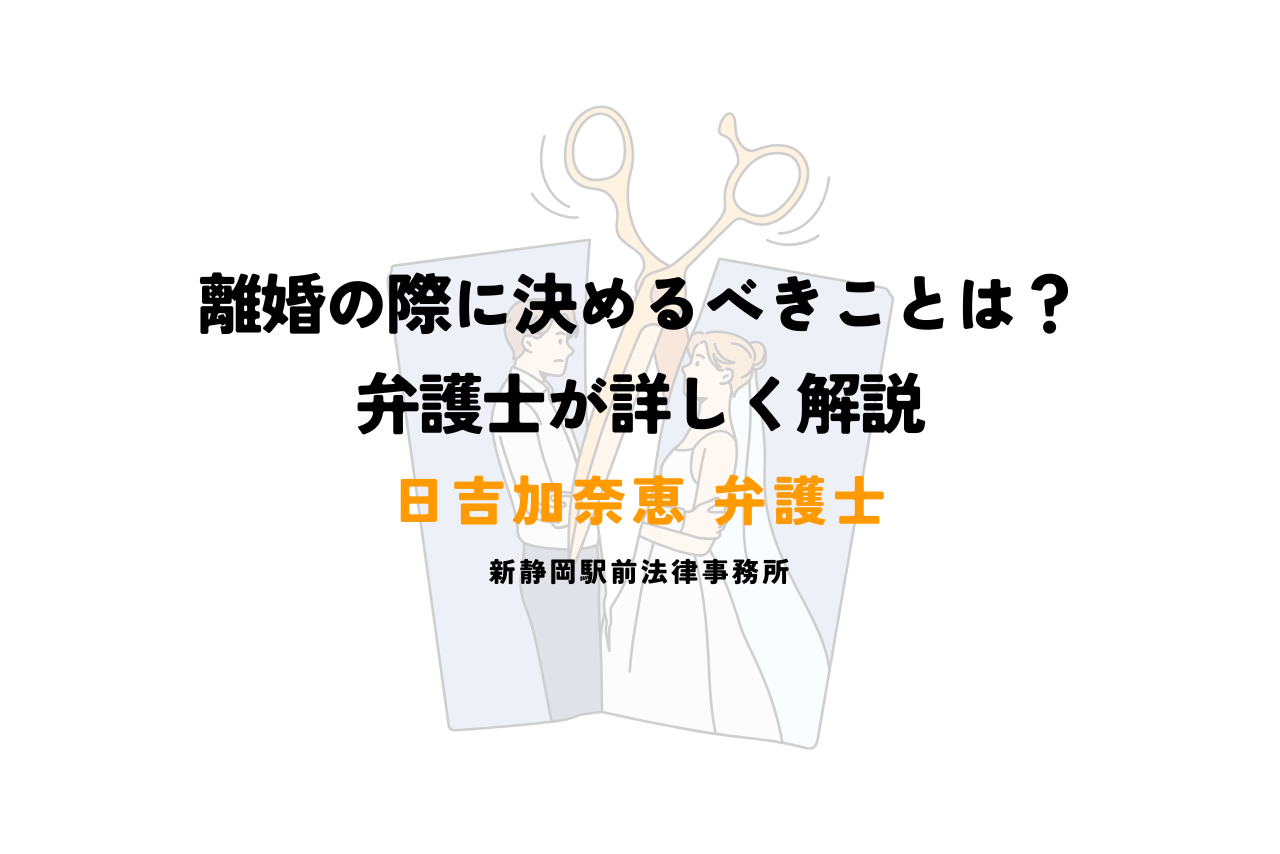離婚は、離婚届を提出すればすることができます。
この際、財産分与や慰謝料などの条件は、特に決めなくても離婚届は提出できますが、きちんと条件を決めないと、本来もらえるべきお金がもらえない、離婚後の生活が安定しないなどの不利益を被ってしまう可能性があります。
そこで本記事では、離婚をする際に決めておいた方がよい条件について解説します。
離婚で決めるべきこと
離婚の際に決めておいておいた方がよいことは、主に以下の6つです。
なお、お子さんがいない場合には、①財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割決について決めておくとよいでしょう。
①財産分与
②親権
③養育費
④面会交流
⑤慰謝料
⑥年金分割
①財産分与
財産分与とは、夫婦の婚姻期間中に共同で築き上げた財産を、それぞれ尾の貢献度に応じて分けることをいいます。
民法第768条1項に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定められているとおり、法律上も認められている権利です。
婚姻期間中に貯まった財産については、原則として夫婦が等しく貢献したと考えられることから、実務上は2分の1ずつ財産を分けることがほとんどです(お互いが合意すれば、それ以外の割合で分与することも可能です)。
対象となる主な財産は、現金や預貯金、株や有価証券、不動産、積立式の生命保険、退職金、企業年金、自動車などです。
お互いの名義の財産をそれぞれリスト化し、どの財産をどう分けるかを決めるようにしましょう。
なお、財産分与の基礎知識については、以下のコラムで解説しています。
②親権
お子さんがいる場合、どちらが親権者となるかは、離婚の際に必ず決める必要があります。
他の離婚条件と異なり、親権が決まっていない場合には、離婚をすることができません。
なお、民法改正により、2026年5月までには、共同親権の制度が開始されます。
共同親権の制度が開始されてからは、共同親権とするのか、単独親権とするのか(単独親権とした場合はどちらが親権者となるのか)を決めることとなります。
③養育費
お子さんがいる場合には、お子さんの養育費についても取り決めをするとよいでしょう。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用をいい、子どもと一緒に暮らして子どもの監護をする親(監護親)に、もう一方の親(非監護親)から支払われます。
養育費の額は、お子さんの数や双方の年収を元に、裁判所の作成した算定表で決めることが一般的です。
算定表を参考に、養育費は月額いくらとするのか、いつまで支払ってもらうのか、特別の出費(大学への進学やお子さんの入院等)の負担はどうするのかといったことを決めるとよいでしょう。
養育費の決め方については、以下のコラムでも解説しています。
④面会交流
面会交流とは、非監護親が子どもと直接会ったり、面会以外の方法(電話、手紙、メール等)でやり取りをすることをいいます。
離婚したとしても、子どもにとって親であることには変わりなく、子の健全な成長のためには面会交流を実施することが重要であると考えられているので、虐待をしていて子どもに会わせるのが適当ではない等の事情がない場合には、面会交流についても定めるとよいでしょう。
面会交流については、頻度(月1回や週1回等)、日時(第1日曜日の9時から15時等)、引渡場所、宿泊を伴う面会交流をするのか等の条件を決めておくとよいでしょう。
面会交流については、以下のコラムでも解説しています。
⑤慰謝料
相手の不法行為により離婚をすることになった場合には、相手に対して慰謝料を請求できます。
例えば、相手が不貞行為(不倫)をしていたので離婚することとなった、相手からの暴力を理由に離婚をすることとなったという場合です。
離婚慰謝料の額は、夫婦の婚姻期間や子どもの有無、不法行為の回数や内容によって決まりますが、おおよその相場は50~300万円です。
なお、相手が合意さえすれば、相場と異なっても原則自由に金額を決定することができます。
慰謝料の支払いが生じる場合には、慰謝料の額の他、支払い方法(一括か分割か)、支払い時期についても決めておくとよいでしょう。
離婚の慰謝料を請求できる場合については、以下のコラムでも解説しています。
⑥年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金(標準報酬月額・標準賞与額)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことです。
夫婦が協議により年金分割を行う場合、分割の割合は、2分の1を上限として合意により決めることができます。
ただし、3号分割(平成20年5月1日以降に離婚をした場合で、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者であった方が、第3号被保険者期間における相手方の厚生年金を2分の1ずつ分割するよう請求することができる制度)による場合には、割合が2分の1となることから、実務上は2分の1と合意することがほとんどです。
なお、国民年金は年金分割の対象になりませんので、例えば、配偶者が自営業である場合(厚生年金納めていない場合)には年金分割をすることができないので注意が必要です。
年金分割の手続きなど詳細は、こちらのコラムでご確認ください。
離婚条件はいつ決めるとよい?
前述したとおり、親権以外の離婚条件は決めていなくても離婚届を提出できます。
少しでも早く離婚したい場合には、まずは離婚届を提出したうえで、その後に財産分与や慰謝料、養育費について協議をすることも可能です。
ただし、財産分与や年金分割は離婚が成立してから2年以内に請求しないと権利が消滅してしまいますし、養育費は、請求をした時からしか支払を求められないため、請求するのが遅くなると、その分もらえる額が減ってしまうことになります。
また、相手が離婚を求めている場合には、離婚に応じてしまった後に条件交渉をするのが難しい場合もあるでしょう。
これらの事情を踏まえ、離婚成立前に条件を決めるべきか否かを慎重に検討する必要があります。
離婚条件が決まったら
離婚条件について相手と合意ができた場合には、必ず合意できた条件を書面に記載するようにしましょう(この書面を「離婚協議書」といいます)。
書面がないと、相手から「そんな合意はしていない」などと言われてしまうリスクがあります。
こちらが金銭の支払義務を負う場合であっても、支払うべき義務がある金銭とその額をきちんと残しておかないと、追加で請求を受けてしまうことにもなりかねません。
また、養育費の支払いは通常お子さんが成人するまで続くため、お子さんの年齢によっては支払い期間が長期間に渡ることもあります。
このような場合には、公正証書を作成することを検討しましょう。
公正証書に、「支払を怠った場合には強制執行に服する」という趣旨の文言(強制執行認諾文言といいます)を入れることで、支払いが滞った場合に裁判を経ずにすぐ強制執行(預貯金や給与の差押えなど)をすることができます。
離婚協議書の書き方はこちらのコラムでご確認ください。
まとめ
これまで解説してきたように、離婚をする際には多くの決め事が必要です。
相手方の提示してきた条件が良い条件であるかどうか、ご自身のみでは判断がつかない場合もあるでしょう。
当事務所では、これまでに多くの離婚に関するご相談をお受けしており、ご相談者様の状況に合わせた最適なアドバイスをさせていただきますので、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。