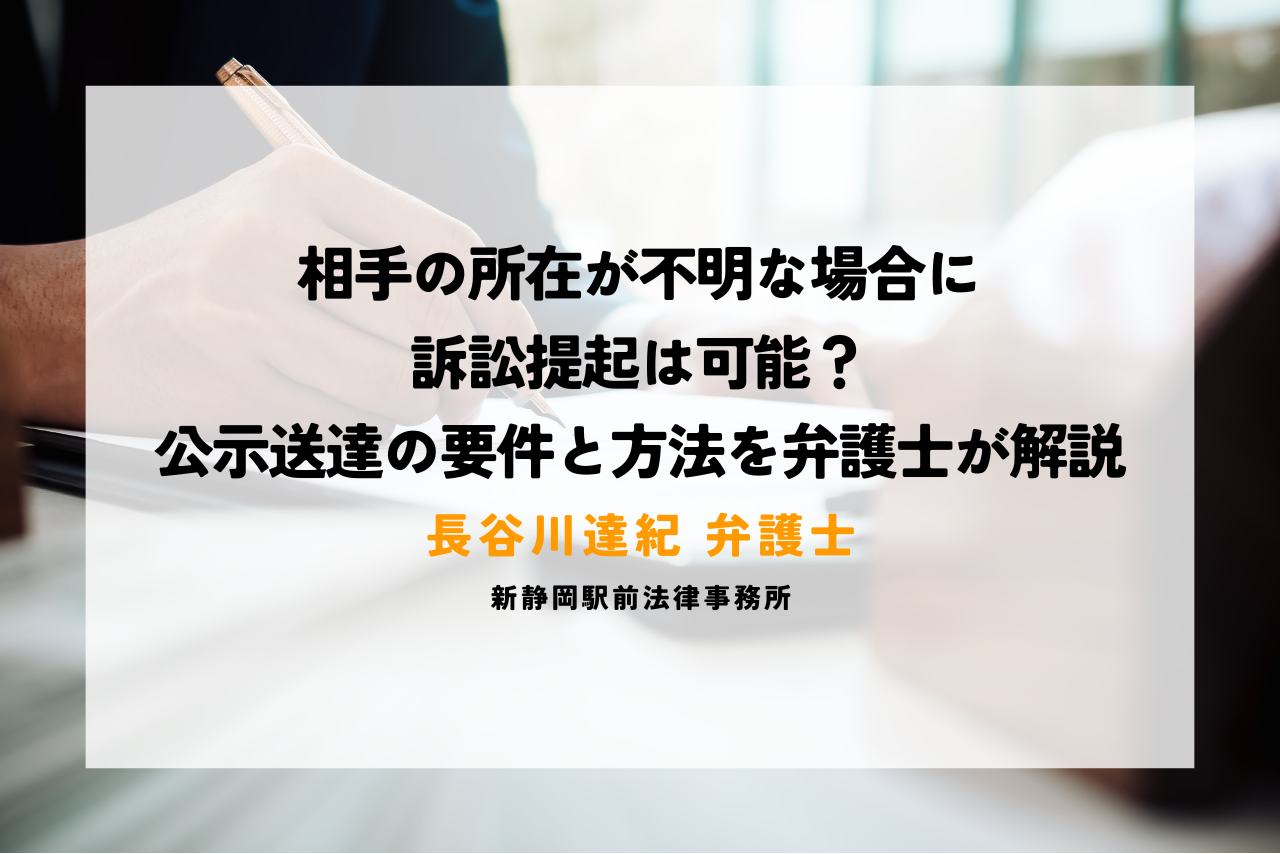相手方の住居所が不明な場合、公示送達という方法により訴訟手続を進められることがあります。
本稿では、公示送達の要件と方法を解説いたします。
目次
1. 公示送達とは
「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、又は、相手方の住居所が不明であるために、意思表示を到達させることができない場合に、意思表示が到達したものとみなす手続をいいます(民事訴訟法第110条)。
訴訟が係属(裁判を開始)するためには、裁判所が相手方に訴状を送達する必要があります。
しかし、相手方の居所が不明の場合、訴状を送達することができず、訴訟を開始することができません。
このような場合に、公示送達制度を利用することで、相手方に訴状を送達したとみなすことができます。
実務上は、貸金返還請求や建物明渡請求などの一般民事事件で、相手方に書面を送付しても「あてどころ尋ねあたりません」(送付先の住所地に相手方が居住していないこと)を理由に書面が返送されてしまい、その他調査を行っても住居所が判明しなかった場合に利用されることが多いです。
また、配偶者が自宅を出てしまい、長年行方不明で連絡も取れないという場合に、公示送達の手続を利用して離婚訴訟を提起することがあります。
2. 公示送達の要件
①当事者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合
相手方の住居所や勤務先が不明であることが要件です。
実務上は、住民票・戸籍の附票の取得、携帯電話番号への架電、携帯電話番号・自動車のナンバーからの弁護士会照会、親族・知り合いへの事情聴取、不動産管理会社への事情聴取、現地調査などの調査を尽くしても、相手方の住居所及び勤務先などを知ることができなかった場合に認められます。
②書留郵便等に付する送達をすることができない場合
訴状の送達は、次の順番に従って実施されます。
これらの送達が不奏功の場合にはじめて公示送達が認められます。
交付送達
相手方に訴状を交付する送達方法です(民事訴訟法第101条)。
原則として、相手方の住所・居所・営業所・事務所に対し郵送する方法で行います。
なお、日本国内に住所等を有することがあきらかでない者に対する送達は、出会った場所に送達することもできます(民事訴訟法第105条)。
補充送達・差置送達
送達すべき場所において相手方に出会わないときは、その使用人その他の従業者または同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができます。
また、相手方や上記の者が正当な理由なく書類の受領を拒んだときは、その書類を送達すべき場所に差し置くことができます(民事訴訟法第106条)。
書留郵便等に付する送達
裁判所書記官が書留郵便等により訴状を発送した時点で送達の効果が生じる送達方法です(民事訴訟法第107条)。
相手方の住居所等が知れている場合には、この方法により送達を完了することができます。
③外国においてすべき送達について、民事訴訟法第108条の規定による送達ができない場合
訴状を外国に送達する場合、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託して行いますが(民事訴訟法第108条)、これができない場合、又は、できないと認めるべき場合には、公示送達が認められます。
④民事訴訟法第108条の規定により、外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても、その送達を証する書面の送付がない場合
上記外国送達の場合に、外国の管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても、送達を証明する書面が送付されない場合には、公示送達が認められます。
3. 公示送達の方法
訴状の公示送達は、原則として、当事者が申し立てることにより行います(裁判所の職権で行うこともできますが、実務上は当事者の申立てによる場合がほとんどです)。
前述した書留郵便等に付する送達を行い、これが不奏功になると、相手方の住所の調査をするのが一般的です。
調査の具体的な内容は、前述した住民票・戸籍の附票の取得、携帯電話番号への架電、携帯電話番号・自動車のナンバーからの弁護士会照会、親族・知り合いへの事情聴取、不動産管理会社への事情聴取、現地調査などです。
現地調査は、相手方の最後の住所地や住民票上の住所地に赴き、呼び鈴を押したりノックをしたりして反応があるか、電気・水道・ガスメーターが動いているか、郵便物が溜まっているか、カーテンがかかっているなどの生活感はあるか、(夜に)部屋の電気は点いているか、近隣住民への聴取などを行い、写真を撮影するなどして資料化する必要があります。
調査を終えたら、その内容を調査報告書にまとめ、資料を添付して、裁判所に公示送達の申立てを行います(公示送達の申立書に調査報告書と資料を添付する方法で行います)。
調査が不足している場合、裁判所から調査の補充の指示がありますので、指示に従いましょう。
4. 公示送達の手続
公示送達の申立てが認められると、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示します(民事訴訟法第111条)。
掲示を始めた日から2週間が経過すると、公示送達の効力が生じます(民事訴訟法第112条1項本文)。
2回目以降の公示送達(判決等の公示送達)は、裁判所書記官の職権で行いますので、別途申立ては必要ありません。
また、2回目以降の公示送達の場合、掲示開始の翌日から効力が生じます(同項但書)。
5. 公示送達完了後の流れ
公示送達が完了すると、裁判所において、第1回口頭弁論期日が行われます。
原告(訴訟を提起した者)は同期日に出頭する必要があります。
公示送達の場合、相手方が期日に出頭してきたり、答弁書(訴状に対する反論書面)を提出してくることはほとんどありませんので、ほぼすべてのケースにおいて、第1回期日で弁論終結(主張や証拠の提出が終了)となり、判決期日が指定されます。
判決が言い渡されると、裁判所から判決書が送られてきます。
相手方への判決の送達は公示送達になりますので、掲示がなされた翌日から2週間以内に相手方から控訴の申立てがなされなければ、判決が確定し、裁判は終了となります(なお、公示送達の場合、控訴がなされるケースはほとんどありません)。
6. まとめ
公示送達の申立てが認められるためには、相手方の調査が必要になり、特に住民票・戸籍の附票の取得や弁護士会照会手続はご自身での対応が難しい又はできない手続になります。
また、実務上実施されている現地調査の方法も複雑であり、ご自身での対応が難しい場合が多いです。
さらに、調査報告書の作成など、書面や資料の作成も必要となります。
そのため、公示送達の申立てを検討されている場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
当事務所は、公示送達を多数経験しており、その知識と経験は豊富です。
当事務所への相談・依頼を検討されている方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。