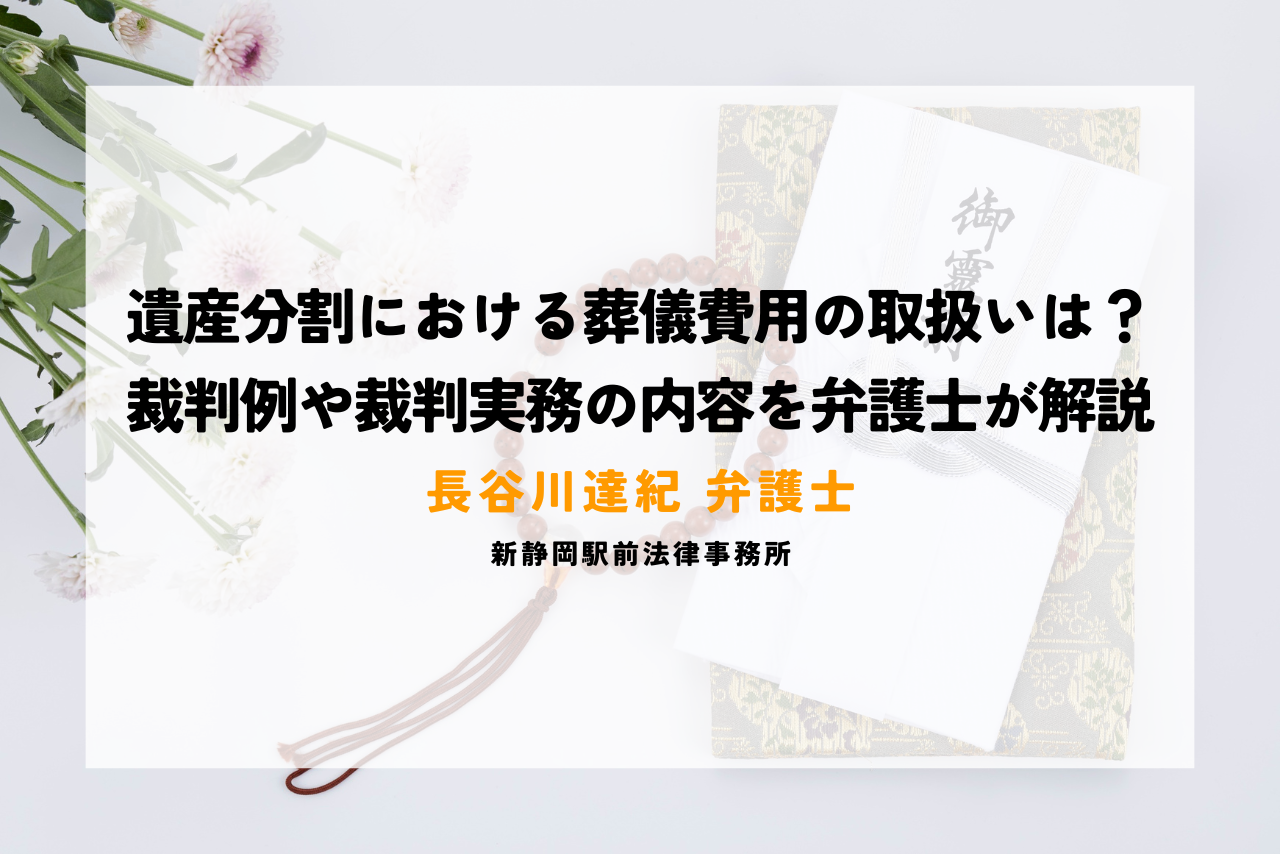遺産分割において、被相続人(亡くなった方)の葬儀費用の負担が問題となることは多いです。
本稿では、遺産分割における葬儀費用の取扱いについて、解説いたします。
目次
1. 遺産分割とは
「遺産分割」とは、被相続人の財産を相続人間で分ける手続のことをいいます。
遺産分割手続が完了しないと、被相続人の財産を受領ないし処分することができないため、相続人が複数いる場合、遺産分割は必須になります。
遺産分割については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 葬儀費用とは
一般的に、葬儀費用とは、以下の費用のことをいいます。
- 施設利用料(通夜、告別式、葬儀、火葬会場等)
- 葬祭用具費(棺、納棺用品、祭壇、霊柩車、花輪、位牌、遺影等)
- 火葬費用
- 寺院へのお布施(読経料、戒名料等)
- 埋葬、納骨費用
- 仏壇、墓地、墓石の費用
- 香典返し
- 役所等への届出費用
- 飲食代
3. 葬儀費用は誰が負担すべき?
葬儀費用は遺産分割の対象外
遺産分割において、葬儀費用の負担割合も合意したいという方が多いですが、原則として、葬儀費用は遺産分割の対象にならないと考えられています。
葬儀費用を誰の負担とすべきかについては、裁判例が分かれておりますが、裁判実務上は、主宰者や祭祀承継者が負担すべきとする考え方(葬儀の喪主が負担すべきという「喪主負担説」)が主流です(東京地判昭和61年1月28日家月39巻8号48頁)。
喪主負担説の場合、香典は喪主に対する贈与と考えられるため、喪主がこれを取得することになります。
なお、その他の考え方としては、法定相続人が法定相続分に応じて負担すべきという考え方(福岡高決昭和40年5月6日家月17巻10号109頁、福井家審昭和40年8月17日家月18巻1号87頁、長崎家佐世保支審昭和40年8月21日家月18巻5号66頁、神戸家姫路支審昭和43年2月29日家月20巻8号88頁)、相続財産に含まれるという考え方(大阪家堺支審昭和35年8月31日家月14巻12号128頁、東京家審昭和37年9月25日家月14巻12号116頁、高松高決昭和38年3月15日家月15巻6号54頁)、慣習や条理によって決定すべきという考え方(甲府地判昭和31年5月29日下民7巻5号1378頁、仙台家古川支審昭和38年5月1日家月15巻8号106頁、神戸家明石支審昭和40年2月6日家月17巻8号48頁)等があります。
被相続人が契約していた場合
例外的に、被相続人が葬儀の契約をしていた場合には、葬儀費用が相続財産に含まれるとされています。
法定相続人は、被相続人の権利義務の一切を承継することから(民法第896条)、被相続人が契約した葬儀の契約がある場合、その契約に基づく権利義務も承継するためです。
相続人間で合意が成立している場合
葬儀費用の負担について、法定相続人間で合意ができる場合には、合意に基づく負担を行うことが可能です。
遺産分割協議や遺産分割調停は、法定相続人の合意成立を目指す手続ですので、これらの手続においては、よく葬儀費用の分担について協議がなされます。
合意が成立する内容としては、相続財産から葬儀費用を支出し、残った相続財産を分割するというものです。
また、香典がある場合には、葬儀費用から香典相当額を控除し、その残額を相続財産から支出することが多いです。
4. 注意点
原則として、葬儀費用は、遺産分割の対象外ではありますが、実務上は紛争となることが多いです。
特に、葬儀費用が高額である場合には、支出の事実や金額の相当性が問題となるケースが多いです。
喪主を務める方は、後の紛争を防止するために、領収書や明細等の客観的資料を保管しておきましょう。
5. まとめ
遺産分割において、葬儀費用が問題となることは非常に多いです。
葬儀費用でトラブルになっている場合、まずは弁護士に相談し、今後の方針等を確認してみると良いでしょう。
当事務所は、遺産分割を含む相続案件に注力しております。
相続に関するご相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。