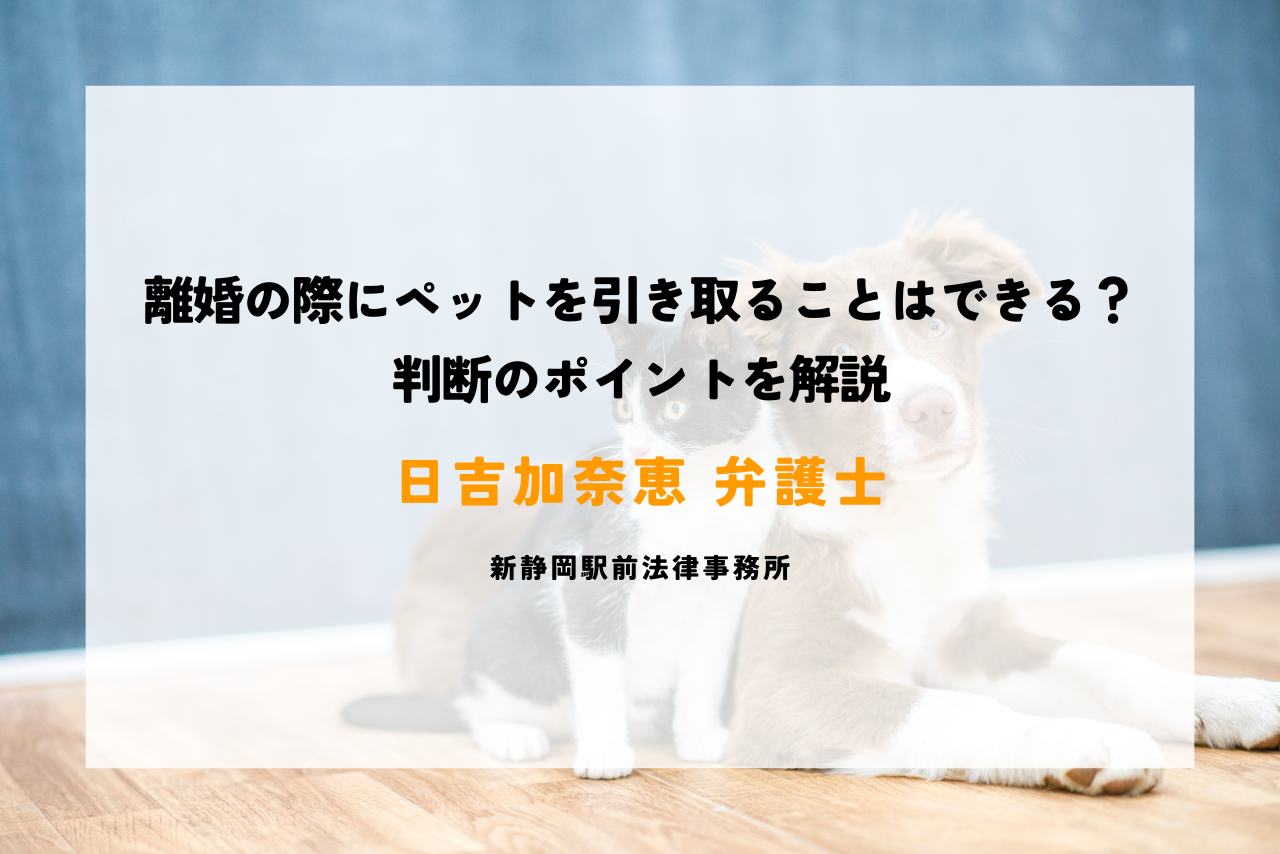ペットを飼っている夫婦が離婚する場合、どちらがペットを引き取ることができるのでしょうか。
お互いにとって家族のような存在であり、なかなかどちらがペットを引き取るかについて合意ができない場合も多いでしょう。
そこで、本記事では、離婚の際、ペットに関して問題となる点を解説します。
目次
1. 離婚の際、ペットはどちらが引き取る?
ペットを飼っている方にとっては、ペットは家族同然だと思いますが、法律上は、ペットは、「物」に該当します。
そこで、ペットをどちらが引き取るかについても、ペットが物であることを前提に決められることになります。
結婚前にどちらかがペットを飼っていた場合
結婚前にどちらかがペットを飼っていた場合、ペットはその配偶者の特有財産(その人固有の財産)に該当します。
特有財産は、離婚の際、財産分与(夫婦の共有財産を離婚にあたって分与すること)の対象となりませんので、元々ペットを飼っていた人の財産として、その人が引き取る(=ペットの所有権を取得する)のが一般的です。
ただし、相手がペットを譲ると言っている場合など、相手と合意ができるのであれば、ペットを飼っていなかった側が引き取ることも可能です。
結婚後にペットを飼い始めた場合
この場合には、ペットは財産分与の対象となります。
結婚後に購入した不動産や家具などと同様に、どちらが取得するのかを話し合いで決めることとなります。
理論上は、厳密には、ペットの価格(価値)を算定し、引き取る側がその価格の2分の1を相手に払うということになりますが、裁判実務上は、ペットなど価値を算定するのが難しい物や、購入してから年数が経過した家具などについては、引き取り手だけを決めることもよくあります。
なお、財産分与については、こちらの記事で詳しく解説しています。
2. ペットをどちらが引き取るか決める方法
上記のとおり、結婚後に飼い始めたペットについては、財産分与の対象として、どちらが引き取るかを話し合いにて決めることになります。
話し合いで合意できた場合には、他の財産と同様、離婚協議書にどちらが取得するかを明記すると後々争いになることを防ぐことにつながるでしょう。
離婚協議書の記載方法や記載例については、こちらのコラムで解説しています。
相手との話し合いでも決まらない場合には、離婚調停を申し立てることを検討しましょう。
調停とは、裁判官(又は調停官)1名と調停委員2名の仲介の元、話し合いにて紛争を解決するための手続です。
離婚調停では、財産分与以外にも、子どもがいる場合の親権や、養育費、慰謝料など離婚にあたって決めることが必要な様々な条件を話合うことができます。
各種条件と共に、どちらがペットを引き取るかを調停で話し合っていきましょう。
離婚調停の詳細な流れについては、以下のコラムをご参照ください。
離婚調停でも合意できなかった場合には、離婚訴訟を提起することが考えられます。
訴訟では、調停とは異なり裁判官が離婚の条件について一定の判断を下すことになります。
離婚訴訟については、以下のコラムで詳しく解説しています。
3. ペットの引きとり手を決めるためのポイント
ペットの引きとりをどちらが行うかを決める際、ポイントとなる点は以下のとおりです。
①ペットがどちらに懐いているか
例えば仕事の都合上、ペットがどちらか一方と過ごす時間の方が圧倒的に多く、ペットがその配偶者に懐いている場合には、その人がペットを引き取る方が適切なことが多いでしょう。
ペットにとっても、より懐いている方に引き取られた方が、安心・安全な生活ができる可能性が高いといえます。
②ペットの世話を主にどちらがしていたか
ペットの世話(散歩や食事、排せつの世話など)をどちらが主にしていたかという点も重要なポイントです。
現在まで継続してペットの世話をしていたのであれば、離婚後も継続してペットの世話を適切にできると判断される可能性が高いといえます。
他方で、例えば婚姻中、ほぼペットの世話をしていなかったのであれば、離婚していきなりペットの世話をするのは難易度が高いと考えられるでしょう。
③離婚後の飼育環境
例えば、ペット飼育可能なマンションに、離婚後すぐに居住できない場合には、ペットを引き取ることが難しいと判断されるでしょう。
その他にも、離婚後に実家に帰る場合には、同居家族にペットアレルギーの人がいないかなども考慮されます。
④経済状況
ペットの飼育には、餌代や予防接種の費用、医療費など、それなりに費用がかかります。
特にペットの医療費は、保険適用がないため高額になることも多いです。
ペットをきちんと飼育できるだけの経済力があるかについても、判断要素となるでしょう。
4. 離婚後の面会や飼育費について
離婚後にペットと面会できる?
離婚をする際に相手がペットを引き取ることに同意した場合であっても、ペットと一切会えないのはとてもつらいでしょう。
これまで述べてきたとおり、ペットは、法律上は「物」に該当するので、法律上は、いわゆる面会交流のように、ペットに定期的に会わせることを求めることのできる権利はありません。
ただし、相手が同意さえしてくれれば、当事者間でペットとの面会について決めることも可能です。
例えば、引き取ることは相手に譲る代わりに、面会を定期的にさせて欲しいと求めると言った交渉をすることを検討しましょう。
この場合には、離婚協議書に面会の条件を詳細に書いておくとよいでしょう。
離婚後に相手にペットの飼育費を請求できる?
ペットを引き取ることを決めた方の中には、相手にペットの飼育費を請求できるかが気になる方もいるでしょう。
こちらについても、特に法律上、相手に飼育費を請求できる権利はありませんが、相手と合意さえできれば請求することは可能でしょう。
合意ができた場合には、離婚協議書に月いくら支払ってもらうのか、いつまでに支払ってもらうのかなどを記載しておくとよいでしょう。
また、長期的に支払ってもらうことを約束した場合などには、必要に応じて、支払いが滞った場合には強制執行が可能である旨の文言(強制執行認諾文言といいます)を含んだ公正証書を作成することも検討しましょう。
5. まとめ
離婚をする際、ペットと離れたくないと考える方は多いです。
お互い感情的になってしまい話し合いが進まない場合には、弁護士を通じて協議をすることで、協議がスムーズに進む場合もあるでしょう。
また、弁護士に依頼をすれば、ペットに関することだけではなく、離婚に関するあらゆるお悩みを相談することも可能ですので、お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。