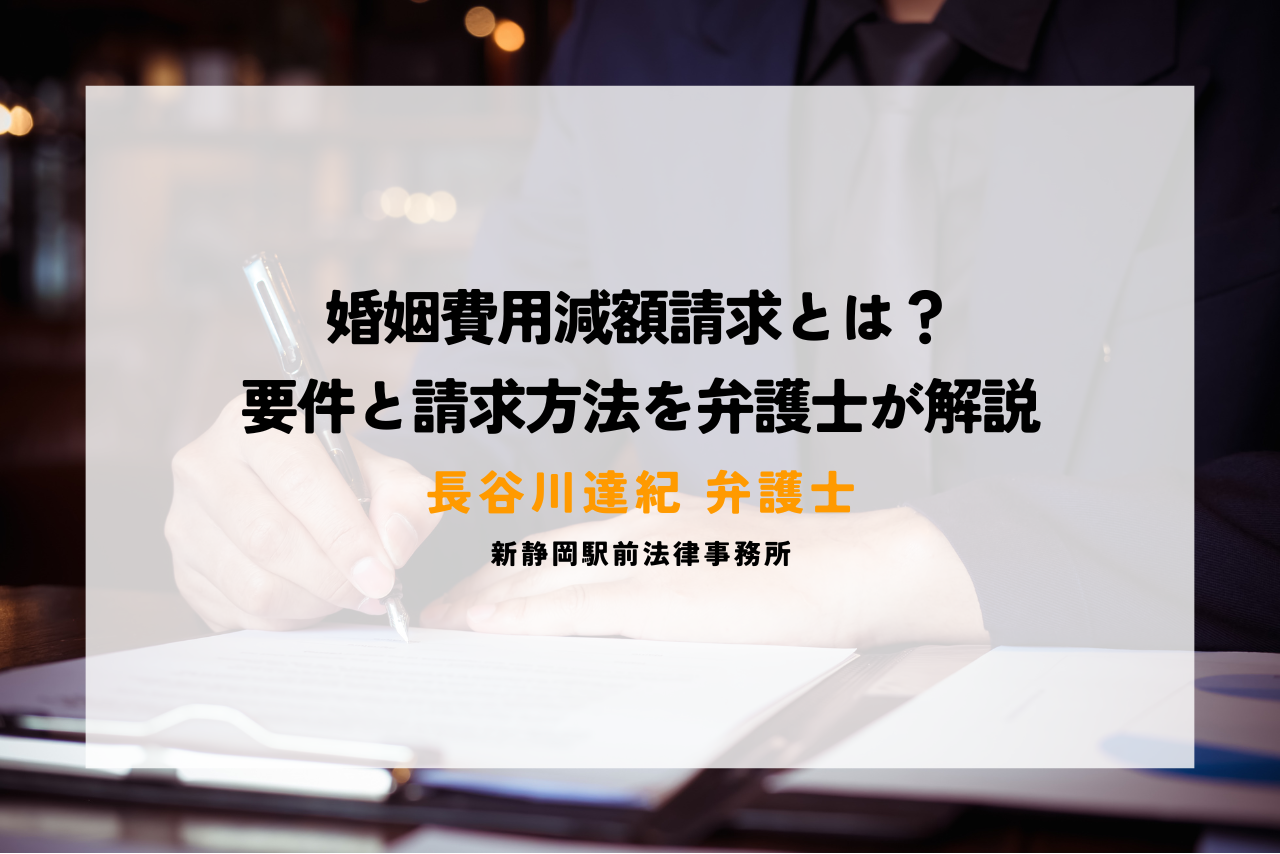婚姻費用について合意が成立した後、又は、裁判所の審判や決定がなされた後、当事者の一方又は双方の事情が変わった場合、婚姻費用の減額を請求できる場合があります。
本稿では、婚姻費用の減額が認められる要件と減額請求の方法を解説いたします。
目次
1. 婚姻費用とは
民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とされています(民法第760条)。
これを婚姻費用の分担といいます。
具体的には、夫婦の生活レベルが同等になるように、夫婦の一方が配偶者に婚姻費用として、毎月一定の金員を支払う形にする方法が一般的です。
婚姻費用の基礎知識やについては、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 婚姻費用減額の要件
民法は、「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる」と定めています(民法第880条)。
上記規定は、婚姻費用の減額について直接定めた条項ではありませんが、裁判実務上及び学説上は、上記規定を婚姻費用にも類推適用することで婚姻費用の減額請求が可能であると解されています。
上記規定に基づき、「協議又は審判があった後事情に変更を生じたとき」には、婚姻費用の減額請求が可能ということになります。
3. 婚姻費用の減額が可能なケース
どのようなケースであれば、「事情に変更を生じたとき」という婚姻費用減額の要件を満たすのでしょうか。
以下、裁判実務において減額請求が認められている一般的なケースを紹介いたします。
義務者の収入の減少
義務者(婚姻費用を支払っている側)の収入が減少した場合、婚姻費用の減額が認められる可能性があります。
ただし、単に収入が減ったというだけで養育費の減額が認められるわけではありません。
例えば、会社員として年1000万円の収入を得ている方が自ら会社を立ち上げたいという理由で独立開業し年収が500万円に減少したという場合、義務者自らの都合で収入を減少させたものとして、婚姻費用の減額が認められない可能性が高いです。
また、部署の異動で残業代が減って収入が約50万円減少したという場合や今年は業績賞与が支給されず年収が約100万円減少したというような、予見可能な事情変更かつ収入の減額幅の場合も、婚姻費用の減額が認められないことが多いです。
一方で、収入が減少するやむを得ない事情があるような場合、例えば、大病を患い退職を余儀なくされ収入がなくなってしまった場合やリストラされ転職したため収入が減少したような場合には、婚姻費用の減額が認められる可能性が高いです。
権利者の収入の増加
権利者(婚姻費用の支払を受けている側)の収入が増加した場合、養育費の減額が認められる可能性があります。
また、婚姻費用の合意が成立した当時、権利者が監護していた子が幼く、働くことができなかったため、収入をゼロとして婚姻費用を計算したが、合意時から時間が経過し、子の年齢が上がったことで、働くことができるようになった場合には、実際に働いていないとしても、働くことは可能として一定の収入があるとみなすことで婚姻費用の減額が認められる可能性があります(「潜在的可動能力」といいます)。
子の扶養が必要なくなった場合
権利者が子を監護している場合、監護していた子の扶養が必要なくなった場合には、子の生活費分の婚姻費用を減額することができます。
例えば、婚姻費用の合意が成立した当時は子が大学に通っていたが、大学を卒業し、就職した場合には、婚姻費用の減額が認められます。
また、婚姻費用の合意成立時は母が子を監護していたが、後日父が子を監護するようになった場合も、婚姻費用の減額が認められます。
実務上多いケースとしては、母が静岡の実家で子と一緒に生活していたが、子が東京の大学に進学することになり、東京に住んでいる父と同居することになったというような場合です。
その他、父が母に対し、子の監護者指定・子の引渡しの審判を申し立て、父の請求が認められて監護者が変更になったというケースもあります。
子にかかる費用の支出がなくなった場合
婚姻費用の金額を決定するに当たっては、子の習い事や子の学費(私立学校や大学等)を加算することがあります。
例えば、子が塾に通っているため、塾代月額2万円を夫婦が2分の1ずつ負担することとし、婚姻費用月額に1万円を加算するということがあります。
このように、子にかかる費用を加算している場合に、例えば、子が習い事を辞めた、大学を中退したといった事情が生じた時には、子にかかる費用の加算分の婚姻費用を減額することができます。
4. 婚姻費用減額の始期
婚姻費用の減額は、婚姻費用の減額を請求した時から効果が生じます。
事情の変更が生じた時から減額が認められるものではないので、注意が必要です。
婚姻費用の減額を求める場合には、必ず内容証明郵便やメール等記録に残る形で減額請求をするか、後述する婚姻費用減額調停を申し立てるなどの対応を取るようにしましょう。
5. 婚姻費用減額請求の方法
協議
婚姻費用の減額請求は、裁判外で行うことも可能です。
配偶者と協議を行い、金額や始期について合意に至った場合、後の紛争が生じないようにするために、合意した内容を書面等に残すようにしましょう。
調停
裁判外での協議がまとまらない場合、又は、裁判外で協議を行うことが難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
調停とは、裁判所を通じた話合いのことです。
調停委員会(裁判官1名と調停委員2名の合計3名)が間に入り、話合いの仲介をしてくれますので、裁判外の協議よりも解決力が高い制度といえます。
もっとも、あくまで「話合い」ですので、双方の合意が成立しない限り、調停で解決することはできません。
婚姻費用減額調停の管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
婚姻費用減額調停の申立書は、裁判所のホームページに書式が掲載されていますので、ご参照ください。
また、調停の申立てに当たっては、1200円の収入印紙を納める必要があります。
収入印紙は申立書の正本に貼付する方法で納めます。
さらに、裁判所が書類を当事者に送付することが必要となるため、郵券(郵便切手)を納める必要もあります。
郵券の金額や種類の内訳は裁判所ごとに異なりますので、事前に管轄の裁判所に確認するようにしましょう。
審判
調停でも話合いがまとまらない場合、「審判」という手続に移行します。
「審判」とは、裁判官が、当事者双方の主張や資料を精査した上で、婚姻費用の減額を認めるか否か、認める場合いくら減額するかを決める手続です。
審判の内容に不服がある場合には、審判書の受領から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告をすることができます。
即時抗告が受理されると、高等裁判所での審理が開始され、高等裁判所の裁判官が決定を下すことになります。
6. 注意点
離婚や婚姻費用の相談において、「婚姻費用を減額する事情の変更が生じたため、その時から婚姻費用を減額して支払っている」という方がいらっしゃいます。
しかし、前述のとおり、婚姻費用減額の効果が生じるのは、婚姻費用減額を請求した時からになりますので、婚姻費用減額の事情変更が生じたとしても、一方的に婚姻費用を減額することはできません。
また、「婚姻費用の減額事由及び減額する旨を通知した時から婚姻費用を減額して支払っている」という方も散見されます。
しかし、配偶者との合意が成立していない段階では、婚姻費用の減額が確定しておらず、また、仮に減額が認められることが確実であったとしても減額される金額が確定していないので、配偶者の同意なく婚姻費用を減額してしまうと、強制執行(給与や預貯金の差押え等)をされてしまうリスクがあります。
したがって、婚姻費用の減額につき、配偶者との合意が成立若しくは裁判所の審判ないし決定が確定するまでは、従前どおりの婚姻費用を支払うようにしましょう。
なお、婚姻費用の減額が確定すれば、婚姻費用減額の始期(婚姻費用減額の請求時)から支払った婚姻費用と減額後の婚姻費用の差額(過払分)を、返金又は将来分の婚姻費用から差し引く方法で清算をすることが可能です。
7. まとめ
婚姻費用減額請求は、事情の変更が認められるか、減額できる金額及びその計算方法などの法律論、調停や審判等の裁判手続などの専門的な知識が必要となる場合があるので、婚姻費用減額請求を検討されている方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所は、婚姻費用減額請求を含む離婚案件に注力しており、婚姻費用減額請求の知識と経験は豊富です。
当事務所への相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。