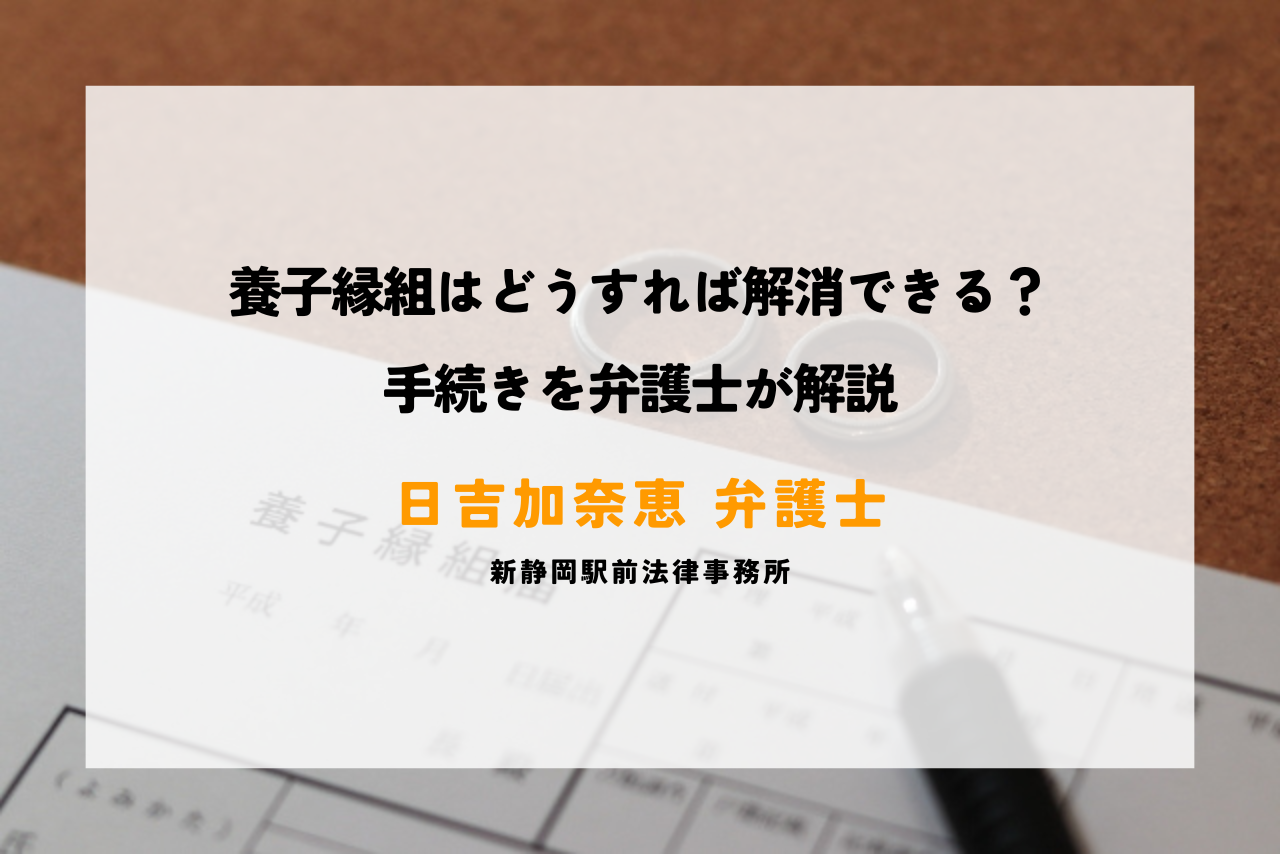結婚相手に前の夫との子どもがいた場合、結婚するにあたり養子縁組をすることもあるでしょう。
その相手と離婚をしたとしても、親子関係は当然には解消されないため、養子縁組の解消手続きをする必要があります。
そこで、本記事では、離縁の手続きや注意点について解説します。
目次
1. 養子縁組とは
養子縁組とは、養親と養親との間に法律上の親子関係を作りだす制度です。
養親と養子の合意(養子が15歳未満の場合には、養子の親権者などの法定代理人)をしたうえで、市区町村の役所へ届け出れば、養子縁組の効果が生じます。
養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じます(民法第809条)。
養親と養子は法律上親子となりますので、養親は養子を扶養する義務を負いますし、養子は養親の相続人となります。
2. 養子縁組の解消(離縁)とは
養子縁組の解消とは、養子縁組によって生じた法律上の親子関係を解消するための手続きです。
離縁をすることにより、養親と養子との法律上の親子関係は解消されます。
離縁をすると、養親の養子に対する扶養義務はなくなり、養子は養親の相続人ではなくなります。
3. 離縁しないとどうなる?
前述のとおり、結婚相手に連れ子がいて養子縁組をした場合、離婚しても当然には離縁されません。
離縁せずに放置していると、以下のようなデメリットが生じます。
①養育費を支払い続けなければならない
離縁をしないと、養子に対する扶養義務はなくなりませんので、元配偶者から養育費を請求された場合には、支払をしなければなりません。
仮に支払を拒んだとしても、調停や審判を経れば、最終的には支払い義務が認められれてしまいます。
②相続権が消滅しない
離縁をしなければ、法律上の親子関係が解消されない以上、養子は養親の相続人となります。
ご自身が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合でも、子どもの相続分は法律上同等ですから、その子と養子は子どもの相続分を同等の割合で分けなければなりません。
相続が発生した際に、実子と養子がどの遺産をどちらが取得するかなどについて、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、交流がない(少ない)実子と養子が円滑に協議をできる可能性は少なく、トラブルの元となり得るでしょう。
また、仮に養自身が養子の子より先に死亡してしまった場合には、養子の相続人となります。
この場合には、元配偶者との間で遺産分割協議をしなくてはなりません。
このように、離縁をしないことには大きなリスクが伴いますので、連れ子がいる配偶者と離婚する場合には、ご自身の状況を踏まえ、離縁すべきか否かをしっかりと確認するしょうにしましょう。
4. 離縁の方法
離縁の方法には、以下のいずれかの方法があります。
①協議離縁
養親と養子(養子が15歳未満の場合には、離縁後に養子の法定代理人となる者)が協議し、合意のうえで離縁届を提出すれば、離縁が成立します。
合意さえできれば届出のみで離縁できるため、相手が合意してくれるのであれば、最も簡便な方法です。
②調停離縁
調停とは、裁判官(又は調停官)と2名の調停委員で組織される調停委員会が当事者の話し合いを仲介する手続きです。
当事者同士での協議が難しくても、第三者を介して話し合いをすることにより、合意に至る場合があります。
ただし、あくまで当事者間の話し合いにより合意を目指す手続きのため、お互いに合意に至らなければ離縁はできません。
調停の申立先は、離縁を求める相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
なお、調停で合意が成立すると、調停調書という合意の内容が記載された書面が作成されます。
成立の日から10日以内に、調停調書の謄本(写し)と共に離縁届を役所に提出しましょう。
③審判離縁
調停においてほぼ合意が成立しているものの、合意にまで至っていないケースで、裁判所が離縁を認めるのが相当と認める場合には、裁判所が「調停に代わる審判」(家事事件手続第284条1項)をすることがあります。
審判がされた場合にも、調停の場合と同じような審判書が作成され、この審判書と離縁届を役所に提出することになります。
ただし、調停に代わる審判がされるのは、相手が離縁に合意しているのにも関わらず、突然家庭裁判所に来られなくなり、調停の成立手続きが行えないなど例外的なケースに限られます。
④裁判離縁
調停において相手が離縁に同意しない場合には、裁判によって離縁を認めてもらうほかありません。
離縁訴訟の申立先は、調停と同様、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判において離縁が認められるのは、以下の法律上の離縁理由があることが必要です(民法第814条1項)。
- 他の一方から悪意で遺棄されたとき(民法第814条1項1号)
- 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき(民法第814条1項2号)
- その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき(民法第814条1項3号)
再婚相手の連れ子と養子縁組をしており、再婚相手との離婚が成立している場合には、1号や2号の理由には該当しませんので、「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると主張することになります。
なお、必ずしも再婚相手との離婚のみで離縁が認められるわけではないことには注意が必要です。
5. 離縁をした場合戸籍はどうなる?
養子と離縁をした場合、養子の名字や戸籍はどのようになるのでしょうか。
①養子の名字
離縁をした場合、原則として、養子は養子縁組前の名字に戻ります。
ただし、養子縁組から7年が経過していた場合には、養子(又はその法定代理人)が離縁から3か月以内に届け出ることにより、養親の名字を名乗ることが可能となります。
②養子の戸籍
離縁をした場合、養子は養親の戸籍から抜けることになります。
この場合には、養子は、養子縁組前の戸籍に戻るか、新たな戸籍を編成するかを選択します。
③養親の戸籍
養親の戸籍からは、養子が除籍され、養子の欄には「除籍」という旨と、養子がいつ離縁されたかが記載されます。
6. まとめ
本記事では、養子との離縁について解説しました。
離縁の手続きを忘れてしまっていると、後々大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
相手が離縁に同意してくれない場合には、調停や裁判を行う必要が生じてしまいますが、ご自身のみでは対応が難しい場合もあるでしょう。
当事務所では、離婚に関する多くのご相談をお受けしており、離婚に関するお悩みをワンストップで対応することが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。