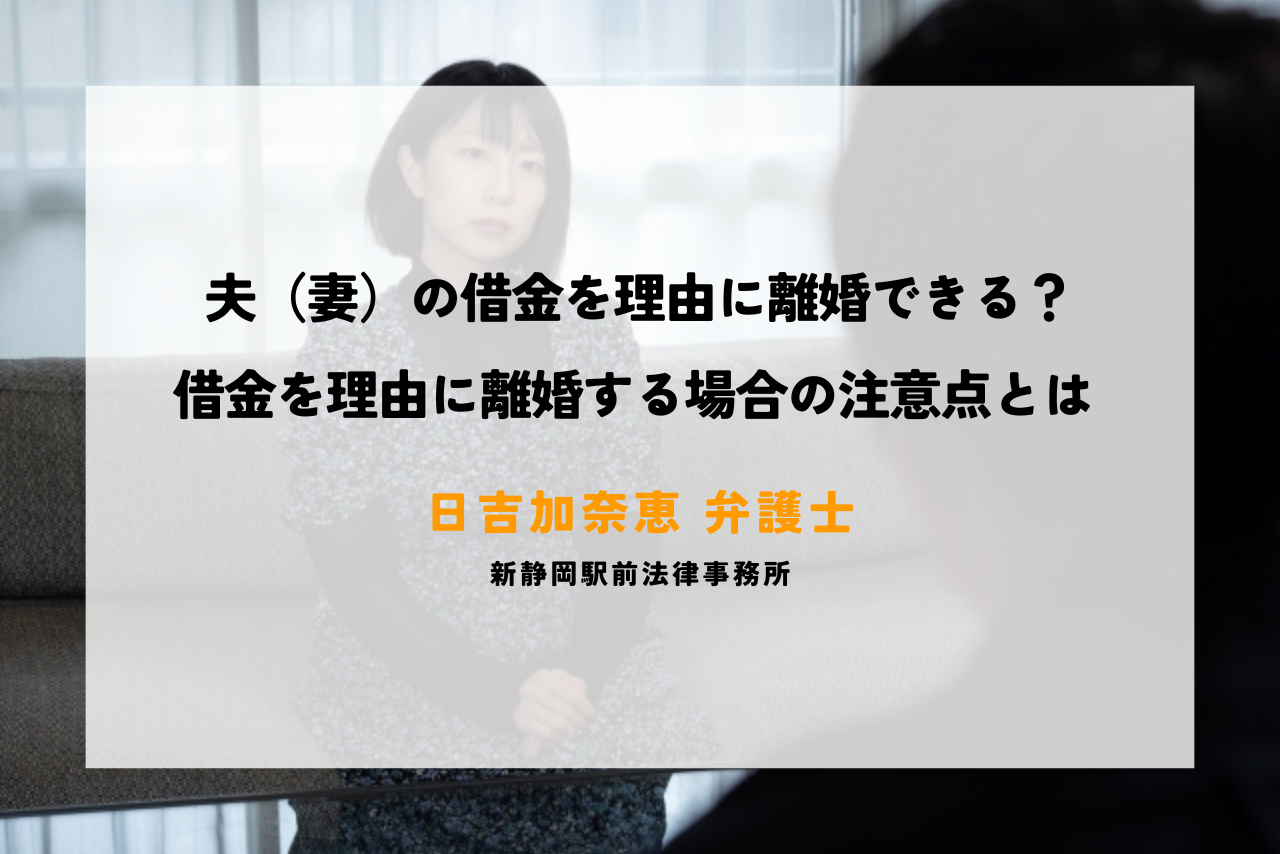配偶者が借金を繰り返していることを理由に離婚をしたいという方は多くいらっしゃいます。
相手の借金を理由に離婚をできるのか、相手の借金を自分も払わなければならないのかなど、不安に思うことも多いでしょう。
そこで、本記事では借金を理由に離婚する場合について解説します。
目次
1. 配偶者の借金を理由に離婚できる?
離婚は、お互いに話し合い離婚をするか(これを協議離婚といいます)、離婚調停を申し立て、調停委員の仲介の元相手方と話し合った上で離婚をするか(これを調停離婚といいます)、裁判を起こして裁判官の判断により離婚するか(これを裁判離婚といいます)のいずれかの方法にて行います。
協議離婚や調停離婚の場合、相手が離婚することに合意すれば離婚ができますので、借金を理由に離婚したいと告げ、相手も納得すれば借金を理由に離婚ができます。
ただし、離婚をする際には財産分与や慰謝料などの条件について定めたり、お子さんがいる場合は親権や養育費についても合意する必要があります。
調停離婚の場合、この条件が折り合わずに調停が成立しないこともあるので注意が必要です。
協議や調停で離婚ができない場合には、離婚裁判を行い、裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。
離婚裁判では、以下に記載する法が定める離婚事由がある場合にのみ離婚が認められます(民法第770条1項)。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
借金を理由に離婚したい場合、①・③・④の離婚事由には当てはまりませんので、②又は⑤に該当するかが問題となります。
②の悪意の遺棄とは、夫婦の義務とされている同居義務や扶養義務に正当な理由なく反した場合に認められます。
例えばギャンブルを理由に借金を繰り返し、一切生活費を入れないといった場合には、悪意の遺棄であると認められる可能性があるでしょう。
また、趣味にお金をつぎ込み借金ばかりし、一切家庭を顧みないために、夫婦関係が破綻しているような場合には、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。
このように、借金を理由に離婚裁判をする場合、単に借金があることのみでは離婚が認められない可能性があることに注意が必要です。
なお、離婚調停や離婚裁判については、以下のコラムで詳しく解説しています。
2. 離婚後に配偶者の借金を支払う必要がある?
借金を理由に離婚する場合、相手の借金を離婚後に負担しなくてはならないか心配な方もいるでしょう。
離婚の際には、財産分与といって、婚姻期間中に築いた財産を夫婦が2分の1ずつ分け合うことになります。
この財産分与は、あくまでプラスの財産がある場合にのみ行うため、マイナスの財産(借金)の方が多い場合に、相手の借金を半分負担しなくてはならないというわけではありません。
また、プラスの財産の方が多い場合には、プラスの財産の価額からマイナスの財産の価額を控除して、残額を2分の1ずつ分けます。
例えば預貯金が100万円、借金(負債)が50万円の場合、100万円から50万円を控除した50万円が財産分与の対象となるのが原則です。
ただし、相手がギャンブルなど個人的な理由でした借金については、マイナスの財産として控除しないことが可能です。
以下のような理由の借金については、財産分与の際にプラスの財産から控除しないよう主張することができるでしょう。
- ギャンブルのためにした借金
- 不貞相手にプレゼントなどをするためにした借金
- 結婚前に相手が借りていた借金
逆に、以下のような場合には、プラスの財産から控除する必要があるでしょう。
- 生活費のためにした借金
- 子どもの学費のための教育ローン
- 自宅不動産の住宅ローン
3. 例外的に借金を負担しなければならない場合
上記のとおり、配偶者が自分の名義でした借金については、支払う必要がないのが原則ですが、契約内容によっては自身に請求が来る場合もあります。
連帯保証をしているケース
連帯保証とは、主たる債務者(本来の債務者)の保証人として、債務を負担することをいいます。
この場合、保証人は、主たる債務者と同様の責任を負うことになるので、主たる債務者が債務を支払わなかった場合に、債務の全額を支払う必要が生じます。
あくまで保証人であることから、支払った後に、主たる債務者である配偶者に対して支払った額を返還するよう求めることができますが(求償権といいます)、相手の支払能力によっては全額を回収できない可能性もあるでしょう。
連帯債務者となっているケース
連帯債務とは、ある債務について、複数の債務者が独立して債務を返還する義務を負う形の契約です。
この場合には、自身も債務者(=借入をした人)となるため、当然に返済の義務を負うことになります。
このように、自身が保証人となっているケースや連帯債務者となっているケースでは返済の必要が生じます。
連帯保証や連帯債務の場合には、自身も借入の際に契約を締結していることになるので、契約書などを確認するようにしましょう。
また、連帯保証人となっているケースでは、相手の親族などに新たに連帯保証人となってもらうなどといった方法により、離婚後は連帯保証人から外れるという交渉ができる場合もあるので、金融機関や相手と交渉してみることもお勧めです。
4. 養育費の額に影響がある?
借金を理由に離婚する方の中には、借金を理由に養育費の額が減ってしまうのか心配な方もいらっしゃるでしょう。
しかし、養育費は子どもの健全な成長のための重要な費用であり、借金があるからといって減額されたり、支払い義務が免除されるものではありません。
子どものための重要な費用であることから、仮に相手が破産したとしても、養育費の支払義務については免責がされないこととなっており(非免責債権といいます)ますので、相手の収入に応じた額をきちんと請求することができます。
ただし、借金を理由に、支払いが滞ってしまったりする可能性もあることから、可能な限り公正証書や調停調書などの、強制執行が可能な形で支払い義務を定めるとよいでしょう。
養育費の請求方法については、こちらのコラムで詳しく解説しています。
5. 借金を繰り返す相手と離婚をする場合に慰謝料を請求できる?
相手がギャンブルのために借金を繰り返し、家庭を一切顧みなかった結果離婚する場合には、相手のそういった行為のために婚姻関係が破綻したとして、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、借金を繰り返している相手の場合、慰謝料の支払能力がない場合も多いでしょう。
この場合には、分割払いを提案し月々少しずつ慰謝料を支払ってもらう、財産分与で調整する(例えば、慰謝料の支払いを免除する代わりに自宅はもらうなど)といった方法も検討するとよいでしょう。
6. まとめ
相手の借金を理由に離婚する場合、借金額や自身が連帯保証人となっているかなどを事前に詳しく確認しておく必要があります。
ご自身の状況を正確に把握し、方針を検討することが必要になりますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、離婚に関するご相談を数多くお受けしており、状況に応じてアドバイスをさせていただくことが可能ですので、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。