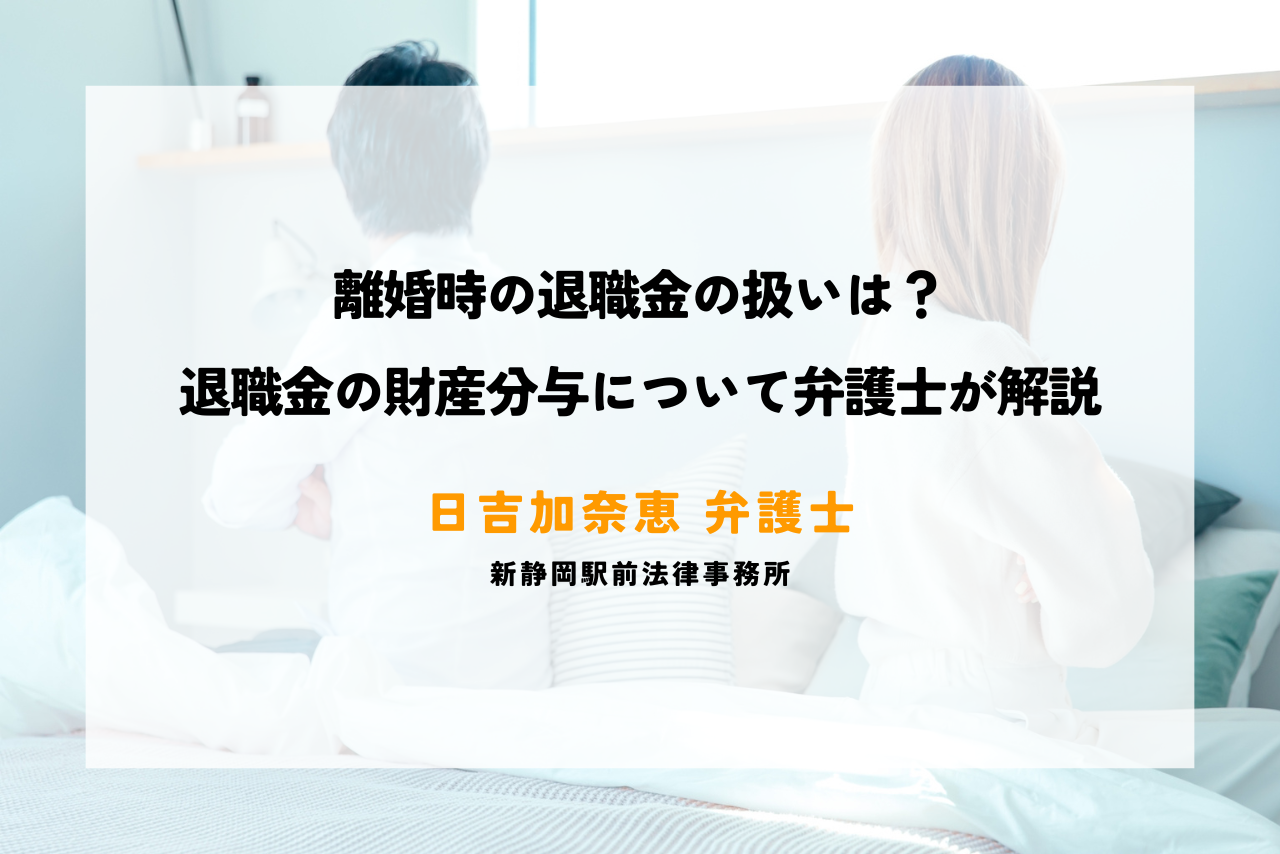婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、共有財産として財産分与の対象となります。
退職金は、退職時に支給されるという性質上、離婚における財産分与で退職金が対象になるのか、退職金の分与や計算の方法が分からないという相談は多いです。
本稿では、退職金の財産分与について弁護士が解説いたします。
なお、離婚時の財産分与の基礎知識については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
目次
1. 退職金とは
「退職金」とは、従業員が会社を退職する際に会社から支払われる一時的な賃金のことをいいます。
退職手当や退職慰労金と呼ばれることもあります。
賃金の後払い的性格を有しているため、勤続年数に比例して積み上げられることが一般的です。
退職金は法律上支払が義務付けられているものではないので、退職金制度は会社が就業規則等で定めるなどして、退職金の計算方法や金額を独自に決定することになります。
2. 退職金は財産分与の対象となるか
前述した一般的な退職金の性質からすると、婚姻期間中に積み上げられた、すなわち、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産といえるため、基本的に退職金は財産分与の対象になるということになります。
また、企業年金(確定拠出年金や確定給付年金等)も、賃金の後払い的性格を有しており、勤続年数に比例して積み上げられたもので、退職時に一時金として金銭が支払われる場合には、財産分与の対象となる可能性が高いです。
なお、企業年金と公的年金(厚生年金や国民年金)は、まったく別のものになります。
企業年金は財産分与で議論されるべきものですが、公的年金は離婚に伴う年金分割により処理されるものです。
年金分割については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
3. 退職金が財産分与の対象とならないケース
前述のとおり、退職金は基本的に財産分与の対象となりますが、財産分与の対象にならないこともあります。
具体的には、退職金の支払が確実でない場合には、財産分与の対象とならないと判断される可能性があります。
退職金の支払の確実性は、下記の事情を考慮して判断されます。
退職金規定の有無
会社の雇用契約書や就業規則等に退職金を支給するための規定がない場合、退職金の支払が確実でないと判断される可能性が高いです。
また、仮に退職金に関する規定があった場合であっても、具体的な計算方法や支払時期がない場合、例えば、「会社の業績により支給の有無と金額を決定する」など、支払の有無が不確実な規定になっている場合には、退職金の支払が確実でないと判断される可能性があります。
定年までの期間
定年までの期間が長いほど、退職金の支払予定時期が先になることから、確実性が低いと評価される傾向にあります。
会社の規模・経営状況
会社が倒産したり、会社の経営状況が悪化して賃金が支払えないような場合、退職金の支払が確実とはいえないことから、会社の規模・経営状況も考慮されます。
例えば、大手企業や公務員の場合には、退職金の支払の確実性が高いと評価されることになります。
他の従業員に対する支給実績
他の従業員に退職金が支払われた実績が多い会社の場合、退職金の支払の確実性が高いと評価されやすくなります。
4. 財産分与の計算方法
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産が財産分与の対象となるので、退職金も婚姻時から別居又は離婚時までが財産分与の対象となります。
具体的には、別居時又は離婚時に退職した場合の退職金の金額から、婚姻時に退職した場合の退職金の金額を差し引いた金額の2分の1が財産分与の金額となりまる。
例えば、別居時に退職した場合の金額が1000万円で、婚姻時に退職した場合の金額が100万円であれば、1000万円から100万円を差し引いた900万円の2分の1である450万円が財産分与の金額となります。
5. 財産分与の支払時期
退職金が退職した際に支払われるものであるという性質上、古い裁判例では、退職金の財産分与は退職時に支払われるべきというものも見られました。
しかし、近年の裁判例では、他の財産分与と同様に離婚時に支払われるべきとする裁判例がほとんどです。
したがって、基本的に退職金の財産分与は離婚時に支払われるものと考えて良いでしょう。
6. 既に退職金が支払われている場合
既に退職金が支払われている場合には、退職金が口座に預貯金として入金されていることになるので、口座の預貯金が財産分与の対象ということになります。
財産分与の基準時(別居時又は離婚時)までに、支払われた退職金の金額が減少している場合には、原則として、減少した金額の2分の1が財産分与の対象となります。
7. 退職金の財産分与の請求方法
退職金の財産分与は、裁判外でも請求が可能ですので、まずは当事者間で協議をしてみるのが良いでしょう。
裁判外での協議がまとまらない場合には、調停を申し立てることを検討しましょう。
「調停」とは、裁判所を介した話合いの手続で、調停委員会という裁判所が指名した裁判官(又は調停官)1名と調停委員2名が話合いの仲介をしてくれます。
まだ離婚が成立していない場合には夫婦関係調整(離婚)調停、既に離婚が成立している場合には財産分与調停を申し立てることになります。
なお、財産分与調停は、離婚成立時から2年以内に申し立てることが必要ですので、注意が必要です。
また、調停については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
8. まとめ
退職金の財産分与においては、退職金の金額を計算するための資料の収集や財産分与の計算が必要になり、専門的な知識や経験が必要となることもありますので、退職金の財産分与でお困りの方は、弁護士に相談することを検討すると良いでしょう。
当事務所は、財産分与を含む離婚に関する紛争を多く経験しており、実績は豊富です。
当事務所に相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。