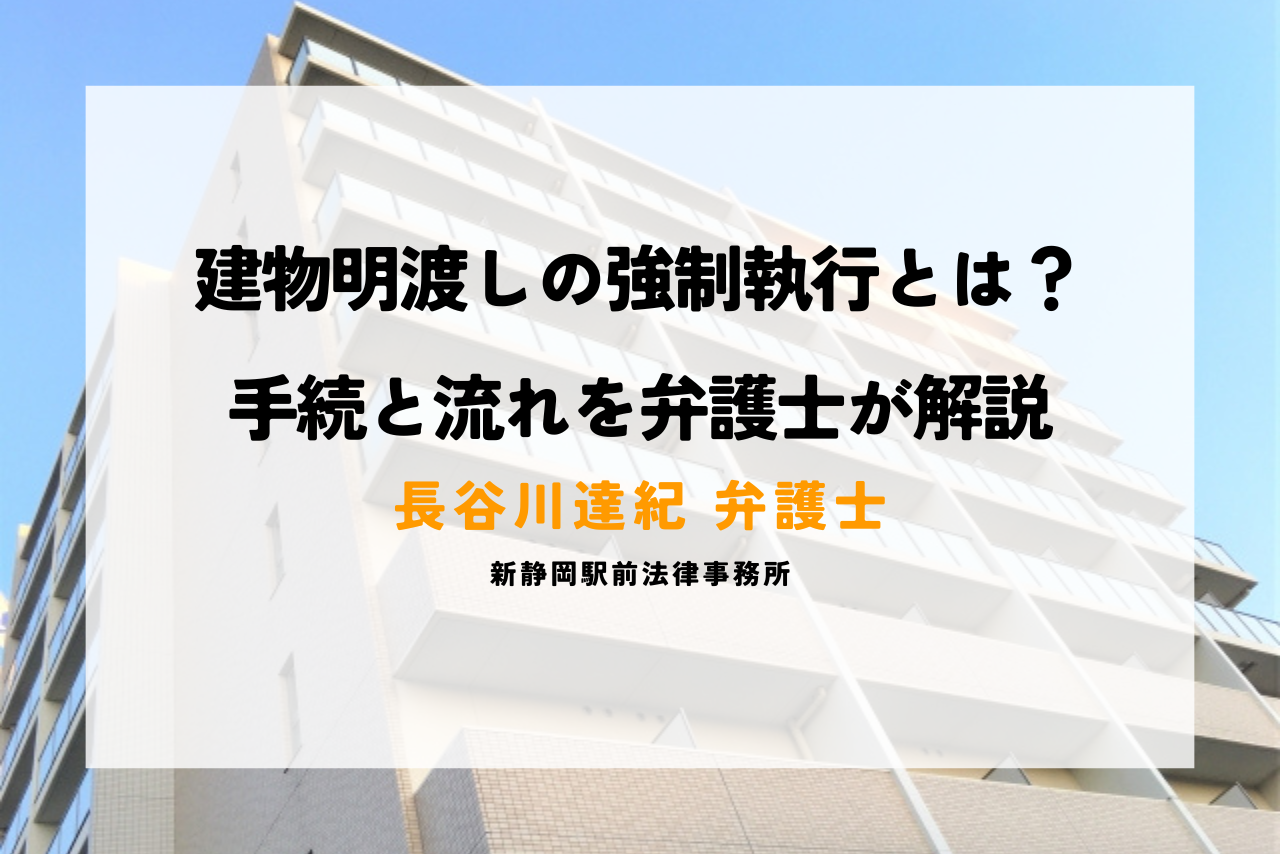建物の明渡しを命じる判決を取得しても、勝手に建物内に立ち入ったり、建物内の荷物を撤去することはできず、裁判所に強制執行手続の申立てを行う必要があります。
本稿では、建物明渡しの強制執行の手続と流れを解説いたします。
なお、建物明渡請求の詳細は、以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
目次
1. 強制執行とは
「強制執行」とは、債務の履行を命じる判決や裁判上の和解がなされたにもかかわらず、相手方が任意に債務を履行しない場合に、国家が強制的に債務を履行させる手続のことをいいます。
建物明渡しの場合、例えば、裁判所が建物の明渡しを命ずる判決を下したにもかかわらず、相手方が任意の明渡しに応じない場合、裁判所の執行官が強制的に建物内に立ち入り、荷物を搬出したり、相手方を退去させ、建物を申立人に引き渡す手続になります。
裁判所を通さずに、自ら鍵を交換してしまったり、荷物の撤去や搬出を行ってしまうと(「自力救済」といいます)、民事上の損害賠償請求をされたり、住居侵入罪や器物損壊罪などの刑事罰を課されるおそれがあるので、自力救済行為は絶対にやめましょう。
2. 強制執行の申立方法
建物明渡しの強制執行は、建物の所在地を管轄する裁判所に申し立てることで行うことができます。
申立てに当たっては、後述する書類を管轄裁判所の執行官に提出する必要があります。
3. 必要書類
債務名義
「債務名義」とは、公的機関が債務の履行義務の存在を証明した文書のことです。
具体的には、建物の明渡しを命じる確定判決、建物の明渡しを義務とする裁判上の和解(和解調書)や公正証書などが該当します。
債務名義のないまま、強制執行手続をすることはできませんので、債務名義を取得していない場合には、まずは債務名義を取得する手続を行うようにしましょう。
なお、建物明渡請求訴訟については、以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
また、債務名義には執行文を付与する必要があります。
「執行文」とは、債務名義に強制執行ができる効力があることを公的に証明する文書のことをいいます。
執行文は、裁判所又は公証役場に執行文付与の申立てを行うことで付与してもらうことができるので、強制執行を申し立てるに当たっては、事前に執行文付与の申立てを行うようにしましょう。
送達証明書
債務名義が相手方に送達されていることを証明する送達証明書の提出が必要です。
送達証明書は、裁判所又は公証役場に申請することで取得することができます。
また、債務名義が判決正本の場合、判決の確定証明書が必要な場合もありますので、裁判所から指示があった場合には、取得して提出するようにしましょう。
申立書
強制執行を求める申立書を作成し、裁判所に提出する必要があります。
必要部数は、裁判所用1通と債務者用(債務者の人数分)です。
また、申立書には、当事者目録(当事者の氏名や住所を記載したもの)、債務名義の表示及び執行場所の略図を添付するようにしましょう。
登記事項証明書・代表者事項証明書
当事者の一方又は双方が法人の場合、法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書が必要です。
登記事項証明書と代表者事項証明書は、法務局で取得することができます。
また、登記事項証明書と代表者事項証明書は、発行から3か月以内であることが必要ですので、注意しましょう。
住民票・戸籍謄本
債務名義に記載されている当事者の氏名や住所に変更があった場合、住民票の写し又は戸籍謄本を提出する必要があります。
住民票の写しは住民票上の住所の役所で、戸籍謄本は本籍地の役所で取得することができます。
また、住民票の写し又は戸籍謄本は、発行から1か月以内であることが必要ですので、注意しましょう。
予納金
強制執行の申立てに当たっては、予納金の納付が必要になります。
管轄の裁判所により予納金の金額は異なりますが、建物明渡しの強制執行では、相手方が1名の場合は、概ね6〜7万円程度のことが多いです。
なお、訴訟提起等の際には郵券(郵便切手)の納付が必要ですが、建物明渡しの強制執行の場合、郵券は予納金から充当されるため、郵券の納付は必要ありません。
また、予納金以外に生じる費用としては、執行に必要な費用として、人件費・荷物の撤去費用・荷物の保管費用・荷物の運送費用・段ボール代・鍵の解錠費用などが生じます。
執行費用は、建物の間取りや形状、荷物の量等により異なりますが、一般的なマンションやアパートの一室の場合は数十万円程度、戸建ての場合は100万円程度の費用がかかるのが一般的です。
なお、執行にかかった費用は、相手方に対する請求が可能です。
4. 強制執行の流れ
①執行官との打合せ
強制執行の申立てが完了したら、執行官と打合せを行います。
「執行官」とは、裁判の執行などの事務を行う裁判所職員です。
建物明渡しの強制執行においては、執行官が建物の占有者の占有を排除して、明渡しを実現することになります。
執行官との打合せは、直接会って実施することもありますし、電話等で行う場合もあります。
執行官の打合せにおいては、明渡しの催告(相手方に明渡期限と強制執行の日時を伝える手続)の日と断行日(強制執行を実行する日)を決定します。
また、執行補助者についても、打合せが行われます。
「執行補助者」とは、鍵の解錠業者や荷物の搬出業者などの強制執行の作業を補助する業者のことです。
自ら選定した執行業者がいれば執行官に伝え、適当な執行業者がいない場合には執行官から紹介してもらえることもあります。
②明渡しの催告
執行官との打合せが完了すると、執行官と明渡しの対象となっている物件に赴き、物件の状況を確認した上で、明渡しの催告を行います。
明渡しの催告は、明渡期限と強制執行の日時を記載した公示書を物件内に貼り付ける方法で行われます。
③断行
明渡期限の日を経過しても、相手方が物件を明け渡さない場合には、事前に公示した強制執行の日時に強制執行を断行します。
断行には、必ず申立人の立会いが必要になるので、執行官と執行補助者と共に物件に赴くことになります。
執行補助者が荷物を搬出するなどして相手方の占有を排除することが完了したら、鍵を交換した上で物件が申立人に引き渡されます。
搬出した荷物は、執行官が指定する保管場所に一定期間保管され、債務者や同居親族等に荷物の引渡しができる場合にはこれを引き渡し、引き渡せない場合には売却・破棄等の処分が行われます。
なお、実務においては、建物明渡しの強制執行の申立てと併せて、建物内の動産の強制執行(動産執行)の申立てを行うことが一般的です。
建物内に価値のある動産がある場合には、動産執行により動産を換価することで、未払賃料や執行費用に充てることができるからです。
5. まとめ
これまで解説したとおり、建物明渡しの強制執行手続は、必要書類の収集・執行官とのやりとり・催告や断行への立会いなど、負担が大きい手続になります。
ご自身で対応することが難しい、専門的な知識・経験がある者に手続を一任したいという方は、強制執行手続を弁護士に依頼することも検討すると良いでしょう。
当事務所は、離婚や相続などの家事事件に注力しておりますが、離婚や相続の案件においては、不動産が争点になることが多いため、不動産案件の経験も豊富です。
不動産問題の相談を希望される方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。