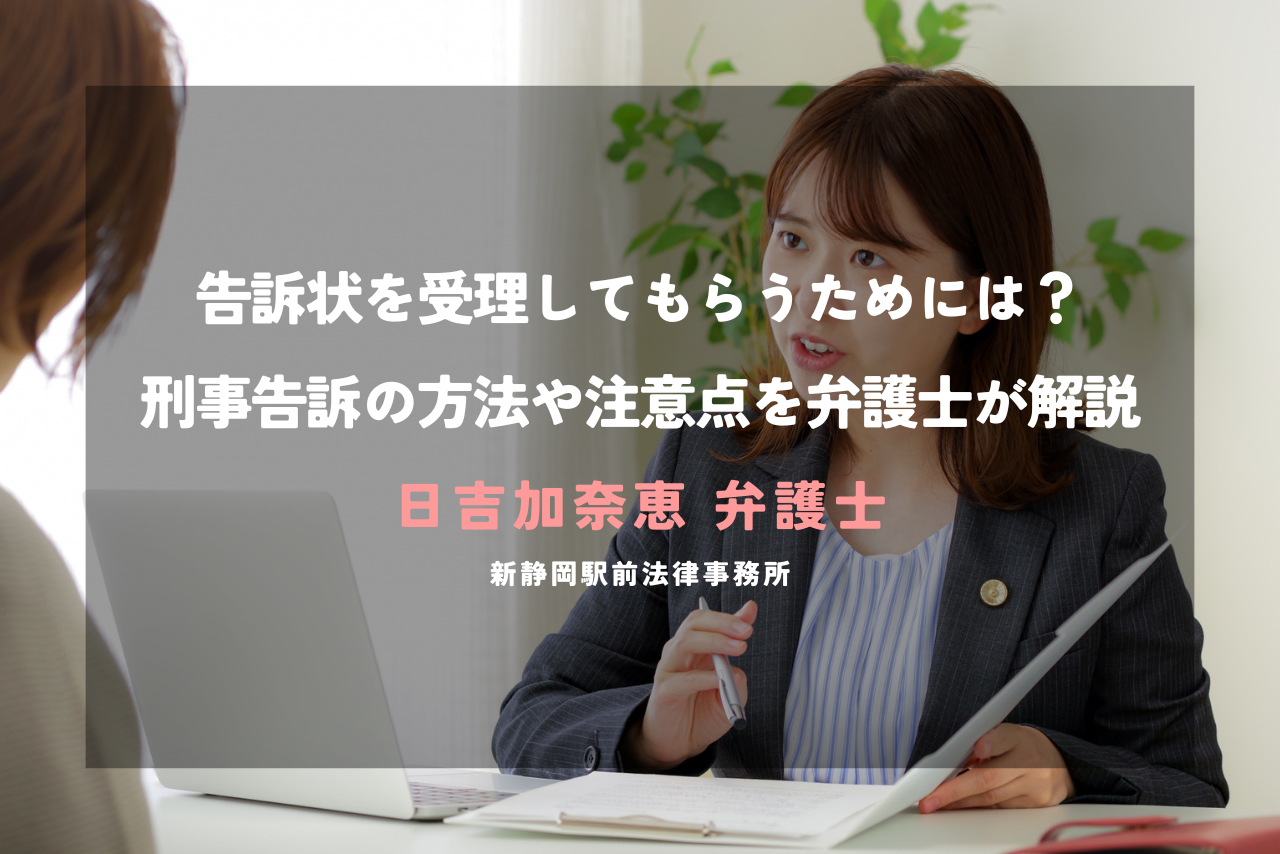犯罪の被害に遭ってしまった場合の対処法として、刑事告訴をし、犯罪の被害を警察に申告して相手の処罰を求めるという方法があります。
そこで、本記事では、告訴の方法や、告訴をする場合の注意点について解説します。
目次
1. 告訴とは
告訴とは、犯罪の被害にあった場合に、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して加害者の処罰を望むという意思表示をすることです。
似た制度として被害届や告発というがあり、いずれも犯罪の事実を捜査機関に申告するという点では同じです。
告訴と被害届の違いとしては、警察は告訴状を受理した場合には必ず捜査を開始しなければならないのに対し、被害届は、警察に対し捜査を開始するよう義務を課すものではないという点です。
警察が被害届を受理したとしても、警察の判断で捜査を開始しないということが可能なため、確実に捜査を開始して欲しい場合には、告訴をすることを検討するとよいでしょう。
告訴と告発の違いは、届出ができる人が被害者本人(または代理人)に限られているかどうかです。
告訴は被害者本人しかできないのに対し、第三者など被害者以外の人でもできるのが告発です。
なお、名誉棄損など一部の犯罪については、告訴がなければ検察官が起訴できないとされています(これを「親告罪」といいます)。
被害者が望んでいないのに、知られたくない事項を強制的に証言させられたりするのを防ぐために、一部の犯罪については起訴をするには告訴を必須としているのです。
2. 告訴の方法
告訴は、書面又は口頭で行うことができます。
書面でする場合には、告訴状といって、以下の内容を書いた書面を捜査機関に提出します。
- 作成年月日
- 宛先(警察署の署長名を記載します)
- 告訴人の氏名、住所、電話番号
- 被告訴人の氏名、住所、電話番号
- 告訴趣旨(行為と罪名、加害者の処罰を求める旨の記載)
- 告訴事実(犯罪の詳細)
- 証拠方法(証拠として提出する資料の説明など)
例えば、傷害事件で告訴を行う場合の告訴の趣旨は以下のような記載をします。
被告訴人の下記行為は、刑法第204条(傷害罪)に該当すると思料されるため、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴する。
また、告訴事実は以下のように記載します。
被告訴人は、令和○年○月○日午後○時○分頃、静岡県○○市○○所在の告訴人の住居地において、告訴人に対し、告訴人の胸部を殴る・蹴るなどの暴行を加え、告訴人に胸部打撲の傷害を負わせたものである。
これに加えて、告訴に至る経緯として当事者の関係性や、当日の状況などを詳しく記載することが一般的です。
また、傷害の場合には、証拠として、怪我をした部位の写真や診断書等を提出します。
なお、口頭で告訴を行う場合には、上記の事実を捜査機関に申告して、告訴調書を作成してもらうこととなりますが、実務上は告訴状の提出を求められることが多く、口頭で告訴を受理してもらえることは稀です。
3. 告訴状の提出先
告訴状の提出先は、検察官又は司法警察員と定められています(刑事訴訟法第241条1項)。
司法警察員とは、巡査部長以上の階級の警察官のことをいいますので、検察官か警察官に告訴状を提出することになります。
ただし、警察官による捜査を経ずに検察官が捜査を開始することは基本的にありませんので、警察官に対し告訴状を提出する方がスムーズでしょう。
また、提出する警察署について、法律上特段の決まりはありませんので、どこの警察署であっても提出は可能ですが、告訴状が受理された後、スムーズに捜査がされるためにも、犯罪があった場所を管轄する警察署に提出する方がよいでしょう。
4. 告訴状は必ず受理してもらえる?
告訴状を提出しようとして警察署に行ったのに、受理してもらえなかったというご相談をよくお受けすることがあります。
このような場合に考えられる理由としては、告訴状に記載すべきである事項が書かれていなかったり、証拠が足りないと判断されたり、犯罪事実が不明確(犯罪の時間や場所、方法が不明確)だったりといったことです。
前述のとおり、告訴状を受理した場合には警察官は必ず捜査を開始しなければならないことから、限られた時間・人員の中では、全ての告訴状を受理できないという実情があると考えられます。
5. 告訴状を受理してもらうためのポイント
それでは、どうすれば告訴状を受理してもらえるのでしょうか。
以下では、告訴状を受理してもらうためのポイントを解説します。
①証拠を提出する
告訴状を提出するにあたっては、事前に可能な限りの証拠を集め、告訴状と共に提出しましょう。
証拠が一切ないというような場合、告訴人の証言のみでは捜査機関も事件性があるかどうかが判断できません。
たとえば、傷害事件で告訴をしようとした場合に、相手に暴行をされた証拠や怪我をした証拠が一切ないという場合、警察としても、本当に犯罪事実があったかが分からず、告訴状を受理してもらえない可能性が高くなってしまうでしょう。
②警察や検察に事前に相談する
警察や検察に事前に相談をすることも一つのポイントです。
都道府県の警察本部や警察署には、告訴・告発センターが設置されていたり、検察庁にも告訴を受け付ける専門の係があるので、告訴状を書く際には、事前に相談してみるとよいでしょう。
③示談する意向があると明言しない
告訴状を提出する段階で、示談の意向がある・示談の予定があることを明言してもらうと、警察官は、後々示談が成立したら刑事告訴が取り下げられてしまうと考え、告訴状の受理に消極的になってしまう可能性があります。
もちろん、告訴状が受理され、後に示談をすることが妨げられるものではありませんが、告訴状の提出段階では、はっきりと意向を伝えないといった対応が考えられます。
④明確な告訴状を作成する
例えば、犯罪事実が不明確だったり、記載内容が不明確であったりすると、形式や記載の不備を指摘されて、告訴状を受理してくれないということがよくあります。
告訴状の作成にあたっては、正確な記載を心がけるようにしましょう。
また、前述した告訴状へ記載すべき内容については、漏らさずに記載をしましょう。
⑤弁護士などの専門家に相談する
ご自身のみで対応することが難しい場合には、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
弁護士であれば、不備のない告訴状を作成することができますし、捜査機関としても、犯罪事実を弁護士も確認していると認識し、告訴状を受理しやすくなるといった効果が期待できます。
6. 告訴状が受理された後の流れ
警察官が告訴状を受理すると、まずは警察が捜査を開始します。
捜査の中では、警察が加害者(被告訴人)を取り調べ、必要に応じて逮捕することもあります。
警察による捜査が終わると、警察は事件を検察に送致(事件の記録を検察庁に送ること)します。
事件の記録を受領した検察官は、捜査を経て起訴又は不起訴の判断をします。
検察官が起訴をした場合には刑事裁判が開かれ、有罪であるのか、無罪であるのか、有罪であるとしてどのような刑罰となるのかが決まります。
不起訴になった場合には、刑事裁判は開かれず、事件は終了となります。
告訴状を提出している場合には、警察官や検察官による捜査の段階で、加害者の代理人弁護士から示談の申し入れがあることがありますので、示談に応じられるかどうかを検討するようにしましょう。
なお、検察官は、告訴人に対し、起訴又は不起訴の結論を告訴人に報告する義務を負います(刑事訴訟法第260条)。
更に、不起訴の判断をした場合には、告訴人の請求に応じて、不起訴の理由を開示しなければならないとも定められていますので(同法第261条)、不起訴となってしまった場合には、必要に応じて検察官へ理由を確認しましょう。
また、理由が適切でない場合には、検察審査会(検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査する組織をいいます)への審査の申立てを検討するとよいでしょう。
7. 告訴できる期間に制限はある?
一定の罪の場合、告訴をできる期間について制限がある場合がありますので、注意が必要です。
刑事訴訟法第235条1項本文では「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過したときは、これをすることができない」と定められていますので、親告罪について告訴をする際には、期間制限内に告訴をするようにしましょう。
親告罪の代表的例は名誉棄損罪(刑法第230条1項)や、侮辱罪(刑法第231条)などです。
親告罪以外の犯罪については、告訴をできる期間に制限はないので、時効を迎えるまではいつでも告訴をすることができます。
ただし、一般的には事件の発生から時間が経過すればするほど、証拠が散逸していく(例:防犯カメラの映像が消えるなど)などの理由で犯罪の立証がしづらくなりますので、早めに告訴をする方がよいといえます。
8. まとめ
告訴状は、なかなか警察に受理してもらえないことも多く、ご自身のみで対応するのが難しい場合が多いです。
告訴状の提出を検討される場合には、経験豊富な当事務所の弁護士に相談することを検討してみてください。