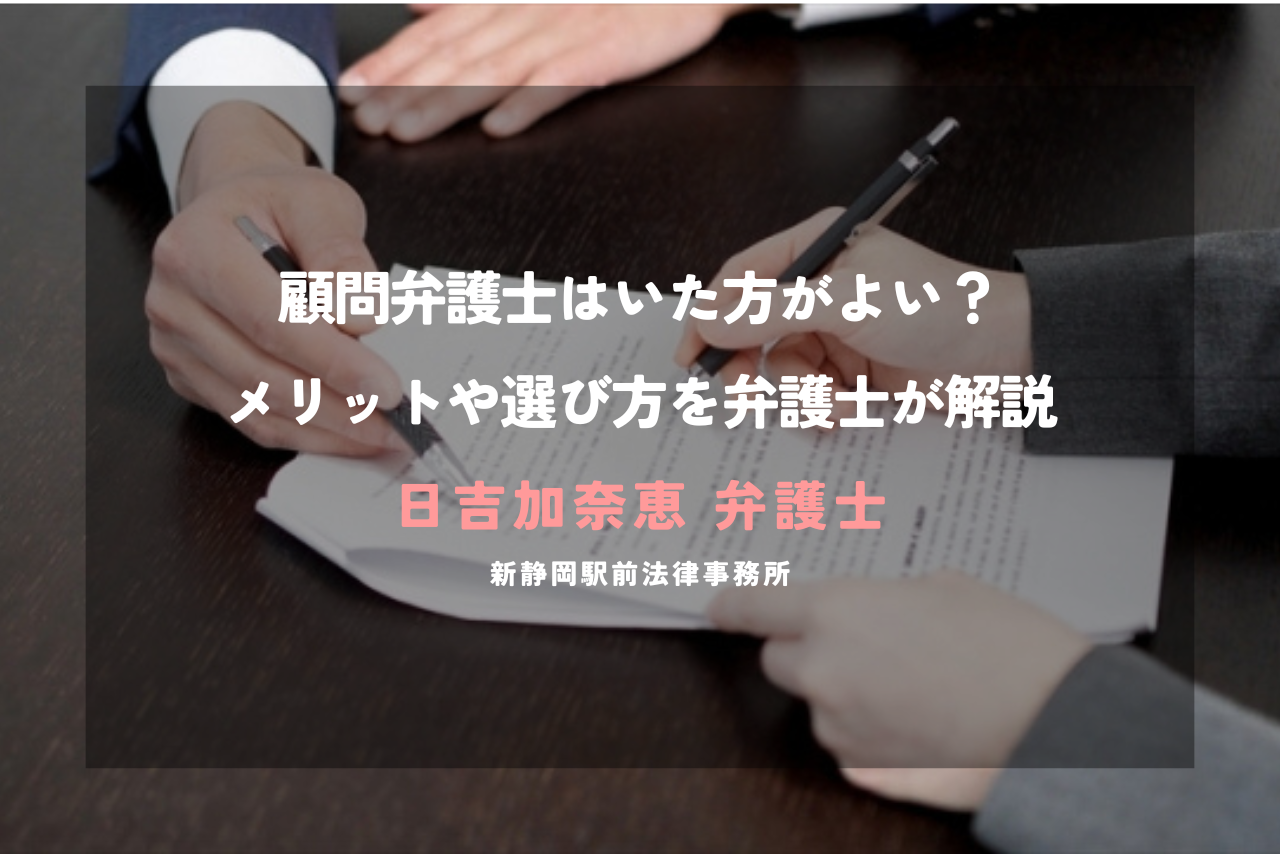企業経営をしていくうえで、守らなければならない法律は多いです。
また、取引の際や従業員とトラブルになってしまった際にも、法律に基づいてトラブルを解決する必要があります。
このように、企業経営の場面では、法律を理解し、適用していく場面が非常に多いです。
顧問弁護士がいることで、日常的に法律に関する相談を気軽にすることができ、企業をより成長することにつながります。
そこで、本記事では、顧問弁護士の必要性や選び方について解説します。
目次
1. 顧問弁護士とは
顧問弁護士とは、顧問契約を締結した企業に対して、法的サービスやアドバイスを継続して提供する弁護士のことです。
会社の事業内容に法的リスクがないかといった予防法務観点からのアドバイスはもちろん、万が一トラブルが発生してしまった際の対応まで、顧問弁護士が追う役割は様々です。
例えば、新規ビジネス実施の際の法的チェック(景品表示法や消費者契約法、個人情報保護法など守るべき法律の規定を順守できているか)就業規則などの社内体制の整備から、トラブルや不祥事発生時の法的対応(従業員との労働問題、不祥事発生時の対応、取引先からの債権回収など)、契約書の作成・リーガルチェックに加え、各種研修のサポート(コンプライアンス研修など)など、あらゆる法的サービスについて対応することになります(なお、契約内容によっては、対象外となる業務もあるため、事前によく確認することをお勧めします)。
2. 顧問弁護士のメリット
①継続的に相談ができる
企業に顧問弁護士がいることの大きなメリットの一つが、継続的に相談することができるという点です。
事案ごとに弁護士に依頼をすることももちろん可能ですが、その場合、会社が実施しているビジネスの内容や会社の状況など、前提を都度説明する必要があることになります。
継続的に相談をすることで、弁護士も企業の状況をよく理解できるため、より実効性のあるアドバイスが可能となります。
②いつでも相談できる体制を整えることができる
顧問弁護士がいない場合、相談の都度依頼できる弁護士を探し、契約を締結したうえで法的サービスの提供を受けることになります。
相談ができるまでにタイムラグが生じたり、場合によっては弁護士が見つからないということもありえるでしょう。
顧問弁護士であれば、こういった事前の対応は一切不要で、すぐに相談できます。
また、弁護士に相談すべきか悩むような事柄でも、気軽に相談することができます。
③迅速な対応をしてもらえる
多くの弁護士は、複数の案件を同時に処理しているため、連絡がつきづらい、案件対応までに一定程度の時間がかかるというのが通常です。
そのため、トラブルが起きたときにすぐに対処してもらえない、急いでリリースしたい案件があるのに間に合わないということが起きてしまいます。
顧問契約を締結している企業からの依頼については、優先的に対応をしてもらえますので、トラブルが起きた際に対応ができず被害が拡大してしまうことを防ぎやすくなります。
また、日常的に相談しやすい環境が整っているため、事前にスケジュール感も相談することにより、ビジネスの進行を阻害しない形で相談が可能となります。
④コストを抑えることができる
多くの弁護士とは、月額3~5万円で顧問契約を締結することができます。
企業に新たに法務部を設置するとなると、人員の確保や採用コストなど、多くの労力がかかります。
顧問弁護士であれば、事前にコストを把握しやすく、また顧問料の範囲内で様々な相談に乗ってもらえることができます。
なお、顧問契約の場合、対応範囲や稼働時間等が契約に定められており、訴訟対応や上限時間を超えた業務については別途費用が必要となる場合もあります。
顧問契約締結の際は、事前に条件をよく確認しておくとよいでしょう。
⑤トラブルを予防しやすい
実は、多くの法的トラブルについては、事前に予防措置を講じていれば防げた可能性があったものとなります。
弁護士には、トラブルが起こってしまってから相談するというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、企業経営の観点からすると、大切なのはトラブルを起こさない「予防法務」です。
顧問弁護士がいれば、日常的に相談ができるため、トラブルの予防に関するアドバイスももらいやすいといえるでしょう。
3. 顧問弁護士の選び方
このように、企業の経営の観点からもメリットが多い顧問契約ですが、顧問契約を締結する際には、どの弁護士を選ぶかについて慎重な検討が必要です。
以下では、顧問弁護士を選ぶ際のポイントを解説します。
①自社の事業に理解のある弁護士を選ぶ
これまで述べてきたように、適切なリーガルサポートには、ビジネスへの深い理解が必須です。
弁護士にもそれぞれに得意分野がありますので、製造業には詳しいが、ITはあまり・・・という方もいるでしょう。
展開するビジネスによって適用される法律も様々のため、弁護士の経歴や過去の対応実績を踏まえて、元々業界への基礎知識がある弁護士を選ぶとよいでしょう。
②相性の良さ
顧問契約を締結した場合には、その弁護士と長期的・継続的に付き合っていくことになります。
コミュニケーションが取りづらかったり、気軽に相談できない弁護士を選んでしまうと、せっかくの顧問契約が無駄になってしまうことになりかねません。
信頼関係を構築することで、より顧問契約のメリットを感じることができるでしょうから、相性の良さも重視して選ぶとよいでしょう。
③対応範囲とコストが見合っている
月額の顧問料の範囲でどこまで対応してくれるかは、その弁護士によっても様々です。
多くの顧問契約では、月額の稼働時間の上限が決まっており、その上限を超えて対応をした場合には、別途料金がかかることが通常です。
それに加えて、例えば、月額の稼働時間の範囲内であっても、特定の案件については別料金であるといったケースもあり、顧問契約の条件については弁護士によって多種多様です。
自社がどのような対応を依頼する想定か、どの程度活用できそうかなどを踏まえて、コストと対応内容が見合った弁護士に依頼することで、長期的な関係を築くことができるでしょう。
4. 顧問契約のご相談なら新静岡駅前法律事務所へ
コンプライアンスに関して世間からの厳しい目が注がれる昨今、顧問弁護士は、企業にとって必要不可欠な存在になりつつあります。
当事務所には、東京都内の大手IT企業にて企業内弁護士として勤務した経験を持つ弁護士や、労働問題を多数取り扱っている事務所に所属していた弁護士が在籍しておりますので、
ご希望に応じた法的サービスを提供することが可能です。
また、当事務所では、月額3万円から顧問契約をご依頼いただくことが可能ですので、顧問契約の締結をご検討の方や、現在の顧問契約の見直しをご検討いただいている方は、お気軽にお問い合わせください。