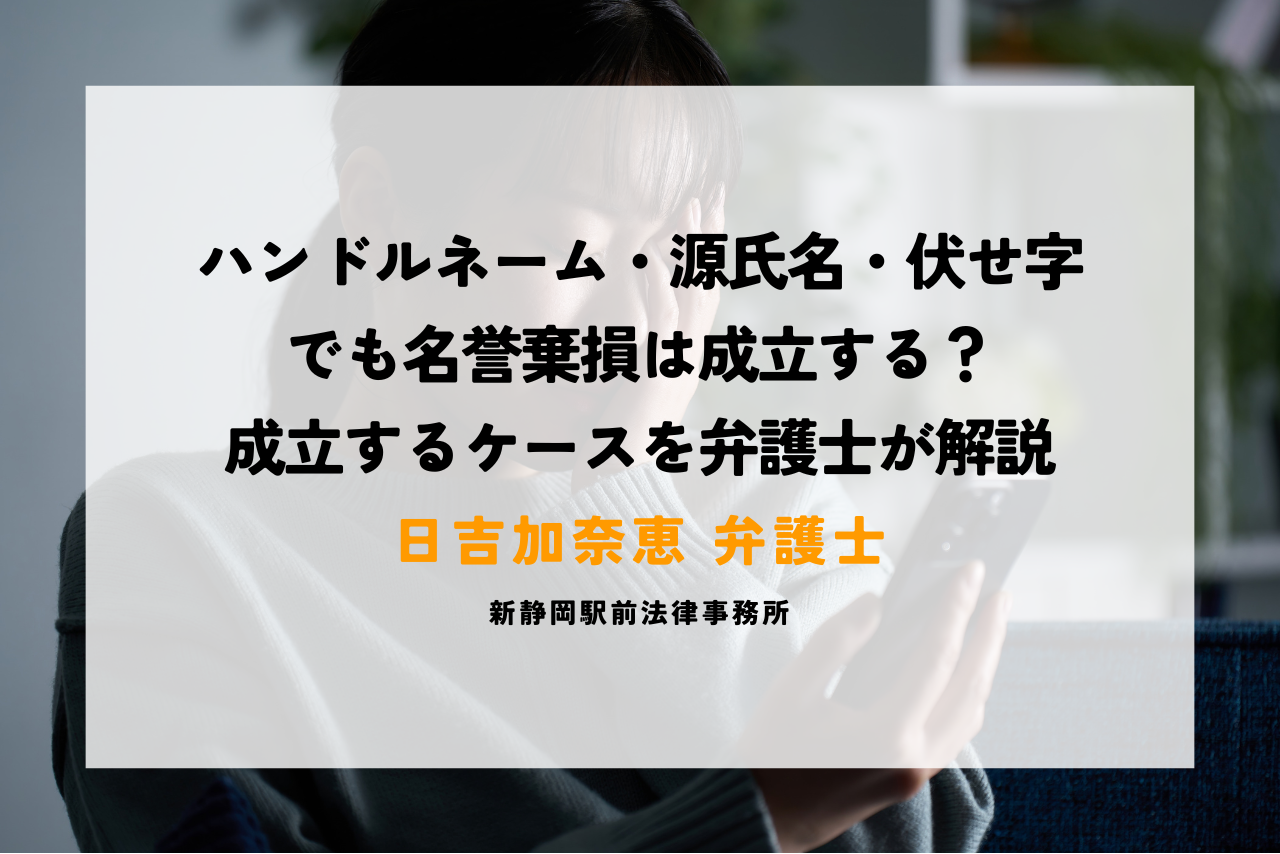近年、インターネットの普及により、誹謗中傷の被害は深刻化しています。
中には、本名を出さずに「A山A子」など名前の一部を伏せ字にしたり、源氏名のみを記載して誹謗中傷をしている投稿もあります。
そこで、本記事では、ハンドルネームや源氏名、伏字による名誉棄損について解説します。
目次
1. 名誉棄損とは
名誉棄損とは、公然と事実を適示したり、意見や論評をすることにより人の名誉を棄損することをいいます。
「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことをいいます。
例えば、誰もが閲覧できるSNSに投稿をした場合には、公然性があるといえるでしょう。
また、名誉棄損といえるためには、事実を摘示(具体的な事実を挙げること)するか、意見や論評をすることにより人の名誉を棄損(=特定の人・団体の社会的評価を低下させること)したといえることが必要です。
なお、刑法上の犯罪にあたる名誉棄損罪(刑法第230条)については、意見論評のみでは成立せず、事実の摘示が必要とされていますので、注意が必要です。
2. 名誉棄損と同定可能性
名誉棄損が成立するためには、上で挙げた要件の他に、第三者が投稿を見た際に、その投稿が誰のことを指しているかが判別できることが必要です。
これを同定可能性といいます。
例えば、「Aさんには犯罪歴がある」という書きこみだけでは、書かれた本人であっても、Aさんが自分のことを指すのか、他の誰を指すのかが分からないでしょう。
このような場合には、同定可能性がないとして名誉棄損は成立しません。
3. ハンドルネーム、伏せ字、源氏名で名誉棄損(名誉権侵害)が成立するか
ハンドルネームの場合
投稿にハンドルネームのみが記載されている場合であっても、そのハンドルネームから特定の個人を識別することができれば、名誉毀損が成立する可能性があるでしょう。
例えば、芸名や作家のペンネームなど、ハンドルネームを用いた社会活動の実態がある場合には、特定の個人を識別できる可能性があると認められる可能性が高いといえるでしょう。
他方で、個人の方が限られた場所でのみハンドルネームを用いているといった場合には、同定可能性が認められないことがあります。
伏せ字の場合
名前の一部が省略されている伏せ字やイニシャルの場合でも、投稿から個人が識別できるかが判断のポイントとなります。
また、他の記載と併せて特定の個人を識別できるかも重要です。
例えば、「S木M子さん」のみではどの人を指すのかは特定できない可能性が高く、名誉毀損は成立しないと考えられます。
他方、「〇〇会社勤務のS木M子さん」と記載されている場合、その会社に「S木M子」という記載に当てはまる人が一人しかいなければ、投稿を見た人が、〇〇会社に勤めている木M子さんのことを言っているのだな、と分かるため、名誉毀損が成立する可能性が高いといえるでしょう。
源氏名の場合
源氏名の場合も同様に、誰のことを指している投稿か判別できれば名誉毀損が成立する可能性があります。
源氏名の場合、他のお店にも同じ名前のキャストがいることも多く、源氏名のみでは同定可能性が否定されるケースも多いでしょう。
他方、「キャバクラ〇〇のA子(源氏名)」と記載されている場合には、同定可能性が肯定されうるでしょう。
また、投稿自体にお店の名前が書いてなかったとしても、掲示板がお店ごとに作成されている場合、そのお店のキャストについての話題であるとして、同定可能性が認められることもあります。
4. アカウント名のみ記載されている場合
投稿に氏名の一部や源氏名が記載されておらず、InstagramやXのアカウント名のみが記載されている場合も多いでしょう。
このような場合には、記載されたアカウントのフォロワーに知り合いがいれば、同定可能性が認められる傾向にあります。
5. 名誉棄損をされている場合の対処法
①投稿の削除を請求する
SNSや掲示板等の投稿で名誉棄損をされている場合、投稿をそのままにしてしまうと、時間の経過とともに投稿を見る人も増え、被害が拡大してしまいます。
サイトの管理者に削除依頼を出す(近年では、削除依頼用フォームがあるサイトが多いです)、裁判所を通じて削除をするよう申し立てるなどして、投稿の削除をするとよいでしょう。
削除依頼の方法は、以下のコラムで詳しく解説しています。
ただし、後に投稿者の特定や投稿者への損害賠償請求をする場合には、投稿の証拠が必要です。
必ず証拠(スクリーンショット等)を保存したうえで削除依頼をするようにしましょう。
また、証拠は、投稿の内容や投稿日時、投稿のURLが分かる形で保存しておくようにしましょう。
②相手に対して損害賠償請求をする
名誉棄損は、民法上の不法行為にも該当するため、相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
投稿者が不明な場合には、まずは相手の住所や氏名を特定する必要があります。
発信者情報開示命令という制度を利用して相手の情報の開示をさせましょう。
開示命令の申立て方法は、以下のコラムで詳しく解説しています。
損害賠償請求は、相手に対して内容証明郵便(誰が、いつ、どんな内容の文書を誰に対して送付したのかを、郵便局が証明してくれる郵便)を送付するか、民事訴訟(裁判)を提起して行うことが一般的です。
訴訟については手間や時間がかかるため、まずは内容証明郵便を送付し、相手が交渉に応じない場合や、交渉が決裂してしまった場合には訴訟をすることをお勧めします。
③被害届の提出や刑事告訴を検討する
被害届を提出する・刑事告訴をすることも一つの手段です。
これにより警察が捜査を開始してくれれば、相手は取り調べを受けたり、場合によっては逮捕されることになります。
刑事罰を避けたい相手から、示談の申し入れがされ、その中で交渉することにより慰謝料を受け取る・今後投稿をしないことを約束させる等の交渉ができる可能性があります。
なお、示談交渉は、通常は、相手が委任した弁護士より、示談をしたいという申し入れの連絡が来る形で始まります。
このような場合、警察から、加害者の弁護人に連絡先を教えてよいか?と確認が来ることが多いので、示談交渉をしてもよいとお考えの場合には、連絡先を教えてよい旨を回答するようにしましょう。
6. まとめ
投稿に氏名の一部しか記載されていない場合や、源氏名のみしか記載されていない場合に名誉棄損が認められるかについては、数多くの裁判例があり、慎重な判断が必要です。
投稿者の特定の際にも、同定可能性が認められることについての主張を詳細にしないと、裁判所に同定可能性を認めてもらえないといったことになりかねません。
当事務所では、SNSや掲示板での誹謗中傷に関するご相談を多くお受けしており、投稿者の特定の実績も豊富です。
お悩みの方は、一度お気軽にお問い合わせください。