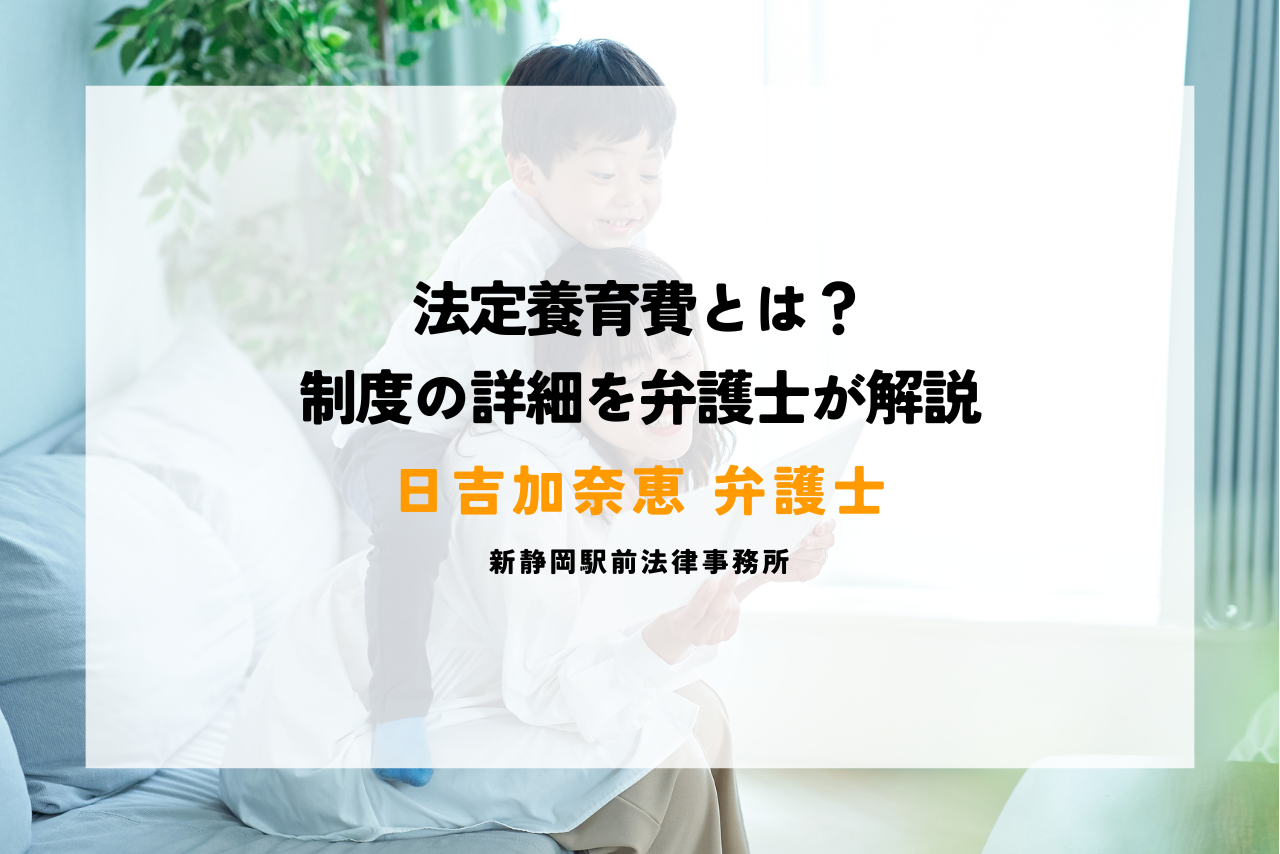民法改正により、離婚時に養育費の額を取り決めしていなくても一定額の養育費の請求が可能となる「法定養育費」の制度が導入されます。
そこで、本記事では、法定養育費の制度の詳細について解説します。
目次
1. 法定養育費とは?
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいい、生活費や医療費、教育費などが含まれます。
夫婦が離婚した後、子どもと一緒に暮らし、子どもの監護養育をする親(監護親といいます)は、もう一方の親(非監護親といいます)に対し養育費を請求することができます。
もっとも、養育費の請求をするためには、離婚時の協議や調停などの手続きにより、養育費の額(子どもひとりあたり月額〇円という形が一般的です)を決める必要がありました。
しかし、養育費の額を協議することなく離婚してしまい、その後の請求には手間や時間がかかったり、相手が協議に応じてくれないなどという理由で、養育費の支払いを受けていない監護親が多いという実情がありました。
そこで改正民法では、養育費について取り決めがない場合でも、以下のとおり改正民法で新設される条文に基づき、一定額の養育費を請求できることになりました。
改正民法第766条の3第1項
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。(以下略)
2. 法定養育費の制度概要
法定養育費を請求できる期間
法定養育費は、離婚の日から請求できます。
例えば、離婚から1年後に法定養育費を請求する場合には、離婚の日から1年分をまとめて請求することができるのです。
また、法定養育費を請求できる期間は、以下のいずれか早い時期までとされています。
- 父母の協議により、養育費の分担についての定めをした日
- 養育費の分担についての審判が確定した日
- 子どもが成年(18歳)に達した日
法定養育費は、あくまで当事者間の養育費に関する協議がない場合に暫定的に養育費を請求できる制度のため、父母の協議や審判により養育費の額が決まった場合には、法定養育費の請求はできなくなり、代わりに協議や審判で決まった額の支払を請求することになります。
また、子どもが成人した場合にも法定養育費の請求はできません。
子どもが大学や専門学校に進学するため18歳以降も養育費を支払ってもらう必要がある場合には、父母の協議で養育費を決めておくようにしましょう。
法定養育費を請求できる場合
法定養育費の請求ができるのは、父母が養育費の取り決めをせずに離婚(協議離婚であるか調停離婚であるか裁判離婚であるかは問いません)をした場合です。
養育費の取り決めがある場合には、その取り決めに従って養育費の支払を請求することができるため、法定養育費の請求はできません。
法定養育費の額
法定養育費の額は、条文上「法務省令で定めるところにより算定した額」とされています。
まだ法務省令で指定されていませんが、現状法務省が公開している省令案では、子ども1人あたり月額2万円とされています。
今後、パブリックコメント(意見公募)を経て、正式に額が決定される予定です。
3. 法定養育費を請求できない場合はある?
法定養育費は、支払い義務を負う人が支払いに合意しなくても当然に請求できるものですが、法律上の例外は定められています。
以下のいずれかに該当することを相手が証明した場合には、請求が認められないとされています(改正民法第766条の3第1項但書)。
- 支払能力を欠くためにその支払をすることができない
- 支払をすることによってその生活が著しく窮迫する
また、過去の法定養育費の支払については、家庭裁判所が支払い能力を考慮して支払義務の一部又は全部を免除することができるとされています(改正民法第766条の3第3項)。
例えば、過去分の支払額が膨大であり、支払能力がないと考えられる場合には、過去分については一部のみ支払義務が認められるといった可能性があります。
4. 法定養育費と先取特権
法定養育費には、先取特権が付与されることになりました(改正民法第306条3号、第308条の2)。
先取特権とは、債権者(法定養育費の支払を請求することのできる人)が債務者(法定養育費の支払義務を負う人)の財産から、他の債権者より優先して債務の弁済を受けることのできる権利です。
この先取特権がある場合、債権者は、債務名義(請求権があることを公的に証明する書類、をいい、判決や調停調書、公正証書がこれにあたります)がなくても強制執行(債務者の財産を差し押さえること)をすることができます。
今までは、養育費の取り決めがない場合には、まずは養育費の調停や審判を経て、債務名義を取得してからでないと強制執行はできませんでした。
法定養育費の請求の場面では、調停や裁判等を経ることなく、直ちに相手の給与や預金の差し押さえをすることができるのです。
また、改正民法では、法定養育費のみではなく、離婚時に父母が離婚協議書等で取り決めした養育費についても、一定額については先取特権が付与されることとなりました。
養育費の差し押さえについては、こちらのコラムで詳しく解説しています。
5. 法定養育費の制度はいつから始まる?
法定養育費は、改正民法が施行された日から請求が可能となります。
改正民法の施行は、公布(2024年5月24日)から起算して2年を超えない日までに施行されると定められているため、遅くとも2026年5月23日までには改正民法が施行されます。
なお、改正民法の施行以前に離婚した場合には、改正民法の施行後であっても法定養育費の請求はできないため、注意が必要です。
6. 養育費に関するご相談は新静岡駅前法律事務所まで
法定養育費の制度が新設されることにより、離婚時に養育費の取り決めがなかった場合でも養育費が請求できることとなりました。
ただし、法定養育費はあくまで養育費の取り決めがない場合の暫定的な制度であると位置づけられていることから、額も最低限の金額とされる可能性が高いです。
養育費の取り決めをしていればより多くの養育費をもらえる可能性もあります。
また、相手が任意に支払わない場合の強制執行の手続きについては、ご自身のみでは対応が難しい場合もあるでしょう。
当事務所では、養育費に関するご相談の解決実績が多数ありますので、養育費に関してお困りの場合には、お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。