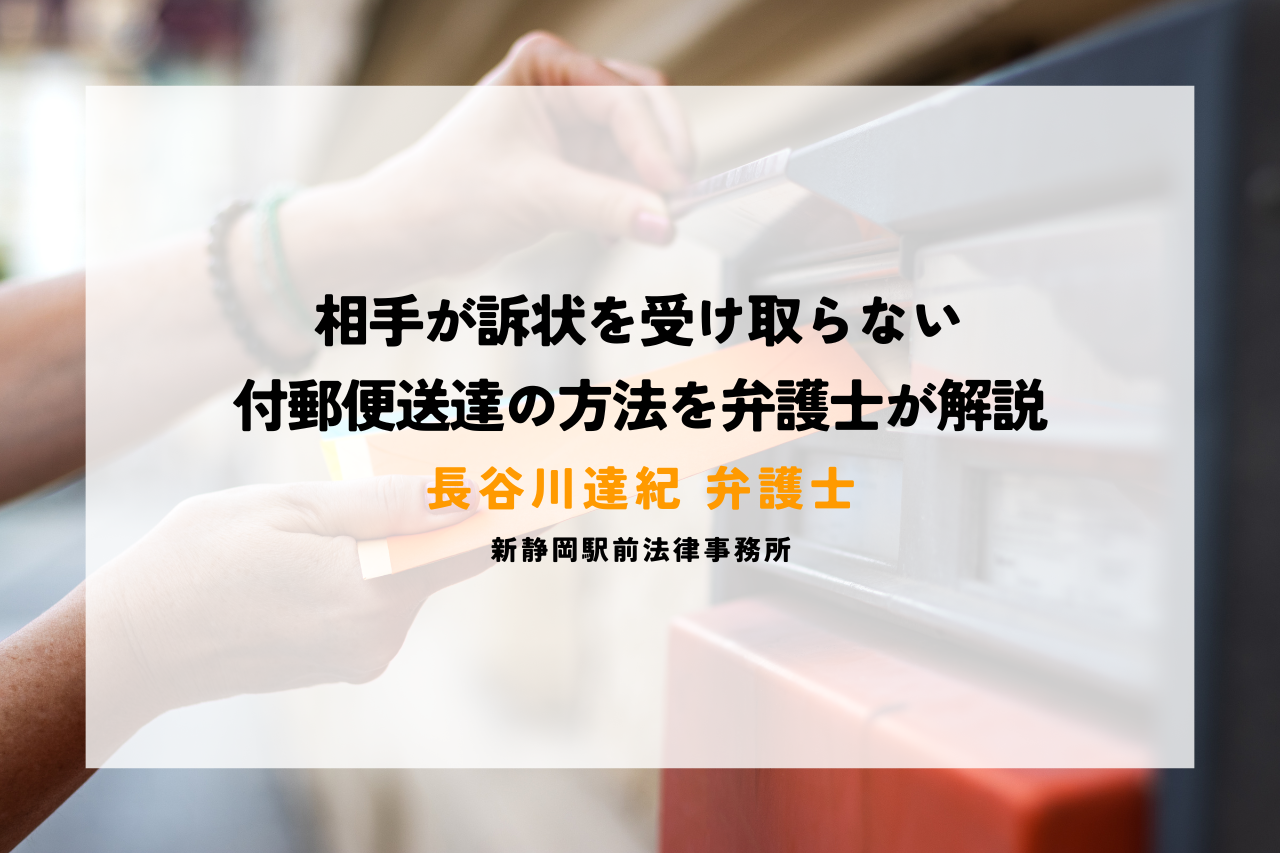相手方に訴訟を提起したいが、相手方が裁判所からの訴状を受け取らず、訴訟を開始できないことがあります。
このような場合に有効な方法が付郵便送達です。
本稿では、付郵便送達の方法を解説いたします。
目次
1. 付郵便送達とは
訴訟(裁判)は、裁判所が被告に訴状を送達することにより係属(開始)します。
そのため、訴訟の相手方が訴状を受領しない場合、訴訟を開始することができません。
「付郵便送達」とは、裁判所が被告に訴状を発送した時点で訴状を送達したものとみなす送達方法のことをいいます(民事訴訟法第107条)。
正式名称は「書留郵便に付する送達」といい、「書留送達」と呼ばれることもあります。
付郵便送達の場合、裁判所が訴状を発送した時点で訴状が送達したものとみなされるため、仮に被告が訴状を受領しなかったとしても、訴訟が係属することになります。
私の経験上、債権回収や詐欺被害の案件において、相手方が訴状を受領せず、付郵便送達を利用することが多いです。
2. 付郵便送達の方法
通常送達等が不奏功であること
いきなり付郵便送達制度を利用することはできず、まずは通常送達(特別送達)、休日送達(日曜日又は祝日を指定して送達する方法)、就業場所が分かっている場合には就業場所送達(相手方の就業場所等に送達する方法)を行うのが実務上の運用です。
通常送達や休日送達は、相手方の住民票上の住所地や現住所地に行います。
通常送達等を試み、「保管期間経過のため返還」となり、訴状が受領されない(通常送達等が不奏功である)場合に初めて付郵便送達を検討することになります。
相手方が訴状の送達場所に居住・在籍していること
付郵便送達制度を利用するためには、原則として、相手方が訴状の送達場所(住民票上の住所地、就業場所等)に居住又は在籍している、若しくは、居住又は在籍していると推認されることが必要です。
例えば、相手方の住民票上の住所地を送達場所として訴状を通常送達したところ、「あてどころ尋ねあたりません」という理由で訴状が返送された場合、同住所地に相手方が居住していない可能性が高いことから、付郵便送達はできません。
また、後述する調査の結果、相手方が訴状の送達場所に居住していないことが明らかになった場合にも、付郵便送達はできません。
相手方の住居所等が不明な場合には、付郵便送達ではなく、公示送達制度を利用することになります。
なお、公示送達については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
調査報告書の提出
裁判実務上、付郵便送達を認めてもらうためには、相手方が訴状の送達場所に居住・在籍していることを調査した上で、裁判所に調査内容をまとめた調査報告書を提出する必要があります。
調査の具体的な内容は、相手方の住民票・戸籍の附票の取得、携帯電話番号への架電、携帯電話番号・自動車のナンバーからの弁護士会照会、親族・知り合いへの事情聴取、不動産管理会社への事情聴取、現地調査などです。
現地調査は、相手方の住民票上の住所地等に赴き、呼び鈴を押したりノックをしたりして反応があるか、電気・水道・ガスメーターが動いているか、郵便物が溜まっているか、カーテンがかかっているなどの生活感はあるか、(夜に)部屋の電気は点いているか、近隣住民への聴取などを行い、写真を撮影するなどして資料化する必要があります。
調査の結果、相手方の居住・在籍が確認又は居住・在籍が推認できた場合には、調査報告書をまとめて裁判所に提出します。
なお、調査報告書と併せて付郵便送達を行う旨の上申書も提出することになります。
調査が尽くされていないと判断された場合、裁判所から追加の調査を求める連絡がありますので、その場合は裁判所の指示に従いましょう。
3. 付郵便送達完了後の流れ
付郵便送達が完了すると、第1回口頭弁論期日が行われます。
付郵便送達の場合、相手方が引き続き訴状を受領しない可能性が高く、実務上も、相手方は付郵便送達の方法により送達された訴状も受領しないケースがほとんどです。
そのため、相手方は、訴状の内容も第1回口頭弁論期日の日時も確認できていないことから、答弁書は提出されず、第1回口頭弁論期日に出頭して来ないことがほとんどです。
相手方が答弁書を提出せず、期日に出頭もしなかった場合、弁論は終結(主張や証拠の提出が終了)となり、判決期日が指定されます。
判決が言い渡されると、裁判所から判決書が送られてきます。
相手方への判決書の送達も付郵便送達になりますので、判決書が発送された翌日から2週間以内に相手方から控訴の申立てがなされなければ、判決が確定し、裁判は終了となります。
なお、付郵便送達の場合、相手方は判決書も受領しない可能性が高いため、控訴されるケースは非常に少ないです。
4. まとめ
上記のとおり、付郵便送達が認められるためには、調査が必要になり、特に住民票・戸籍の附票の取得や弁護士会照会手続はご自身での対応が困難で、また、現地調査の方法も非常に複雑で、詳細な調査報告書の作成も必要となります。
そのため、付郵便送達が必要となる可能性が高い案件については、弁護士に依頼し、調査や調査報告書の作成を一任することをお勧めします。
当事務所は、付郵便送達を多数経験しており、その知識と実績は豊富です。
当事務所への相談ないし依頼を検討されている方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。